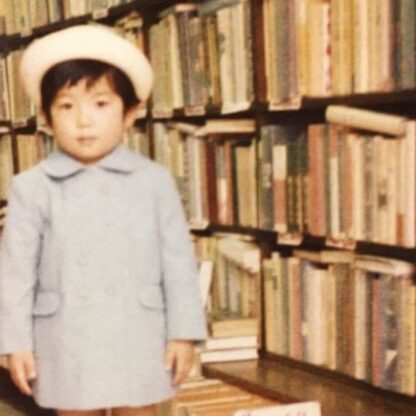“6月12日” 「蚤の目大歴史366日」 蚤野久蔵
*1893=明治26年 シベリアを単騎横断した福島安正中佐がウラジオストクに無事到着した。
1887=明治16年、ドイツ・ベルリン公使館に情報将校=少佐として赴任し、のちに総理大臣になる公使の西園寺公望のもとで活動した。当時、ロシアはシベリア鉄道を建設中で帰任に際してポーランドを経てロシア入り、ペテルブルグ、エカテンブルグ、外蒙古から東シベリアというルートを馬で踏破する命を受けた。開通すれば日本への脅威となる鉄道の建設状況や民情をつぶさに見聞して報告したことを評価され途中で中佐に昇格した。
前年2月11日ベルリンを出発、この日午後5時、最終目的地のウラジオストクに愛馬ウスリー号にまたがって姿を現した。日本貿易館の前には日の丸の旗を持った多くの日本人たちでごった返していた。やがて遠くに馬に乗ったひとりの日本人の姿を認めたとき一斉に歓声がわきあがった。踏破した距離は1万8千キロにのぼった。思いもかけない大歓迎に、あくまで<秘密調査>のつもりだった中佐は戸惑いを隠せない。受け答えも「天祐にも無事に」つまり天の助けもあって、などと遠征の中身には全く触れずじまいで終始した。これには各紙の記者も大弱り。大阪朝日新聞の西村天因記者はこう書き送った。
「両陛下の御真影の前に立ちて敬礼し、首を挙げて御真影を拝し、佇立之を久しうして去る能わず、傍より之を見れば両眼涙あり。嗚呼、中佐の孤鞭単騎シベリアに入るに当り固(もと)より生還を期せざりしは明らかなり」から始まって「実に中佐が涙は血にして血は大丈夫の奇なり。まさに一滴千金の涙というべし」まで意味のない<麗句>を連ねた。
大きく報道されたことで国中が快挙に酔った。「さっそうと馬にまたがり、あらゆる困難をものともせずにシベリアの荒野を行く寡黙な男」というところが受けたのでしょうなあ。でも何頭の<ウスリー号>を乗りつぶしたのだろう。29日の新橋駅頭は大変な騒ぎになる。
*1949=昭和24年 特集記事が噂になり書店では予約段階で月刊誌『文藝春秋』が売り切れた。
お目当ての記事は「天皇陛下大いに笑ふ」という対談で6月号に掲載されることになったが予約注文にも応じられない事態に急遽増冊する騒ぎになった。話術の天才の徳川夢声、人気詩人で作詞家のサトウハチロー、東大教授でフランス文学者の辰野隆の3人が宮中で<御前放談会>をしたら陛下が生まれてはじめて笑われたというものだった。
きっかけは文藝春秋の創業社長・菊池寛の一周忌(3月6日)に縁故の面々とバスを仕立てて出かけた多磨墓地への墓参の帰り。洋画家で俳優の宮田重雄が持ち前の大声で「こないだ夢声老とハッちゃんと辰野大博士が天皇さんのまえでバカばなしをして、陛下は生まれてはじめてお笑いになったらしい」と話したのを聞いた編集長の池島信平が「それ、いきましょう」と御前放談会の3人に<誌上再現>を注文した。
宮中への案内役は辰野。宮内府(宮内庁)から辰野に、陛下は国民と親しまれる方法をいろいろ考えておられるが民衆に親しまれている人たちと陛下がお話をする機会があればと<人選を一任>された。2時間の対談だから10ページ以上あるが一気に読ませる、いや聞かされるか。各自の紹介で陛下が笑われるところと最後のあたりを紹介する。
辰野:こっちは御案内役ですからね、両大人を御紹介しなければならないんだ。どうも仕様がない。「今日は図らずも昔の不良少年が、一人ならず三人まで罷り出でまして洵(まこと)に畏れ多いことでございます」と申上げたら、陛下が「あっ、そう。アッハアハア・・・」とお笑いになった。(笑声)
徳川:あの開幕がよかったですよ。
サトウ:傑作でしたね。
辰野:「徳川は私と同じ府立一中でございまして、ちょうど私と入れ替わりぐらいに入学した後輩でございますが、サトウのほうは中学校を五年間に八度も変わったそうでございますから、どこの中学とも申上げかねます」と申上げたら、アッハアハアとお笑いになって。
サトウ:それから二時間でしたね。
辰野:そうでしたね二時間。
* * *
徳川:陛下、鬼ゴッコなさるらしいですね。
サトウ:陛下は御存じかナ、鬼ゴッコを。
徳川:鬼につかまっちゃいけない、ということだけは御存じらしいんだ。だから、鬼が来るとお逃げになる。これが変わってる。ふつうは横へ曲がったり、木のまわりを廻ったりして逃げるでしょう。陛下は絶対そうじゃない。まっすぐ、どこまでもまっすぐ逃げておいでになる。(笑声)これ、洒落や冗談じゃない。全力を尽してまっすぐお逃げになる。
サトウ:いい話だね。
司会:ではこのへんで・・・
この座談会は多くの読者に拍手を持って迎えられた。前年わずか8万部だった『文藝春秋』はこの年に18万部、その翌年が28万部と10万部ずつ部数を伸ばす。これがきっかけとなって『文藝春秋』はやがて国民雑誌と呼ばれるようになる。初の社員公募で入社した池島はその後、社長に就任した。