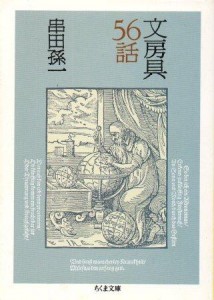書斎の漂着本(69)蚤野久蔵文房具
登山家、エッセイストとして研ぎ澄まされた独特な響きのある文章を多く残した串田孫一が「机上の小物たち」への愛着を綴った『文房具』である。月刊専門誌への連載が、1978年(昭和53年)に白日社から単行本として出版された。
身近な小道具でありながら、それゆえに日進月歩で変わっていく文房具。連載は大阪万博が開催された1970年(昭和45年)から74年(同49年)までの4年間にわたるちょうど48回分であるが、われわれ団塊世代が社会人のスタートを切ったなつかしい時代でもある。外函の裏に内容がデザインされているので「目次」代わりに紹介することにしたが、いまでは文具店でもお目にかからない<絶滅種>も多いのではないだろうか。
たとえばペン先、白墨、謄写版、吸取紙・・・同世代かそれ以上の方なら実際に使ったことがあるだろう。もっともペン先は英字などの飾り文字・カリグラフィーを書くためや、アニメの原画などには不可欠だから画材屋さんなど専門店に行けば揃う。白墨=チョークは学校現場での黒板がホワイトボードにとって代わって姿を消しかけたが、建設現場などで使われるからホームセンターにある。だが謄写版はコピー機の普及で絶滅したし、吸取紙もあの三日月形のホルダーと共に記憶だけに残る。
串田は「ペン先」を「母の手がインキだらけになっていたのを時々私は想い出す。もう何十年も前の話である。別にわざわざ悪い万年筆を使っていただけではないが、その頃は、万年筆はしばしばインキが流れ出して悲惨な目に遭うものであった。(中略)もう一つ想い出すのは、母の人差指の横のところに、青い点があったが、それは、うっかりしてペン先を立てて、インキが入ってしまったのだと私に話した。その点は母が死んで灰になるまで薄くもならずにずっと残っていたが、そんなことがあるものだろうか」と書き出す。小学校からフランス語を習っていたので、厳格なフランス人の先生にやらされたペン習字の想い出は「綴りを一つでも間違えると、その単語を三十でも五十でも書かせるのだった」と。最後は「ペンはペン軸にさしたまま筆立に立てておくのが普通であるが、酔っぱらってその上に尻餅をつき、立ちあがったらお尻にペンが五、六本ささってぶらさがったという話を最近きいた。いっぺんに酔いがさめてしまっただろうと思う」の挿話で結ぶ。
「白墨」では「白墨のかけらを利用して、どういうものか、骸骨を沢山造った。されこうべである。かけらを見付けると、ナイフでせっせとされこうべを造った。それを欲しがる友だちにはやり、自分では机や窓のへりにずらりと並べていた」。それが「昨年久し振りに中学校の同窓会に出席し、お互い歳をとった昔の友だちと話をしている時に、その中の一人が、私の文字を細かに彫った白墨をまだちゃんと持っていると言った。大事にとっておいてくれたというより、何となく残っていたのであろう。その話を聞いてから、今やったらうまく出来るだろうかと思いながら、造っていない」。時空を越えて、はオーバーかもしれないが文章展開の呼吸が伝わる。
「帳面」にはノートと呼びたくないわけ、「ぶんまわし」はコンパスの別名と説明される。「丸筒」では「私は最近、エヴェレストが中心に出ている、立派なヒマラヤの地図を友人から貰った。遠方からそれを郵便で送って来たが、手製の丸筒に入れ、その芯には、別の紙が固く巻いてあった。それはどこにも皺が出来ずに無事に届いた。最初から畳んである地図であるならば、それが地上最高の山とその周辺のものあろうと、どうということもないが、刷り上ってから、さまざまな人の手に渡りながら、結局私のところに届くまで、どこにも折目がつけられなかったとなると、今無造作にそれを畳んでしまう気にはなれなかった。結局丸筒に入れて保存することになる」というその効用が。続くのは、時々おじいさんが娘に代わって店番している文具店で謄写版の原紙を買った話である。「ぼんやりと店の中を見廻しているのが悪かったのだが、二枚の原紙をおじいさんは丁寧に八つに畳んで、しかも折目を指先でしごいて紙袋に入れてくれた。無駄な買い物になった」と苦笑を禁じ得ないエピソードと対比される。
白日社版『文房具』は、彩色版画を添えた65部の限定版まで出版されて即完売となったらしい。その後は『文房具52話』として1996年(平成8年)に時事通信社から、2001年(同13年)にこの『文房具56話』がちくま文庫から出されているからどちらかは入手可能だろう。
書き加えられたのは、ワインの瓶の下半分を切り取った筆立が東側に窓のある書斎なので日光が差し込んでいるわずかの間だけ光ることを見つけて感動した「緑の光」。「貝光」は紀伊半島を旅した友人から貰った宝貝を、書き損じて小刀で丁寧に削った字をこの貝でこするとすべすべになり目立たなくなる。これは筆者の単なる思い付きだったが中国・明の書物で中国では古くから紙を磨く際に、貝の滑らかなところでそれをやっていて「貝光」と名付けていることを知ったという話である。
あらためて『文房具56話』にある「後記」を読んでいて「この連載の文章が初めて単行本の形をとって書店の店頭に並べられたのは、連載から五年後の一九七八年であった。その時の初版は、今方々探しても見当たらず、十月二十五日発行の一箇月後の十一月二十五日の第二刷が出て来た。こんなことは私の本の場合は大変珍しい。単行本にした白日社の社長は悦んでいたと思う」とあった。「ひょっとしてこれは初刷か?」と思って奥付を確かめたら、翌年三月二十三日の第三刷であった。なんだか下世話な終わり方になってしまったがお許し願いたい。