新・気まぐれ読書日記 (47) 石山文也 文庫解説ワンダーランド
このブログを愛読されている先輩の某氏から久しぶりのリクエスト。「文庫か新書で、何か面白い本ない?」続けて「寝転がって読むにしても単行本は重いからね」とのたまう。おざなりに答えるわけにはいかないし、単行本を文庫化したのを勧めると「それ読んだ」とくる。そうなると新書かな、というわけで年初から読んだのを机の上に並べてみる。川上仁一の『忍者の掟』(角川新書)、呉座勇一の『応仁の乱』(中公新書)、武田徹の『日本ノンフィクション史』(同)は私の好きないわゆる歴史関連。高村薫の『作家的覚書』(岩波新書)と養老孟司の『京都の壁』(PHP新書)は連載を一冊にしたものだし、無類の犬好きゆえ倉阪鬼一郎の『猫俳句パラダイス』(幻冬舎新書)はお気に召さないだろう。<辛口評論家>吉川潮の『毒舌の作法』(ワニブックスPLUS新書)は「悪口と毒舌は違います」とはいうものの「何で」と言われそう・・・。それにしてもよく読んだなあ、とつぶやきながら斉藤美奈子の『文庫解説ワンダーランド』(岩波新書)を選んだ。
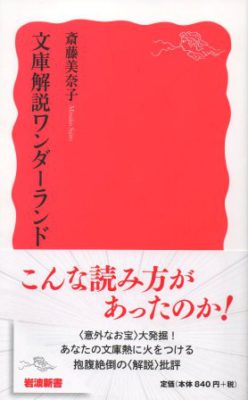
斉藤美奈子著『文庫解説ワンダーランド』(岩波新書)
見返しに(文庫解説を)「基本はオマケ、だが人はしばしばオマケのためにモノを買う」とある。まさしくその通りだから、帯にあるように、抱腹絶倒の<解説>批評であるし、「こんな読み方があったのか!」と楽しんでもらえそうだ。
取り上げるのは内外の約40冊の解説、よく知られた作品ばかりだがサブタイトルでまず笑わせる。夏目漱石の『坊ちゃん』は「四国の外で勃発していた解説の攻防戦」、川端康成の『伊豆の踊子』と『雪国』は「伊豆で迷って、雪国で遭難しそう」、林芙美子の『放浪記』は「放浪するテキスト、追跡する解説」とくる。太宰治の『走れメロス』に至っては「走るメロスと、メロスを見ない解説陣」と、どれから読もうかと迷ってしまう。シェイクスピアの『ハムレット』は「英文学か演劇か、それが問題だ」、バーネットの『小公女』は「少女小説(の解説)を舐めないで」、渡辺淳一の『ひとひらの雪』はエロスの世界を意外にも女性作家が担当して「解説という<もてなし>術」を展開する。最新作では百田尚樹の『永遠の0』に「軍国少年と零戦が復活する日」という具合だ。
なかでも「試験に出るアンタッチャブルな評論家」とした小林秀雄は<コバヒデ>の愛称で登場する。もちろん著者の、である。テキストは『モオツァルト』、『無常という事』、『Xへの手紙』。しかも解説は江藤淳が<コバヒデ専属>なのだという。江藤は慶應大学在学中に『夏目漱石論』で華々しくデビューし、評伝と批評の間をいく『小林秀雄』で文芸評論家として地位を固めた。小林とは30歳違いで父と息子ほど差がある新鋭だったが「江藤君なら」と容認、いや大抜擢したのであろうか。ならば解説がわかりやすいかというと、さにあらず。文庫解説の中でも特殊な部類に属する文芸評論の解説は、解説を読んでも本文の理解の助けになることはなく、もっと頭が混乱することも少なくない。日本を代表する批評家二人の最強のタッグ、文庫解説とは「権威を権威たらしめるツールとして機能する」のだと喝破する。
対象作品であれ、解説であれ、それでも理解できなかった場合はどうするか。対処法は「薄目を開けて読む」。能を鑑賞するごとく、わからなくてもいいから幽玄の世界に遊ぶことだろうと指南する。でも私の場合、そうしたところで神秘体験のようにコバヒデが降ってくることはないだろうね、いまさら。
「あとがき」で、著者は文庫本の巻末についている「解説」は誰のためにあるのだろうとあらためて触れている。書く前は「読者のため」に決まっている、と思っていたが、さまざまな文庫の解説を読んでみると、そうとばかりもいえないケースが少なからず存在することに気づいた。「読者のため」ではないとすると、誰のため?ひとつは「著者のため」、もうひとつは「自分のため」であると。
文庫解説はどうあるべきかという問いに正解はない。読者としては、メディアリテラシー(=たくさんの情報メディアを主体的に読み解くことで真偽を見抜き活用する能力)を磨いて、解説をも批評的に読むのが最良の対抗策と結ぶ。いま流行の新語でうまくまとめられてしまった。
ではまた






