季語道楽(39)隠れ歳時記の自在さ(その2) 坂崎重盛

“死”と“笑い”の歳時記
前回、太宰治、久保田万太郎の忌日が、夏の季題になっていることにちょっとだけふれて、先に進んでしまった。市販の一般的な季寄せや歳時記を手にする人なら周知のことながら、巻末の「付録」の項目の中に「年中行事一覧」や「二十四節気表」などとともに、歴史上の人物、著名文化人、作家、俳人等の亡くなった日“忌日”の一覧表が掲載されている。(本によっては「宗教」の項目の中にあるものも)その人の“忌日”が、そのまま季語になったわけである。
ところで、ふと思い出して、本棚の俳句関連の本をチェックすると、ありました! 文学者の忌日だけを収録したものが。佐川章『文学忌歳時記』(一九八二年・創林社)

文学忌歳時記 著:佐川 章
著者の佐川章(さがわ・あきら)は、ぼくにとって初の名だが、略歴によると一九四一年茨城県生まれ。法務省を経て、この本を出した時点では都立紅葉川高校で国語の教諭。論文として「長塚節の『家意識』に関する一考察」「太宰治『津軽』考」がある。
この『文学忌歳時記』(ハードカバー、204ページ)の概要だが、例によって、本を手にして帯を熟読する。その著作のあらましを紹介するときに、その本づくりを担当した編集者(ときには著者自身)が文案を考え、作成した帯の文を引用するというのは、いかにも安易なことのように思われるかもしれないが、同じく本づくりをしてきた人間としては、まったく、そうは思わない。
帯の文章は、そんなに軽々しいものではない。そこには著作の執筆における真意、本全体の構想、力説したい部分などや、編集者、出版社側としては読者にどうにか手に取ってもらい、購読してもらいたい、という気持ちがつづられているのだ。
まあ、オーバーにいえば帯(腰巻きともいう)は“切れば血の出る切実なコピーである、”とぼくは思っている。ということで『文学忌歳時記』の帯を見てみよう。表①では、
樋口一葉から向田邦子まで、今は亡き代表的文学者二六五名の、
死因、最後の言葉、縁故者の回想、墓所などを、死亡月日別に
網羅した初の本格的点鬼簿。(付∕主要文学忌案内、埋葬墓地一覧・
死因ベスト五五他)
とあり、表④帯には、
ぶっ倒れても、
ペンと紙は忘れるな、
地べたの上で、血でもって、
豆のような字で、
書きつづけろ。
みんなそうして書いて、
書いて、
みんなそうして、
死んだのだ。
(高見順「自らに与える詩」より)
と、作家・高見順の言葉を引用、掲載している。では、本文を見てみよう。例えば八月の項。
8月2日 三富朽葉忌。
“天才象徴詩人”。大正6年(一九一七年)のこの日、友人の
今井白楊(詩人)と千葉県犬吠埼君ケ浜で遊泳中、溺れた白
楊を助けようとしてともに波にのまれ溺死。二十八歳。死亡
時刻、午後2時。
8月3日 吉田健一忌
評論家・英文学者・小説家。昭和五十二年(一九七七年)
のこの日、東京・新宿区払方町の自宅で肺炎による心臓衰弱
により死亡。六十六歳。死亡時刻、午後6時0分。(中略)
墓・横浜市久保山の光明寺。
この二人の忌日の記載の少々特異なところは、死因や埋葬されている墓地名はともかく死亡時刻までも言及しているところである。そして、もうひとつ、忌の歳時記とはいえ、生まれ年や生地についてはほとんど触れていない。その人が何年生まれだったのを知りたければ、死亡年から年齢を引かなければならない。
もうひとつ興味深かったのは、帯にも記されていた「文人死因ベスト5」。もちろん、この本の出版された一九八〇年頃までのことになろうが、第1位は癌、2位は結核、3位は自殺、4位は肺炎、5位は脳出血となっている。ここで目にとまるのは3位の自殺。これによって、かつて文学は、自らの命を賭した格闘だったことがうかがえる。
その他、「夭折の文人一覧」「長寿を保った文人」「文人二世一覧」など他の忌日記では、あまり目にしないデータも掲載されている。
ただ、惜しむらくは、“歳時記”をタイトルとしてうたいながら、その忌日に因んだ例句が一切掲げられていないことである。
たとえば、他の歳時記では芥川龍之介の「河童忌(かっぱき)」(「我鬼忌」とも)では、
河童忌の庭石暗き雨夜かな 内田百閒
河童忌や河童のかづく秋の花 久保田万太郎
河童忌や表紙の紺も手ずれけり 小島政二郎
娼婦来てベッドに坐る我鬼忌かな 角川春樹
といった印象ぶかい句が紹介されている。(角川春樹編 『合本現代俳句歳時記』一九九八年 角川春樹事務所)
つまり、佐川章による、この『文学忌歳時記』は、文学者の“死の博物誌”に近く、俳味のある歳時記とは無縁というところが少々もの足りない。ただ「あとがき」にあるように、「取材からはじまって脱稿するまで二年の歳月を要し」、取材した文学者は遺族の方々をはじめ「二百六十余人を数えた」という労作である。
さて、次に控えている歳時記は、矢野誠一『落語︱︱長屋の四季』(昭和四七年・読売新聞社刊)。ぼくが手にしているのは、ハードカバーの元本だが、のち『落語歳時記』と改題。和田誠のカバー画による文春文庫が入手しやすい。
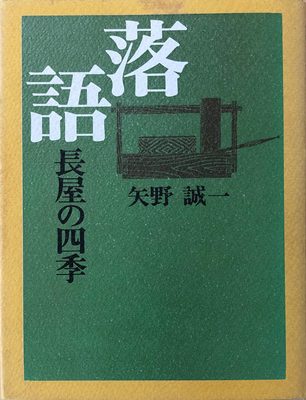
落語 長屋の四季 著:矢野誠一
では「死」のあとに「笑い」の歳時記を、ちょっとのぞいてみたい。例えば、いまの季節、「夏」の章では「酔豆腐」「鰻の幇間」「船徳」「洒落小町」「大山詣り」といった落語の演題とともに「短夜」「蚊帳」「暑さ」「祭」「川開き」「井戸替え」といった季題が並ぶ。
自らも俳号・徳三郎として俳句に親しむ(銀座の歴史あるタウン誌「銀座百点」の「銀座百点句会」の席で、何度かお目にかかっている)、いま、落語、講談など古典芸能ものを書かせたら随一といわれる、この粋人の粋筆を味わってみよう。
にしても、ご自身の俳号を、色男の代名詞みたいな、「「徳三郎」とするあたり、さすが洒落がキツイ方ではある。
矢野誠一の『落語——長屋の四季』の夏の章。ぼくも子供のころから聞いていて、馴染みぶかい『酢豆腐』。これが季語の「短夜」と付けられている。
冷蔵庫などなかった時代は、豆腐なども夜の短い夏の季節、一晩でダメになってしまう。そこで季題は「短夜」。「甘酒」が夏の季語であることはふれたはずだが、かつては「一夜酒(ひとよざけ)」といった。夏の時期は、やはり一晩米麹が甘酒となるからだ。
ところが“酢豆腐”――甘酒はショウガなどをすって美味しい飲み物となるが、すえて酸っぱくなった“酢豆腐”なんて、もちろん、食べられたものではない。これを、かねてから気障(きざ)と思われている少々浮世離れした若旦那の知ったかぶりにつけ込んで食べさせてしまおうという噺。
ぼくは八代目文楽・黒門町の師匠で聞いていた。文楽演ずる気障な若旦那、町内の若い連中から見れば、鼻持ちならない存在ではあったとしても、演じる文楽の人柄だろうか、さほど嫌味な人物ではなく、むしろ、こんな人物が町内に一人くらいいたほうが、罪のない話題のタネになるという、印象を受けた。
知ったかぶりをしたために、カビが生えて腐りかかった豆腐を食べざるをえなくなった若旦那は、気障と思われても、むしろ世間知らずのお人好しという、愛すべき、とまでは言わないにしても、同情に値するキャラクターなのだ。
この落語の存在があって、国語辞典に「酢豆腐」という言葉が載り、「知ったかぶりをする人、きいたふう、半可通」などと解説されている。
著者は「酢豆腐」をめぐって、それこそ「酢豆腐」を地で行った国語辞典の説明や、この演目の東西のバリエーション、改作などを紹介、季語「短夜」として、次の四句を紹介している。
みじか夜や金商人の高いびき 正岡子規
薄化粧して短夜の女客 𣘺本静雨
明易き夜の夢にみしものを羞(は)ず 日野草城
短夜のあけゆく水の匂ひかな 久保田万太郎
子規の句は、現実に、どこかの旅の宿で体験したことか、いや、小説の一シーンから? 三句目の草城は、ここでも女人(新妻?)にこだわる。「羞(は)ず」なんて言ってますが、本気で羞じてなんかいません。いわば、ノロケているんです、夢の中のことまで。
次の万太郎の句は、「水の匂ひ」で、いかにも点が入りそうな句。それにしても繊細な感覚ですね、あの蟻のような微小な筆跡同様。さすが「湯豆腐や命のはてのうすあかり」「鮟鱇も我が身の業も煮ゆるかな」の作者。
「短夜」といえば、他の雑誌で永井荷風の世界を“理系感覚の人”の営みと見立てての連載をスタートさせたが、毎回、荷風作品のタイトルを読み込んだ句を小見出しがわりに作っている。次号は『問わずがたりに』ふれたので、「短夜や問わず語りの杯二つ」という駄句を掲げた。
さて隅田川、夏の噺となれば『船徳』。これもまた黒門町の師匠の持ちネタ。ダメな若旦那を演じさせたら、やはりこの人でしょうね。
噺はポンと、「四万六千日、お暑いさかりでございます。」で、この季節と舞台を浮かび上がらせる。季語はもちろん「四万六千日」、浅草観音で「鬼灯市(ほうずきいち)」が開かれる。
矢野大人の解説から、
落語という芸は、ぎりぎりに煮つめられた、言葉の選択がなされている
ところに、魅力がある。余分な、わずらわしい表現を嫌うのである。その
へんに、同じ話芸でありながら、この芸が、講談や浪曲とは明確な一線を
画している理由がひそんでいる。
と、落語という芸の特質にふれたあと、
そうした、無駄のない、見事な手法がこの『船徳』の、
「四万六千日、お暑いさかりでございます」
という、原稿用紙にしてたった一行におさまる言葉による、あざやかな
場面転換にうかがえる。
という。そして挙げられる句は、「四万六千日」といったら、まず、この句。久保田万太郎の、
四萬六千日の暑さとはなりにけり
そしてもう一句は、悪徳と欲望の人間関係を描いたら、この女流作家・山崎豊子の、
四万六千日の善女の一人われ
自分を「善女」と言う、意外なほどの無邪気さがあったのですね、この作家には。
二句だけでは、ちょっと寂しいので、他の歳時記から引く。
炎立つ四万六千日の大香炉 水原秋桜子
鬼灯市に遭いし人の名うかび来ず 石田波郷
鬼灯市夕風のたつところかな 岸田稚魚
三句目は、夕方となって、やっと境内で売られる鬼灯の葉や実がゆれる風がわたる、猛暑の中の涼の気配をとらえている。
『鰻の幇間』は、世間ずれしているはずの野幇間(のだいこ)(略して“ノダ”)が、旦那とおぼしき人物(?)から「うなぎ」をネタに、ひどい目に合う、という、聞いていて、笑いつつも(悪どいなぁ、こいつは!)とあきれた気持ちにさせられる噺。
と、詳しく紹介したいところでは、ありますが――「おあとがよろしいようで」――。
誠一旦那の次の歳時記本に移りたいので。
この著者の︱︱『志ん生のいる風景』『戸板康二の歳月』『文人たちの寄席』『大正百話』『三遊亭円朝の明治』『荷風の誤植』と言った著作は、タイトルを知ったと同時に入手している。
ところで、先の“落語歳時記”と並んで、同じ著者によるもう一冊、『芝居歳時記』(平成七年・青蛙房刊)についても少しふれておきたい。「初芝居で酔うて顔見世を心待ち」——春なら『道成寺』、冬には『夕鶴』。芝居にだって旬はある︱︱と帯に。

芝居歳時記 著:矢野誠一
例によって、この原稿を書いている季節の「夏の部」を見てみよう。ところで、今年の梅雨、なかなか明けなくて、コロナははびこるし、部屋は湿っけるし、手書きゆえの原稿用紙も文章も、なにやら湿りがち。
まっ、そんなことはどうでもいい。目次をざっと眺める。著者と違って芝居通ではないので知らない演目もある。まずは、おなじみのところで、『東海道四谷怪談』。季語は「蚊帳」、もちろん夏。
旅の温泉宿で「よかったら、蚊帳をお吊りしましょうか。久しぶりに蚊帳を吊って寝たいなんてお客様もいらっしゃるんですよ」と旅館の人に言われた著者は、“蚊帳の季節には少しばかりはずれていたので”と「ご遠慮」して惜しいことをしたと後悔した、と記したあとに、
わが影の身を起こしたる蚊帳の裡(うち) 山口誓子
「なんて気分を味わってみるのも悪くなかったはずである」
と述懐している。
仮にですよ、このとき、仮にですけど、著者がお忍びの女性連れだったら、どうだったかしら。
いいじゃないですか! 色っぽくて、蚊帳! でも、女中さんの手前、下心が見透かされそうでと、やっぱり「けっこうです」とか断ったかもしれませんねぇ。ぼくだったらそんなスチュエーションの場合、根が素直なものだから「はい、喜んで」とか、どこかの居酒屋の店員さんみたいな応えをしただろうなぁ。
そう、話は「東海道四谷怪談」
蚊帳を舞台の小道具として効果的に使った芝居として、すぐ
に思い浮かぶのが『東海道四谷怪談』。ご存知鶴屋南北の名作で
ある。この芝居のハイライトというべき、雑司ヶ谷の民谷伊右
衛門の浪宅の場面で上手に蚊帳が吊ってある。
この蚊帳は質草のためにはずされてしまうのだが……ここからが、ご存知、毒薬で変貌してゆくお岩のコワーイ怪談話となる。
矢野氏、この怪談、あまりにも有名ということもあってか、「昨今の質屋さん、こんなものでも預かってくれるのかしら」とさらっと収めて、
濡れ髪を蚊帳くぐるとき低くする 𣘺本多佳子
旅の蚊帳書架すれすれに吊られたる 稲柴 直
の二句を掲げている。
夏の季節なので、もう一つ怪談で行ってみよう。こちらもおなじみ『牡丹燈籠』。もちろん三遊亭円朝の作。
もとは中国、明の時代の怪奇小説『剪燈新話』。これを、日本の仮名草子『伽婢子(おとぎぼうこ)』がうつしかえ『牡丹燈籠』としたものを、圓朝が自身の見聞なども交えて怪談話として高座にかけたという。このあたりのウンチクは高座での“マクラ”で語られたりすることもある。
ところで、この圓朝の『牡丹燈籠』の聞き書き本(速記本・明治十七年刊)が、当時のベストセラーとなる。江戸の戯作文より、さらに話し言葉に近い言文一致の文体ここにはじまる、ということは日本近代文学史的には、かなり有名な話。
著者は、
いまさら幽霊でもという時代だが、いやそんな時代ならこそ、
夏は怪談がふさわしい。
とし、牡丹を季語とする三句を挙げている。
夜の色に沈みゆくなり大牡丹 高野素十
あしたより大地乾ける牡丹かな 原 石鼎
黒髪を男刈りせり牡丹咲く 殿村莵絲子(としこ)
三句目の「黒髪を……」の句がちょっと気になるが、深追いせず。
和物の演目ばかりではない。「競馬」は季語としては「くらべうま」で夏の季語。というのは、毎年五月五日、京都・賀茂神社では、五穀豊穣、国家安寧を祈る神事として「賀茂競馬」が行われる。また、今日、全国競馬ファンが手に汗にぎるダービーも、五月末の日曜日開催のため、当然、夏の季語とされている。この本の演目では、「競馬」は賀茂神社の「くらべうま」でも日本のダービーでもなく、本場イギリス、アスコット競馬場での『マイ・フェア・レディ』である。ご存知のごとく、オードリー・ヘップバーン主演で大ヒット、その後、日本の舞台にも。しかし、紹介の三句はいずれも「くらべうま」
くらべ馬おくれし一騎あけれなり 正岡子規
競べ馬一騎遊びてはじまらず 高浜虚子
競べ馬賀茂の川風樹々縫いて 日高曲人
因みに手元の『俳句外来語事典』(大野雑草子編・博友社刊)のダービーの項をチェックしてみると、
ダービーの蹄駆け来るラジオの中 富永寒四郎
銀座雑踏ダービーに湧く群れもゐて 河野南睦
の二句があった。
もう一つ、洋物で『ベルサイユのばら』。で季語は「巴里祭」。一七八九年七月十四日は、パリの市民がバスチーユ監獄を襲撃フランス革命の幕が開く。この歴史上の事件を背景に、漫画家・池田理代子が『ベルサイユのばら』を発表、それを宝塚歌劇団が舞台に上げ、空前の「ベルばらブーム」が起きる。
澪パセリ廚にひかり巴里祭 大町 糺
濡れて来し少女が匂う巴里祭 能村登四郎
巴里祭や神父の草の赤ワイン 戸板康二
と、さすがに三句ともハイカラな雰囲気。
以上、『芝居歳時記』から夏の季語とその演目を四つばかりピックアップしてみたが、はたして春夏秋冬、全部で何項目について語られているのか? 目次で数えてみた。七十二項目。つまり七十二の季語と、それに関わる七十二の演目。
この矢野誠一旦那の、いつものことながら、たっぷり時間と体験を積み重ねてきた人ならではの大盤振る舞いの随筆的歳時記の一冊である。







