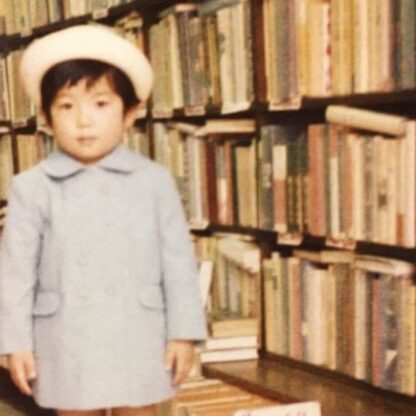“12月27日” 「蚤の目大歴史366日」 蚤野久蔵
*1924=大正13年 北海道・小樽港で陸揚げ中のダイナマイトが爆発、100人以上が亡くなった。
沖仲士を組織する栗山組の作業員が艀船の積荷の木箱入りのダイナマイトを国鉄・手宮駅構内に陸揚げ作業中に手を滑らせ落とした衝撃で爆発、艀船の約800本に誘爆した。爆発で港に停泊中の十数隻が沈没、倉庫や事務所多数が吹き飛び構内に野積されていた石炭にも引火して火災を起こした。周辺の建物は窓ガラスがすべて壊れ、民家では火事が起きた。
朝日新聞には社会面トップで「小樽市手宮驛近くでダイナマイト大爆発す 百餘(余)名慘死重軽症無数を出す 家屋の倒壊、船の沈没夥し」に続いて「死体散乱す 粉砕した貨車四両 死体廿一重傷者五十名収容」「黒焦げ死体に縋って号泣する家族、土中から助けを呼ぶ声」と生々しい惨状を伝えている。爆発と火事との関係については爆風でストーブの上の棚にあった揮発油壜が落下して破損、ストーブに引火して12戸を全焼したと報じた。
病院に運ばれた作業員の談話「海岸から20間(=36m)ばかりのところに繋留してある艀船の中で突然雷のような光が閃いたと思うと続いて大爆音を聞きました。それから後はあたりが真っ暗になった。気の付いたときは病院に運ばれていました」(小樽電話)
手宮駅は小樽港の埋立地にあり1880=明治13年に札幌までの鉄道が開通、その後、炭鉱のある内陸部の幌内まで延伸され幌内線の始発駅として石炭や海産物の積み出しでにぎわった。ダイナマイトは炭鉱で使われるためだった。手宮・南小樽間の手宮線2.8キロは1985=昭和60年に廃線になり駅跡地には鉄道・科学・歴史館の小樽市総合博物館になっている。
*1627=寛永4年 江戸の数学家・吉田光由の実用数学書『塵劫記(じんこうき)』が発刊された。
吉田は京の豪商で保津川や高瀬川の開削事業を手がけた角倉了以の一族で1598=慶長3年に生まれた。幼いころからそろばん塾で学んだが塾長がすぐに「教えることがない」というほどに上達、長じて算学=算術を勉強して数学家となった。多くの数学書を研究し豊かなアイデアで都の人々の暮らしに合うように構成し直したことでも知られる。
たとえば「九九の暗唱順」がある。中国から伝わった九九は平安時代の970=天禄元年、源為憲が作った子供用教科書『口遊(くちすさび)』には「九九八一、九八七二、九七六三・・・」と紹介されている。これを吉田は我々が覚えたのと同じように「ニニンガシ、ニサンガロク、ニシガハチ・・・」と順序を逆にした。原本は同じように漢数字で書かれているがわかりやすく勝手に片仮名にした。そうです、確かにこちらのほうが覚えやすい。私、逆から書くときには電卓で<検算>しましたもの。
『塵劫記』は土倉(金融業)を営んでいた角倉家でもすぐに役立つよう実践的な問題もたくさん盛り込まれている。
「三百四十五石の米を半年間貸す。その間の利率は年二割六分とすると元利合わせていくらか」
「絹一反は長さが二丈六尺である。一反の代銀が三十匁であれば一丈八尺の代はいくらか」
などという問題が並び、「答」と「法=解き方」が解説されている。
発刊後間もなく海賊版が出たのか4年後の1631=寛永8年版は日本初の多色刷りの鮮やかな豪華本に仕上がった。以後、明治時代までに数百種類が発行され日本初の理科系ミリオンセラーとなった。『塵劫記』の名付け親は天龍寺の長老だった光玄老師で「蓋し塵劫来事糸毫不隔」つまり<未来永劫、長い年月がたっても変わらない真理の書>の意味という。
*1198=建久8年 相模川の新橋落成供養からの帰途、征夷大将軍・源頼朝が<落馬>した。
橋は重臣の稲毛重成が亡き妻の供養のために架けた。落成法要は以前から約束もあって参列したが、そこからの帰りに何らかの<変事>が起きた。頼朝が53歳で亡くなるのはそのわずか17日後である。落馬説は<通説>ではあるが、武人で乗馬は得意だったろうし、お供が手綱を曳いていたのだから急に体調が悪くなり馬上から落ちたのか。落馬は<結果>だとすればその前に<原因>として脳卒中などが起きたことも考えられる。
他にも付近が「馬入川」の別名で呼ばれることから「馬が暴れて相模川に入り溺死した」という<溺死説>をはじめ「平家滅亡を怨む何者かに暗殺された」とか「壇ノ浦に沈んだ安徳天皇の亡霊を見て驚いて落馬した」いう<怨恨説>から「愛人のところへ忍んで行く途中に警備の武士に殺された」という<夜這い失敗説>まである。
本当のところはどうなのか。あれほど頼朝の成功譚を書き連ねた鎌倉時代の歴史書『吾妻鏡』にもこの17日間は空白のままである。馬といえば頼朝は平治の乱で敗れ、京の都から落ちのびる途中、近江・野路(現・草津市)で馬上で眠り一行からはぐれ、落人狩りで命を失いかけた。このときはもちろん落馬はしなかったが<眠りこけた>ことは間違いない。この逸話からも<頼朝と馬>との微妙な関係は死ぬまで続いた。