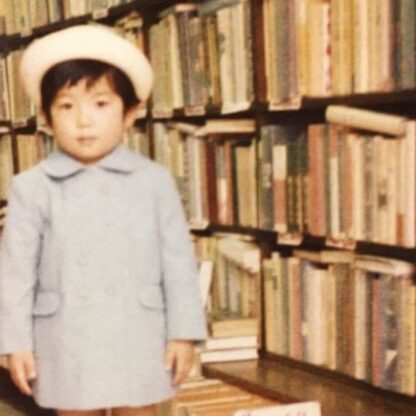ジャパネスク●JAPANESQUE かたちで読む〈日本〉 3 柴崎信三
〈日本〉をめぐる造形、時代のイコンとなった表現。その〈かたち〉にまつわる人々の足跡を探して、小さな〈昨日の物語〉を読む。
3 〈女性〉について
「蝶々夫人」と「花子」
オペラ歌手の岡村喬生の演出によるジャコモ・プッチーニのオペラ『蝶々夫人』(マダマ・バタフライ)が、イタリア・ルッカのプッチーニ・フェスティバルで上演された。2011年夏のことである。初演から1世紀以上たったイタリアオペラの定番を、原作者の故郷で演じるこの舞台が注目されたのは、原曲の台詞やト書きの一部を作品の背景となった日本の演出者が「訂正」して上演したからである。
結果は地元で大きな反響と評価を呼んだ。「正しい日本の姿を知った」「新しい蝶々夫人像を見ることができた」といった声が、有力メディアにも相次いで掲載された。
『蝶々夫人』は1904年の長崎を舞台に、地元の没落した藩士の娘で芸者となっている蝶々と、寄港した米国の海軍士官ピンカートンとの悲恋を描いた作品である。
蝶々は戦艦エイブラハム・リンカーンで長崎にやってきたピンカートンと出会い、愛をはぐくむ。そして信仰をキリスト教に改めて結ばれるが、生まれた子と蝶々を残して夫は3年後に帰国してしまう。「戻ってくる」という言葉信じて待ち続ける蝶々の前にやがて現れたのは、夫が祖国で結婚した妻のケイトで、「子どもを引き取りたい」と要求する。
一途の愛を砕かれて絶望した蝶々は、覚悟を決めて座敷に幼い子に目隠しをさせて遠ざけた後、仏壇の前で父の遺愛の刀を取り出し、「名誉のために生けることかなわざりし時は、名誉のために死なん」と書かれた銘を読みあげ、のどに突き刺し自裁する―。
武士道と芸者、満開の桜、純愛とその裏切り、日本刀による自刃など、当時の西洋の目に映ったジャポニスムの断片が散りばめられた作品である。岡村がこれを敢えて「訂正」して上演したのは、半世紀以上も前にドイツに留学して以来、歌手や演出家としてこの作品に接してきた経験から、プッチーニの原作にまつわる日本文化への誤解や偏見が日本人としていたたまれない、という気持ちを抱えてきたからであったという。
「間違いを演じることはもちろん日本人として苦痛ですが、日本と国とその文化を正しく世界に伝えられなくてはならないし、それは日本人の芸術家としての責任であり、義務でもあるはずです」
オペラ『蝶々夫人』のいくつかの場面や台詞への違和感は、岡村がオペラ歌手として半世紀以上も前にイタリアへ留学し、欧州各地で舞台に立ってこの作品を経験するなかで、拭いがたい感覚として蓄積されてきたようである。
キリスト教に改宗した蝶々に対し、叔父の僧侶〈ボンゾー〉がなぜか丁髷姿で登場して「カミサルダーシコ!」(「神猿田彦」の意)と罵る場面がある。1969年にドイツのケルン歌劇場の舞台で岡村が〈ボンゾー〉を演じたときには、演出で丁髷姿はもとより、手には「南無妙法蓮華経」の文字を逆さに記したミニチュアの鳥居を手に持たされた。烏帽子を被った〈ボンゾー〉や長崎の海の彼方に富士山が描かれた背景、日本家屋のなかを土足で歩く人物、着物の裾をたくしあげた蝶々―など、途方もない演出を数えればきりがない。
プッチーニの代表作としていまも世界中で演じられているこの作品が、こうした誤解を若い世代に拡散し続けていることへの疑問が、自ら原曲を訂正した「改訂版」の現地上演へ踏み切らせたのである。岡村がこの二幕三場のオペラの原作で「誤解」として指摘した台詞とト書きは11箇所ある。そのおもなものをここに挙げてみよう。
▽蝶々の女中、スズキの台詞〈知恵者オクナマは申しました。微笑みは悩みの横糸を解きほぐす〉(「オクサマ」の転訛か)
▽蝶々が新居で着物の袂から手拭、煙管、鏡や扇子とともに、なぜか伊達巻やお歯黒の瓶、仏像を取り出し〈オットケです〉と説明する。(日本風俗の混乱、「ホトケ」の転訛)
▽蝶々とピンカートンの婚姻の儀式の場面で、蝶々の伯父のボンゾー(坊主の訛り)がやってきて「昔からの信心を捨てた」と蝶々の改宗を怒り、〈カミサルンダシーコ!お前の腐った魂にはどんな責め苦が降りかかることか〉と罵る。(「神猿田彦」の訛りとみられ、神道の神のたたりを仏僧が唱える混同)
▽女中のスズキが仏前の祈りを捧げる。〈イザギ、イザナミ、サルンダシーコカミ……テンショーダイサマ! 蝶々さんを泣かせないで〉(伊弉諾尊、伊弉冉尊のことで日本神話の神と仏教儀式の混同。テンショーダイは天照大神のことと思われる)
▽残された蝶々が子どもを抱いて歌う。〈この母が雨の日も風の日も街に出て、お前を抱いて歌い踊り、道行く人に喜捨を乞うのを。ああ、恥ずかしい芸者の仕事をまたするなら、命を断ったほうがいいわ!〉(芸者と言う職業への誤解と偏見)
仏教と神道の混同、「芸者」という職業に対する偏見、日本の習俗(フォークロア)への誤った解釈など、プッチーニが原作を発表した時代の情報の偏り、それによって増幅される異文化への幻影と誤解がこの作品の細部に散りばめられているとみるべきであろう。
岡村はこれらのうちの数か所を訂正して2011年に上演し、なお11か所すべてを改めた「完全改定版」の上演を2013年の上演として企画したが、原作者プッチーニの著作権継承者で孫に当たるシモネッタ・プッチーニの強い反対によって遮られている。
原著と著作権継承者の不可侵の権利という、著作物に対する今日の常識的な法の制約が背景にあるにしても、いまなお持続している日本と西欧のあいだの「誤解」にもとづく異文化理解の根深いせめぎあいが、この作品の「訂正」をめぐる騒動には内在している。ともあれ、岡村の「完全改定版」の上演を認めないとした、プッチーニの孫のシモネッタ女史の言い分も聞いてみよう。
〈プトレマイオス的天動説がコペルニクス的地動説にとって代わられたからといって、ダンテ・アリギエリの『神曲』を修正しようとする人がいるだろうか。レンブラントの『ニコラス・テュルプ博士の解剖学講義』を医師は絵に描かれているようなふるまい方をしないという理由で正そうとするのだろうか〉
〈主張されている『蝶々夫人』の中の神道と仏教の混同も、岡村氏が指摘しているほど重大なものではないように思われる。神道や仏教的要素に関する不正確な点が結果的にあったとしても、ジャコモ・プッチーニが遺したテクストに手を加える理由として承服しがたい〉
シモネッタはプッチーニの原作の〈不可侵性〉を説くにあたり、西欧の知的正統性を踏まえたうえで新たな演出による「訂正」を否定しているが、グローバリゼーションの下でいまや世界中で演じ続けられるこの作品の今日的な評価を考えると、作品成立の時代背景を差し引いても、その「誤解の拡散」に対する抵抗感が日本人にはぬぐえない。今日でもなお、原作に描かれたような日本観が根強く世界に流通しているからである。
改めて振り返るまでもなく、20世紀初めに『蝶々夫人』の「誤解」が独り歩きをはじめる背景には、当時の西欧社会がまだよく知り得ていない「日本」という表象によせた、迸るような好奇心と憧れがあった。とりわけその眼差しは、エキゾチシズムの対象として日本の〈女性〉という像が結ぶ、可憐で健気で誇り高いふるまいと謎めいた東洋的エロスの幻影に結晶していったのである。
プッチーニのオペラ『蝶々夫人』の成立には、その由来に現実のモデルや史実に基づくいくつかの物語の原型が伝えられている。
プッチーニの原作のもとをたどると、物語の原型は米国の作家のジョン・ルーサー・ロングが1897年に「センチュリー・マガジン」に発表した同タイトルの短編小説にゆきつく。作者のロングは当時欧米に伝えられて世界の〈日本〉像に影響を与えたといわれるピエール・ロティの『お菊夫人』を踏まえた上で、実在のモデルによる伝聞を参考にして小説にしたといわれる。
ロティは明治期に来日したフランス人の海軍士官でもあった作家である。見聞した日本の風俗や生活の思い出を『秋の日本』などの作品に残している。『お菊夫人』もそうした異国情緒に導かれて日本の女性を描いた小説である。
〈お前の小さい身体も、お前の小さいお辞儀も、お前の小さい音楽もすべて私にあたえてくれた〉(野上豊一郎訳)
1885年に長崎を訪れておカネさんという遊女と過ごした思い出を、ロティは『お菊さん』でこのように描いたが、日本人については「何と醜く、卑しく、また何とグロテスクなことだろう」などと記して、遅れた文明と異文化への偏見や嫌悪も隠していない。
一方、実在のモデルとして今日伝えられているのは、現在長崎の観光名所となっている「グラバー園」に名を残している幕末の英国の武器商人、トーマス・ブレイク・グラバーの妻となるツルである。
もともとは料亭の仲居で、坂本龍馬らの倒幕運動に肩入れするなど、幕末の動乱期の黒幕でもあった英国人のグラバーに嫁いだ。ツルは着物に蝶々の縫い紋をいれていたことから周囲の人々に「蝶々さん」と呼ばれた。山手のグラバー邸に住むツルを知って、グラバーとの結婚のいきさつや改宗問題などについての話を聞いたのが、米国人の宣教師の夫とともに来日してすぐ近くに住んでいたロングの姉、サラ・ジェーン・コレルである。
コレル夫妻は1891年に来日して53年もの間にわたり日本での布教活動にあたったが、故郷のフィラデルフィアに帰国した折、姉のサラからこの「お蝶さん」の話を聞いた弟の作家、ロングが大きな関心を抱いた。
ツルには『蝶々夫人』のような悲劇的な人生があったわけではない。ただロティの『お菊さん』がフランス人のアンドレ・メサージュによってオペラ化され、すでに1894年にパリのオペラ・コミックで初演されてそのオリエンタリズムが評判をとっていたから、ロングがこれを下敷きにして日本から戻った姉の話をもとに脚色を加え、いわば二番煎じの「日本の悲恋」を売り出そうとして、三年後に『蝶々夫人』という小説にしたという経緯は容易に想像することができる。
ロングのこの通俗小説はヒットした。
すぐに米国で舞台化の話が持ち上がり、劇作家で演出家のデヴィッド・ベラスコが脚本化の権利を得た。1900年、人気女優のブランチ・ベイツをヒロインに迎えてニューヨークのヘラルド劇場で初演されたべラスコ演出の『蝶々夫人』は成功し、その後すぐにロンドンのヨーク劇場で行われた再演も連日満員となるなど、一躍ブームとなってゆく。
プッチーニが見た舞台の『蝶々夫人』はこのロンドン公演である。
英語は解さないが、この舞台の日本趣味の異国情緒はプッチーニを魅了した。終演後の楽屋へ飛び込んでベラスコを抱擁し、その場でオペラ化の申し入れをしたという。
〈こんな感情過多のイタリア人と実務的な取引をするなんてことは、とても不可能なことに思えたからである。何しろ、彼の目には涙があふれ、私の首は、彼の両手でしっかりと抱きしめられていたのだからね〉(モスコ・カーナ『プッチーニ』加納泰訳)
オペラ化の権利を得たプッチーニは、作品化にあたって「日本」と日本文化についてさまざまな情報を集めて、その宗教的な風土や社会風俗を生かす努力それなりにしている。
故郷のルッカに当時駐イタリア公使だった大山綱介が妻、久子を伴って夏の休暇を過ごしていたことから親しくなり、イタリア王妃に筝曲を教えていた久子を通して「君が代」や「さくらさくら」「お江戸日本橋」「越後獅子」などの日本の歌曲を知ったプッチーニは、オペラの『蝶々夫人』のなかにそれらを採り入れた。
当時日本から劇団とともに欧州各地を訪れて巡演し、1900年のパリ万博の公演で艶やかな着物姿が熱狂的ブームを呼んでいた女優の川上貞奴も、イタリアでプッチーニと会って女性の風俗や作法について教えたといわれる。
1904年2月、満を持してプッチーニのオペラ『蝶々夫人』はミラノ・スカラ座で初演された。しかしながら、この舞台は「既作の焼き直し」などと不評をかこった。幕開けに拍手も喝采もなく、聴衆は舞台を沈黙で迎えた。やがて嘲笑と野次が渦巻いた。不評の真相は定かではないが、この原曲には現在の台本以上に日本の文化や宗教、風俗に対する誤解や日本人に対する差別的な台詞・表現があった。このため指揮者のアルトゥーロ・トスカニーニの助言などを受けて削除や修正が行われ、これをもとに同年5月28日、プレッシャで行われた二度目の公演で、この東洋の悲恋物語はようやく成功を収めることになる。
初演におけるこの作品の屈折と、その後に日本のプリマドンナとして迎えられた三浦環に代表されるオペラ『蝶々夫人』の世界的な受容の歩みをたどると、ヒロインの日本の女性像をめぐる〈イメージの交換〉が、20世紀の日本と西欧という異文化間の理解と誤解に果たした役割の大きさを考えざるを得ない。その認識の落差こそが、西欧のジャポニスムという〈憧れ〉の一方で偏見や〈誤解〉の源になっていった、ということも含めて。
同じ時期の欧州を時代背景に、遠路やってきた日本女性の身体と精神を西洋人の眼差しで描いた日本人作家の作品がある。森鷗外の短編小説『花子』である。
〈Auguste Rodinは爲事場へ出て来た。廣い間一ぱいに朝日が差し込んでゐる。このHotel Bironといふのは、もと或る富豪の作つた、贅澤な建物であるが、つひ此間めで聖心派の尼寺になつてゐた〉
17歳の花子は日本からやってきた女優で、劇団とともに欧州各地を巡演している。パリでその評判を聞いた著名な彫刻家のオーギュスト・ロダンが、モデルに呼んでポーズをとらせたいというのである。留学生の久保田が通訳として、花子を斡旋する役割を引き受けてアトリエへ出向いてゆく。
〈健康で余り安逸を貪つたことの無い花子の、些かの脂肪をも貯へてゐない、薄い皮膚の底に、適度の労働によつて好く発育した、緊張力のある筋肉が、額と顎の詰まつた、短い頭、あらはに見えている頸、手袋をしない手と指に躍動してゐるのが、ロダンは気に入ったのである〉
花子は岐阜県からやってきた実在の旅回りの劇団の女優、太田久である。「欧州で芝居をしないか」という興行師の誘いで1902(明治35)年、さきにブームを起こした川上貞奴の後を追うようにして欧州の地を踏んだ。欧州各地の公演をプロデュースしたのは、貞奴のブームを仕掛けたのと同じ舞踏家のロイ・フラーである。
あでやかな着物に舞扇を手に持ち、なぜか最後に必ず演じられる「ハラキリ」の場面が各地で「花子」の人気を異常に高めた。『蝶々夫人』の結末と同じように、日本刀によるヒロインの自刃でエロティシズムとエキゾチシズムがひときわ高められるのが、この時代の欧州における日本女優ブームの一面であったことは、改めて記憶されるべきであろう。
鷗外の小説のなかで、「花子」はモデルとして裸体でポーズをとることを承諾し、ロダンは数十分のデッサンを終えてから通訳の久保田に向かって言う。
〈人の體も形が形として面白いのではありません。霊の鏡です。形の上に透き徹つて見える内の焔が面白いのです〉
高名なフランス人彫刻家が、突然現れた「花子」の裸体から「地中海の女性とも、北欧の女性とも違う、地に根を深く下した木のような〈強さの美〉」を受け止めた、という言葉でこの小説は終わっている。
ロダンが「花子」を初めて見たのは1906年のマルセイユ植民地博覧会における公演の折で、申し入れを承諾した花子をパリの自宅に招いて画室でポーズをとらせた。以来、巨匠ははるばる日本からやってきた、この飾り気のない小柄な女優を寵愛した。
国立西洋美術館に所蔵されている「花子像」など、花子をモデルにした50点以上に上るロダンの作品が伝えるのは、素朴で活力に満ちた日本女性の身体と精神の「強さ」である。ロダンはそこに西洋女性にはない、〈死〉とも通い合う日本女性のなかの固有の〈美〉を見出したというべきだろう。
花子は欧州から米国へと巡演しながらブームを広げた。鷗外が『花子』を発表するのは1910年だから、これは欧州留学から帰った後の鷗外が花子とロダンの挿話に想を得た創作である。やがて帰国して故郷岐阜の妓楼に戻った「花子」、すなわち太田久はロダンから贈られた自身がモデルの「花子像」を終生、大切にしたといわれる。
〈誰もかれもが、彼女の演技の、いかにも扇情的で安っぽいうわべの底にひそむ、なにか名状しがたい、魔法のような要素、彼女の身裡から輝き出る、焔のようなものを感じたらしいのだ〉
ドナルド・キーンは欧米を駆け抜けた「花子」のブームについて、こう記した。
19世紀末、西洋の目によって発見された〈日本〉は繊細な花鳥の意匠や優美な曲線模様などによって、欧米社会にジャポニスムの花を咲かせた。舞台で演じられる「女性」を通したエロティシズムは、そのもっとも誘惑的でミステリアスな表象というべきだろう。
『蝶々夫人』と「花子」という、この時代の現実の日本女性がモデルとなって欧米にブームを広げたジャポニスムの遺産は、多くの幻影と誤解を増幅しながら、21世紀のいまにも生きている。
この項おわり
(参考・引用文献等は連載完結時に記載します)