書斎の漂着本 (35) 蚤野久蔵 饒舌録①
東京の大手出版社だった改造社から、昭和4年(1929)に発刊された谷崎潤一郎の随筆集『饒舌録』は、四六判303ページの初版ながらカバーが失われたいわゆる「裸本」である。裏表紙に黒インクのF・Hyodo(兵頭)というサインの余白に、ほとんど消ゴムで消されてはいるが、鉛筆で書いた子供の落書きがあり、三重丸や四角に混じって「おかっぱ頭の少女」らしいのもある。奥付の「検印紙」がはがされているのは兵頭家の子供たちが切手集めに熱中するあまり<切手そっくり>の検印紙まで失敬したのだろうか。もっとも世間には「検印紙コレクター」という変わった趣味まであるが、こちらは水を浸した布か紙を上から当てて無理にはがした跡が歴然で、いかにも「子供のしわざ」に思える。濃い臙脂色が「谷崎らしい」と感じた裏表紙も取れかかっているから、ここまできたら「破損本」のたぐいだ。それでも200円の値付けなのは、やはり文豪・谷崎の名前ゆえだろうか。
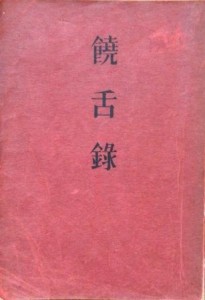 |
 |
「そんなのをよく買いますねえ」と言われる前に言い訳めくが購入した動機を紹介したい。気ままな文芸随筆の『饒舌録』も面白そうだったが、次に『「九月一日」前後のこと』があるのが目についた。まさしく大正12年に首都圏を襲った関東大震災が発生した日付である。幼少時から「地震嫌い」だった谷崎は、横浜の自宅が地震直後に発生した火事で延焼したことが関西移住を決心するきっかけになった。「その時、谷崎はどこで何をしていたのか」をはじめ、綴られた生々しい被災体験にも興味がわいた。
東京・日本橋で生まれた谷崎は、9歳だった明治27年(1894)6月20日に明治東京地震と呼ばれる大規模な直下型地震を体験した。M 8.0と推定される24年10月の濃尾地震からわずか2年8ヵ月後の発生でM 7.0だった。これを大正5年の『中央公論』に、幼少時の地震体験から生まれる恐怖のイメージをテーマにした短編小説『病蓐の幻想』で書いた。病蓐(じょく)とは病床の意味である。『改造』に発表した『「九月一日」前後のこと』もその体験から始まる。
ちょうど彼が小学校の二年の折であったろう。午後の二時時分、学校から帰って、台所で氷水を飲んでいると、いきなり大地が凄まじく揺れ始めた。「大地震だ!」と、彼は咄嗟に心付いたが、何処をどう潜り抜けたのか、一目散に戸外へ駆け出して、大道の四つ角の真ん中につくばっていた。その頃彼の家では日本橋の蛎殻町に軒を並べた商店の土間に溢れるほど雑踏していた相場師の群衆は、誰も彼も金の取引に気を奪われて、日盛りの苦熱を忘れていたが、突然、ぐわらぐわらぐわらと家鳴動し出すや否や、右往左往にあわてふためき、殆ど路次(路地)のような、窮屈なせせこましい、往来のぎっしり詰まった家並みの下を揉みに揉んで逃げ惑うた。
彼の経験によると大地震というものは地が震えるのではなく、大洋の波のように緩慢に大規模に、揺り上げ揺り下ろすのであった。自分の足を着けている地の表面が、汽船の底と全く同一な上下運動をやり出した時を想像すれば、恐らく読者はその気味悪さの幾分かを、了解することが出来るであろう・・・いや、汽船の底と言ったのはまだ形容が足りないかもしれない。むしろ軽気球のように――踏んでも蹴ってもびくともしない、世の中のすべての物よりも頑丈な分厚な地面が、むしろ軽気球のように、さも軽そうにふらふらと浮動するのである。
そうして、その上に載つかっている繁華な街路、碁盤に目の如く人家の櫛比(=密集)した、四通八達の大通りや新道や路次や横丁が、中に住んでいる人間諸共に、忽ち高高と上空へ吊り上げられ、やがて悠悠と低く降り始める。彼は比較的見通しの利く四つ辻に居たために、此の奇妙なる現象を真にまざまざと目撃した。
ああその時のこわさ恐ろしさ!人間が、測り知られぬ過去の時代から生存の土台と頼み、光栄ある歴史をその上に築き、多望なる未来をその上に繋いで、安心して活動していた大地というものが、斯く迄も不安定に、斯く迄も脆弱であろうとは・・・
この作品は『中央公論』に発表した短編だったから、その10年後に書かれた『「九月一日」前後のこと』では「彼」は「私」として語られる。
私は今日、この文章を読み返して見るのに、あの時の大地が「大洋の波の如く緩慢に大規模に、揺り上げ揺り下ろした」というのは、どうも本当とは信じられない。しかしながら、子供の頭に非常に恐ろしいと感じたことは、案外正確な記憶を留めるものであるから、当時の私は、事実そういう印象を受けたのであろう。思うに四つ角へ逃げ出した時には、既に最初の激動が終わって、ゆるい余震が続いていたに違いなく、それが怯え切った少年の眼に怪しい錯覚を与えたかも知れない。
私は確か前記の四つ角へ母と一緒に逃げたのだった。地震の際に母と一緒に逃げた記憶は此れのみではない。その数年前、明治二十四年の濃尾の大地震の時は、東京もかなり強く感じたが、その頃の私は茅場町に住んでいた。揺れが来たのは早朝のことで、母と私は「スワ」というや家を飛び出し、裏茅場町の通りを霊岸島の方へ跣(裸)足で走った。今はっきりと覚えているのは此れだけだけれども、そんなことは幾たびもあった。「お前が騒ぐものだから、子供達が臆病になる」と、父はそういって母をよく叱った。
『「九月一日」前後のこと』には、東京住まいだった谷崎が千代夫人と結婚後、夫人の実家に近い向島に住んだが、江戸時代の安政2年(1855)の大地震ですぐ近くの本所浅草深川がもっとも被害が多かったのを知って、小石川原町へ転居して『病蓐の幻想』を書いた。それで余計に地震の怖さを思い出し、5か月後には同じ町内にあった「建築学のN工学博士」の家作を人から勧められて移った。ここで地震嫌いの母親没、その後は鵠沼、東京・本郷曙町の借家で暮らしたが妻子が流感で気管支を痛め転地療法をすることになって小田原へ。大正10年には映画の仕事の都合(大正活映での脚本家)で横浜・本牧へ転居。ところが海岸沿いの埋立地だったこともあり何度かの地震の後、大正11年4月の地震で大きく揺れた。谷崎は山下町の中国料理店の外壁が崩れて下敷きになった娘が死亡したと聞き、わざわざ<見物>に行って地震がますます怖くなり、10月に山手の平屋の洋館に転居した。もっとも直接のきっかけは9月の台風で海岸沿いの自宅まで波が打ち上がったためだったが、それにしても目まぐるしいほどの転居ぶりですねえ。
しかし何事も、十から十まで好都合には行かないもので、地震に対して安全な平屋は、私のような静かな書斎を必要とする者にとっては、仕事の上に支障が起こりがちだった。やっぱり二階か離れのような座敷でないと、家族や来客の話声が耳につく。その家の書斎は寝室と浴室に挟まれていて、間に廊下があるのでもなく、風呂に入るには書斎を通って行く始末だから、私は結局、書き物が忙しくなり出すと、原稿を抱えて何処かのホテルへ逃げ込まなければならなかった。(私は西洋流に椅子に着かないと書けないのであった)それでその後一箇年ばかりの間は、花月園ホテル、フジヤ・ホテル、海濱ホテル、熱海ホテル、はふやホテル、小涌谷ホテル、オリエンタル・ホテル、メゾネット・ホテルと京浜間から鎌倉箱根あたりへかけての、ホテルというホテルを廻り尽くした。
さて、いよいよ8月である。谷崎夫妻は長女と3人で箱根の小涌谷ホテルで過ごした。温泉だけでなくプールで泳いだり大涌谷を見物したりしたが長女の学校が始まるので27日に横浜へ帰宅。28日は聘珍楼(へいちんろう)で中華料理、29日は東京・芝の改造社へ『愛すればこそ』の印税を取りに行く。
八月三十日の夕刻、私と妻とは高砂町の玉屋で晩飯を済ませ、私はその足で横浜駅から小田原行きの汽車に乗った。妻は散歩がてら、プラットホームまで見送りに来た。
八月三十一日の午後、小涌谷ホテルの滞在ももう一箇月程になり、多少鼻について来たので、仕事をするには場所を変えた方がいいかと思い、この夏芦ノ湖畔に新築された箱根ホテルへ、一日二日試験的に泊ってみようという気を起した。私は折鞄に原稿用紙、備忘録、旅行用の小瓶に詰めたウイスキー、バイエル・アスピリン、下剤、睡眠剤等を入れて、晩餐の時間前に小涌谷を立ち、乗合自動車で湖畔へ向かった。
箱根ホテルはフジヤの経営で、支配人は顔馴染である元の「はふや」の主人であった。外観はコンクリート五層楼であったから、内部はすべて西洋間であろうと予期していたのだが、行ってみると、西洋間は一階にしかなく、それもその晩は満員で、已むを得ず三階の日本間で辛抱しなければならなかった。私はその座敷へ通った時、そういう大きな建物の中へ入った場合の常として、直ぐに「地震」ということが念頭に湧いた。火急の際にこの三階から梯子段を降りて表へ飛び出す暇はないが、しかし湖水に面した方に、相当に広い露台(テラス)がある。その土台は鉄筋コンクリートであろうから、そいつが崩れ落ちる筈はあるまい。よし、若しもの時はあの露台に逃げよう。――私はそんなことを考えながら、日本までは仕事は駄目と諦めて、いつもより早く床に就いた。夜に入ってからは大変な豪雨で、そのために却って地震の方は大丈夫と思ったけれども(大森博士は大風大雨中に大地震はないと言って居られた)土砂降りの音が耳について寝られず、カルモチンを飲んで漸く眠った。
大森博士は「日本地震学会の父」と評される大森房吉(1896-1923)のことで、谷崎とは同じ日本橋区阪本小学校の先輩にあたる。東京帝国大学物理学科を卒業し、大学院で気象学と地理学を専攻、イギリスから招かれた地震学者のジョン・ミルンの指導を受け、濃尾地震の余震の研究を行った。谷崎は博士に会ったこともあり以前は先輩として尊敬していたが大きな地震のたびに新聞に発表される「心配には及ばない」という談話には不信を募らせていた。「大風大雨中は云々」というのもあくまで単なる俗説だったが、そう信じたかっただけであろうか。カルモチンは谷崎が日ごろから持ち歩いていた睡眠薬である。
(以下、この稿続く)




