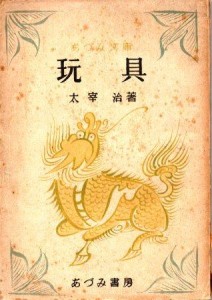書斎の漂着本 (59) 蚤野久蔵 玩具
父の蔵書だった太宰治の自選短編集『玩具』は、終戦1年後の昭和21年8月に東京目白のあづみ書房から発行されている。配給元は終戦後もしぶとく生き永らえていた旧国策会社の日本出版配給統制株式会社である。終戦直後の急激なインフレを示すように奥付の一枚だけは刷り直されているが、表紙は「定価7円」の上から「定価9円」と切り貼りで済まされている。物資不足の中で紙だけでなく、印刷インクの不足は深刻な事態だったからこうした<苦肉の策>も仕方がなかったのだろう。
平成4年に亡くなった父の遺言は「蔵書はすべて本好きな長男の私に任せる」というものだった。母からは「あなたに自分の本を役立てて欲しいということよ!」と言われたものの読書傾向も違うし、私のほうも書斎に入りきれないほど本があったので途方に暮れた。どうしたものかと悩んでいたら、たまたま勤務先の会社の組合が海外の工場や営業拠点に本を贈る運動をすることになった。「現地駐在の方やそのご家族に読んでもらえることで本が活用できそうだ」と思い、母にも了解を取って芥川賞や直木賞の受賞作などを中心に寄付することにした。それでも段ボールにして数十個はあったから「あなたが断トツでした」と言われた記憶がある。
この『玩具』は紙質も悪く、全体が黄ばんだうえに背などもかなり痛んでいたから最初から除外したが、文学全集以外では唯一の太宰作品だった。表題の『玩具』に続き『魚眼記』、『地球圖』、『猿ヶ島』、『めくら草紙』、『皮膚と心』、『きりぎりす』、『畜犬談』の8作が収められている。「あとがき」には「『玩具』から『めくら草紙』に到る五編は、いまから十年前の昭和11年に、砂子屋書房から出版した私の第一創作集『晩年』から選び出した作品でサンボリズム(象徴主義)のにおいが強いようで、巻頭の『玩具』などは散文詩とでもいうべきもののように思われる。『めくら草紙』は、書いている時には実に悲しい気持ちであったが、いま読むとユウモラスな箇所が少なくない。悲痛も度を越すと、滑稽な姿にアウへーベン(止揚)するものらしい。『皮膚と心』は昭和14年に書いた。私は男のくせに、顔の吹出物をひどく気にするたちだったので、こんな作品を思いついた」とある。
太宰は芥川賞への落選や東京新聞の前身である都新聞の入社試験に落ちて自殺未遂を繰り返し、睡眠薬中毒だった昭和10年代前半の自暴自棄生活からようやく抜け出し、井伏鱒二の媒酌で、甲府出身の地震学者・石原初太郎の娘の美知子との結婚生活を送った。甲府市に新居を建てたものの1年足らずで三鷹・下連雀に転居したが2児にも恵まれ『走れメロス』や『津軽』など優れた短編を発表するなど完全に立ち直ったと思われた時期だった。戦時中は甲府に疎開したものの空襲で焼け出され、妻子を連れて津軽の実家にようやくたどり着くがここに落ち着くつもりはなかった。あづみ書房からの出版は家族を東京に呼び戻すための費用捻出のためもあったはずで、同じ年には銀座のBAR「ルパン」で織田作之助と飲んでいるところを写真家の林忠彦に撮られている。芥川龍之介ファンだった太宰の写真といえばいつも芥川をまねて顎に手を置いたポーズだったのが珍しく右足を椅子に立て、大声で何かをしゃべっているあの写真で林の代表作となった。

父の蔵書の中でこの『玩具』は文学全集以外では唯一の太宰作品だったと書いたが、父は好きになった作家をとことん読む性向で本棚は作家ごとに分類されていたから間違いない。その後の太宰作品で代表作になった『斜陽』や『人間失格』はいくつかの文学全集に収録されているからわざわざ購入しなかったのかもしれないが、ではどうして『玩具』だけがあったのか。この年の話題本だったかといえばそれはなさそうだから私なりの<仮説>を立てるとしたら父の「戦後」に大いに関係がありそうだと思いついた。
大正7年に山形県酒田市に生まれた父は、子供のなかった大阪・天王寺区の親戚の米穀商夫婦に引き取られて天王寺中学を卒業すると陸軍士官学校に進んだ。配属は旧満州の野砲連隊で、帰省に合わせて広島の農家の末娘だった私の母とあわただしく結婚式を挙げるとふたたび満州へ舞い戻った。その後は南洋に転戦、飢餓の島となった南太平洋のエンダービー島を経てトラック諸島の夏島で中尉として終戦を迎えた。戦闘の機会はほとんどなかったものの栄養失調などで多くの戦友を失いながらようやく横須賀に引き揚げたのは昭和20年12月だった。
大阪空襲で育った天王寺や上本町一帯は焼け野原になり、養母だけはかろうじて広島の妻の実家にいることがわかったのでそちらに向かった。そこに待っていたのは辛すぎる現実だった。「病気で療養中」ということになっていた新妻は、実際には広島市内へ家屋疎開に行っていて被爆、顔や手に大やけどを負って包帯でぐるぐる巻きになっていたのである。妻の両親からは何度も離婚を懇願されたようだが「戦地で負傷するなど逆の立場だったら妻に介護してもらうことになったはず」と断って連日の治療に付き添った。
たまたまではあるが野砲連隊で中隊長を任された部隊の構成は青森、秋田、岩手、山形4県の出身者で占められ、太宰の故郷・金木村から出征した兵もいたかもしれない。しかし戦友会が弘前で開催された際も、郊外にある太宰の生家を見学したとか、太宰のファンだったとは聞いていない。父がこの『玩具』の出版を知ったのは広島市内の書店の店頭がはじめてだったろうが、表題の『玩具』ではなく『皮膚と心』が目次にあったから購入する気になったのではなかったか。妻の皮膚はやけど特有のケロイドが盛り上がり、何度手術を重ねても結果は思わしくなかったから「皮膚」の二文字が頭にこびりついていた。だからこそ読んでみようと思った、そう想像するのである。『皮膚と心』はこう書き出される。
ぷつッと、ひとつ小豆粒に似た吹出物が、左の乳房の下に見つかり、よく見ると、その吹出物のまわりにも、ばらばら小さい赤い吹出物が霧を吹きかけられたように一面に散点していて、けれどもそのときは、痒くもなんともありませんでした。
登場人物は腕の立つ図案工だが35歳の再婚の男と結婚した25歳の妻。新婚間もなくのある日、妻は夫に吹出物ができたことを告げる。
「わからねえなあ。ジンマシンなら、痒い筈だが。まさか、ハシカじゃなかろう」
私は、あわれに笑いました。着物を着直しながら、
「糠にかぶれたのじゃじゃないかしら。私、銭湯に行くたんびに、胸や頸を、とてもきつく、きゅつきゅつと糠でこすって、きっとこすり過ぎたのでございましょう。こんなに吹出物してしまって、くやしく、うらめしく思います。私はいったい、どんな悪いことをしたというのでしょう。神様だって、あんまりだ」
症状は急速にひどくなる。それと同時に妻は心理的にも追い詰められていく。
翌朝、薄明のうちにもう起きて、そっと鏡台に向かって、ああと、うめいてしまいました。私はお化けでございます。これは私の姿じゃない。からだじゅう、トマトがつぶれたみたいで頸にも胸にも、おなかにも、ぶつぶつ醜悪を極めて豆粒ほども大きい吹出物が、まるで全身に角が生えたように、きのこが生えたように、すきまなく、一面に噴き出て、ふふふと笑いたくなりました。そろそろ、両脚のほうまでひろがっているのでございます。鬼。悪魔。私は、人ではございませぬ。このまま死なせて下さい。泣いては、いけない。
こんな醜悪なからだになって、めそめそ泣きべそ掻いたって、ちっとも可愛くないばかりか、いよいよ熟柿がぐしゃりと潰れたみたいに滑稽で、あさましく、手もつけられぬ悲惨な光景になってしまう。泣いては、いけない。かくしてしまおう。あの人は、まだ知らない。見せたくもない。こんな腐った肌になってしまって、もうもう私は、取り柄がない。屑だ。はきだめだ。もう、こうなっては、あの人だって、私を慰める言葉がないでしょう。慰められるなんていやだ。こんなからだを、まだいたわるならば、私はあの人を軽蔑してあげる。いやだ。私は、このままおわかれしたい。いたわっちゃいけない。私を見ちゃいけない。私の傍にいてもいけない。結婚しなければ、よかった。あの時、死んでいたら、いまこんな苦しい、みっともない、ぶざまの憂き目を見なくてすんだのだ。
医者に裸を見せるのが恥ずかしいとか、電車に乗って吊革を持つことで他の乗客から病気がうつるのではと思われるのがいやだ、などのやりとりがあったものの、結局、自動車を雇って二人で病院へ行く。入口に近いベンチの端に腰をおろしたものの大勢の患者の中でいちばん重い皮膚病なのかもしれないと死んだようにうなだれ、目をつぶる。長い時間、待たされた挙句にようやく順番が来る。
看護婦に招かれて、診察室に入り、帯をほどいてひと思いに肌ぬぎになり、ちらと自分の乳房を見て、私は石榴(ざくろ=腫れた患部)を見ちゃった。目の前に坐っているお医者よりも、うしろに立っている看護婦さんに見られるのが、幾そう倍も辛うございました。お医者は、やっぱり人の感じがしないものだと思いました。あちこちひねくって
「中毒ですよ。何か、わるいもの食べたのでしょう」平気な声で、そう言いました。
「なおりましょうか」あの人が、たずねてくれて、
「なおります」私は、ぼんやり、ちがう部屋にいるような気持ちで聞いたのでございます。
「ひとりで、めそめそ泣いていやがるので、見ちゃ居れねえのです」
「すぐ、なおりますよ。注射しましょう」お医者は立ち上がりました。
「単純なものですか?」とあの人。
「そうですとも」
注射してもらって、私たちは病院を出ました。
「もう手のほうは、なおっちゃった」
私は、なんども陽の光に両手をかざして、眺めました。
「うれしいか?」
そう言われて私は恥ずかしく思いました。
物語はこれで唐突に終わるが、私の父母の闘病や苦しみは、それからもまだまだ続いた。父は太宰のことも、この『玩具』のことも一切書き残さなかったから、その時にどう読んだのだろうかということはあくまで私なりの勝手な<仮説>である。