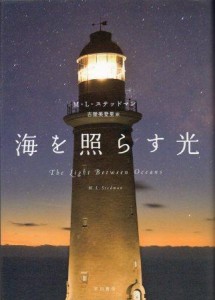新・気まぐれ読書日記 (28) 石山文也 海を照らす光
何年振りだろう、読後に「まいったな!」とつぶやいたのは。『海を照らす光』(M.L.ステッドマン、古屋美登里訳、早川書房)を閉じたときに遥か南半球の孤島に立つ灯台の光を思い浮かべた。
舞台は第一次世界大戦が終わったばかりのオーストラリア。連合国軍の大尉として多くの犠牲者を出した西部戦線に従軍し、その功績により武功十字勲章を受けて名誉除隊となったトムはヤヌス・ロックという無人島の灯台守としての職を得た。そこはオーストラリア大陸の南西端、フランス人探検家にちなんで命名されたパルタジョウズ岬の南西沖にあり、本土からは160キロも離れたまさに絶海の孤島だった。断崖がある島の西側はアフリカ大陸まで続く広大な海、押し寄せるインド洋がここでオーストラリア南洋とぶつかる海の難所でもある。灯台は付近を航行する船に危険を知らせるため5秒おきに周囲50キロに光を放つ。「布の端にぶら下がっている取れかけのボタンのように、南極大陸にあっさりと落ちていきそうなところ」と表現されるように南は南極まで海が広がる。年4回、物資を運んでくる定期船が外界との唯一の連絡手段だった。
トムは東海岸やタスマニアの灯台で半年間にわたり臨時要員として灯台守としての生活を体験したあと定期船が出る港町パルタジョウズにやってきた。同名の岬の付け根にある小さな町だ。ヤヌス・ロックの新任灯台守は港にかかわる全業務を管理する港長(=こうちょう)の食事会に招かれるという慣例があった。ここで小学校の校長の娘イザベルに会う。昼間、港の桟橋で鷗に餌のパンをやっているのを見つけ、短い会話のあとどちらに多くの鷗が寄ってくるかを競争したが名前も聞かずに別れた娘は食事会で<初対面>を貫いた。
ところが3カ月後にやってきた定期船の船長が娘から託された手紙を持ってきた。そこには「拝啓、あなたが海に吹き飛ばされたり押し流されていないことを確かめたいと思っただけなのです。それとあまりに寂しい思いをしていないといいのですが。 イザベル」とあった。さらに、「ヤヌスでの任務が終わって別の任地へ出発する前にちょっと立ち寄ってお顔を見せて下さいね。そのときまで、鯨に食べられないよう充分に注意すること」ということばと灯台に寄りかかっている灯台守が口笛を吹いているその後ろの海に巨大な鯨が大きく口を開けて襲いかかろうとしている絵が描かれていた。ばかばかしくて愉快な絵には、返事の言葉よりも微笑みだけを伝えたかったがトムは「幸いなことに吹き飛ばされたり押し流されたりはしていません。たくさんの鯨を見ましたが、これまでのところ、私を食べようとした鯨は一頭もいません。きっと不味いからでしょう」と書き、「あなたこそそちらの鷗を(パンの餌で)太らせていることでしょう。次の任地はどこか分かりませんがお会いするのを楽しみにしています」と付け加え、船長にポストに投函してもらえるよう頼んだ。宛先を見た船長は「ちゃんと相手に届けるさ。そこを通るついでにな」とウインクした。
こうして3カ月おきに定期船が運ぶ「文通」が「恋」に発展し、やがて結婚へ。二人だけの新婚生活はトムが継続して灯台守を任されることになったヤヌス・ロックで営まれる。幸せな日々、イザベルは島を隅々まで<探検>し、入江や崖、岩、草地にことごとく名前をつけた。「楽園の池」「嵐の角」「不実の岩」「難破の浜」「のどかの湾」「トムの見張り台」「イジー(イザベルの愛称)の崖」などなど。彩色したスケッチに地名を書き込んだ地図を作った。
島の名前についてトムはイザベルに
「ヤヌスという神から1月(January)の名が取られたって知ってる?この島も1月も同じ神から名を取ったんだ。その神にはふたつの顔がある。背中と前に。ひどく醜いやつだ」
「なんの神?」
「門の守護神。いつもふたつのものを見ている。その間で引き裂かれている。1月は新しい年を前に、古い年を後ろに見ている。過去と未来を見ているんだ。この島もふたつの方向を向いている。南極と赤道とをね」
やがてイザベルは妊娠し、トムは定期船で取り寄せた育児書を贈る。イザベルは時間があるときはいつもこの本を読み、知り得た情報を矢継ぎ早にトムに伝える。夫婦の間ではこどもの名前をどうするかが楽しい話題になる。イザベルは次の定期船で両親に吉報を伝えようと楽しみにその到着を待っていた。
ところがある嵐の晩、トムが徹夜で灯台の保守にあたっている間に流産してしまう。二人目も、三人目も。そのたびに崖の手前にトムが流木で作った小さな十字架が立てられ、ハーブ園から持ってきたローズマリーの木が移植された。三人目を埋葬した数日後、やってきた定期船にもう一人、鞄を下げた人物が乗っていた。イザベルはてっきりあれほど嫌がった医師がやってきたのかと勘違いして「裏切り」と名付けた洞窟近くの草地で怒りに身を震わせていたが、それはトムが手配したピアノの調律師だった。イザベルが島に持ってきたピアノはフェルトがすりきれたのか音が出なかった。修理道具を入れたカバンが診療鞄に見えたことで起きた勘違いだった。その夜、光源のマントルを点検するトムの耳にはイザベルが演奏するバッハの曲が届いた。トムは日誌の1922年9月13日水曜日の「備考」欄に「定期便により調律師が来島。事前承認を得て」と書いた。
そして1926年4月27日早朝、奇跡が起きる。イザベルが流木で作った墓の手入れをしているとどこからか赤ん坊の泣き声が聞こえてきた。幻聴かと思ったイザベルは温んだ海の中で出産をするために沿岸へと向かう鯨の群れに目をやるが、また泣き声がする。連絡を受けたトムが入り江に漂着したボートを見つけ、近くに寄ってみると座席には身動きしない若い男。舳先の隙間には女物の柔らかなラベンダー色のカーディガンに包まれて泣き続ける女の赤ん坊がいた。男は既に死んでいたが母親の姿はどこにもない。トムはすぐに無線で本土へ連絡しようとするが、イザベルの強い反対で日誌にも書かずじまいになる。
ルーシーと名付けられた赤ん坊はすくすくと育ち、クリスマス休暇を利用してイザベルの両親や縁者たちと洗礼式を迎える。久しぶりに戻った町で夫婦は驚愕の情報を耳にする。資産家の長女が親の反対を押し切って敵国だったドイツ人と結婚し、娘を産んだが祭の日に町のチンピラたちから夫がリンチを受け、連れていた娘とからくも港のボートに逃れ漕ぎ出したまま行方不明になるという事件が起きていた。娘はひたすら彼らの生存を信じ、毎日のように自宅から警察署を訪ねて往復する生活を送っているが今では誰も相手にしなくなっている。一代で財を成した親は有力な情報をくれた人物にこのあたりでは牧場3つ分にもなる3千ギニーもの懸賞金を払うことにしたがまだ何の知らせもないというのだ。
もちろんこれがルーシーと名付けられ、トムとイザベルの「実子」として成長した赤ん坊である。悩むトムとすべてを忘れることを主張するイザベルの葛藤が続く。さらに2年後、懸賞金に目がくらんだ若者によって「真実」は警察の知るところとなる。ここでは462ページもある長編のほんの入り口だけしか紹介しないが、トムの戦場体験だけでなく、癌で死の床にあった父が戦場に出した手紙があちこち転送されて届き、そこにあった住所から訪ねて知った母親の最後が明らかにされる。毒ガスにやられたり手足を失ったりしても帰還した若者が多くいる町は戦争の傷跡が癒えないままだった。戦場ではトムのすぐそばにいた多くの<真の英雄たち>、彼らはは誰一人として故郷へ帰ることはなかったし、イザベルも優しかった兄二人を戦争で失っていた。
作品の中で繰り返し描かれるのはたくさんの「ふたつのもの」である。善と悪、正と邪、光と闇、感情と理性、生と死、罪と赦し、生みの親と育ての親、後半には警察幹部や弁護士などが登場して実母のほうの「別の人生」が語られる。まさに「禍福はあざなえる縄の如し」ではあるまいか。その間で人々は揺れ動き<正しい選択>をしようと迷い苦しむ。構成も巧みだが登場人物それぞれの心の奥底までもが見事に活写される。まさに灯台のある島の名のヤヌス神がふたつの側面をもつように。
冒頭で書いた「まいったな」のつぶやきにはもうひとつ理由がある。著者のステッドマンはオーストラリアに生まれ育ち、現在はイギリスで活躍する女性法律家である。「マンなのに」は冗談だが、これが作家としてのデビュー作だという。出版されると英語圏でベストセラーになりニューヨーク・タイムズをはじめとする多くの新聞雑誌が書評に取り上げた。スピルバーグらが創立したドリームワークスが映画化権を獲得しているそうだ。理想的な撮影場所となる灯台を探すのに時間がかかったがようやく映画の撮影がスタートしたとのこと。えっ、ヤヌス・ロックは?著者ステッドマンの頭の中だけにある架空の島なのである。
ではまた