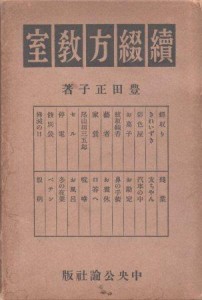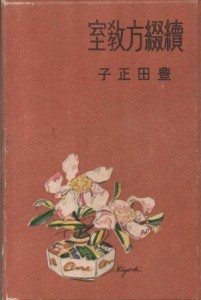書斎の漂着本(73)蚤野久蔵 續綴方教室
綴方とはいまの作文のことである。<天才綴方少女>といわれた豊田正子の『續綴方教室』(中央公論社)は、昭和14年(1939)1月に出版されている。「續」だから当然、「正」にあたる『綴方教室』があって、2年前の同12年に出版されるやいなや話題を呼び、「續」の巻末広告には「綴方教室・改訂七十一版出来」として川端康成が朝日新聞の文芸時評に書いた「成功した早教育」をそのまま引用掲載している。
豊田は大正11年(1922)東京下町の貧しい職人の娘として生まれた。小学校の担任の指導で書いた「うさぎ」が鈴木三重吉主宰の児童雑誌『赤い鳥』に初入選し、以後七編が入選して注目される。卒業後はセルロイド人形の彩色工場などで働きながら、日常のできごとを書き続けた。『綴方教室』が話題を集めたことから出版の翌年には築地小劇場で初演され、正子役は山本安英、東宝映画では高峰秀子が熱演した。『續綴方教室』は豊田の14歳から17歳までの作品24編を収めている。
川端は「早い教育によって文学的なものを子供に加えるのではなく、子供の殻みたいなものを洗い洗っているうちに、こういう綴方の言葉が流れ出て来たのである。本を読むことから入った文学ではない」と書いている。川端が激賞した『尾山田三五郎』は豊田の文章を交えて紹介するとこんな話である。
近所に住む奥戸さんの奥さんの友達だという尾山田さんが家の二畳を借りたいとやってきた。母ちゃんは「うちもわずか六畳と二畳で、親子七人がいるのだから、とても貸せない」と断った。尾山田さんは仕方なく奥戸さんのところから毎日、自動車の工場かどこかへ勤めているようだったが、ブクブクと水ぶくれみたいに肥っていて、丸顔の、目の細い、唇のうすい、髪の毛がちりちりにちぢれた、何となく嫌らしい人だった。(中略)尾山田さんは二十三四のくせに、安田の小父さんに目下のような口のきき方をしていた。その時、父ちゃんの友達の矢島さんが来ていて、尾山田さんに、「あんた、今、どこへ行ってるんですか」と言うと、尾山田さんは「はあ、あの、工場へ行ってるんです」と、頭をぺこぺこさせながら、左手でちぢれっ毛をかき上げた。すると安田さんが、「なんだかずい分休んでるようだね」と言った。「からだが疲れているんで」と言って、尾山田さんは口を結んだままちょっと笑った。
父ちゃん、母ちゃんをはじめとする大人たちのやりとりを聞いた少女はそれをていねいに書いていく。やがて尾山田さんは田舎の実家から送ってきたという五枚組の布団やズボン、洋服などまで売りにくるようになる。父ちゃんが尾山田さんのことを気に入らないと言うので母ちゃんは何も買わなかったが、気の毒に思った奥戸さんの奥さんは何人も友達を紹介してやったらしい。
ある晩、会社から帰ると弟の光男が「ねえちゃん、尾山田って人知ってんだろ。今日ね、お巡りさんが、リヤカーに積んで家にあった机なんか持ってっちゃったよ」と言ったので、「え、なァに、尾山田さんがどうしたの」と聞くと、母ちゃんがお勝手から「正子。あの尾山田って人、泥坊(泥棒)だってよ」と言った。
質屋に盗みに入ったのを見つかり捕まったのだ。さらに亀有警察署から奥戸家へ呼び出し状が届く。
母ちゃんと小母さんの二人で来いというのだそうだ。小母さんの唇は色が変わってわくわくふるえていた。母ちゃんは割合に落着いて、「まあ、しょうがねえな、いくしかあるめえよ」と言った。奥戸の小母さんは、「あたしらいって、まさか、ぶち込まれるんじゃないだろうね」と心配そうに母ちゃんの顔を見つめる・・・
警察に行くと真っ赤に顔をはらした尾山田が座っていて顔もろくに上げない。盗んだものを全部言わなければひっぱたかれるからだったが、盗んだものが六畳くらいの所へ山のようにあって被害者が入れ替わり立ち替わりやって来る。新聞には「雨の中の大格闘。澁江小学校裏、深さ三尺の池中にとび込み、折から降る雨に水中の格闘をつづけ、刑事は尾山田三五郎(24)に指を噛まれても屈せず、遂に賊を捕う」と出ていた。
母ちゃんは「ほんとに、人間なんてわからないもんだ。あの人が盗人なんだからね」と言って、尾山田さんの顔を思い浮かべるようにした。その後、(参考人として)安田の小父さんは五六度、奥戸の小母さんは二度ばかり警察へ呼ばれたが母ちゃんは呼ばれなかった。尾山田三五郎は、今は市ヶ谷の刑務所にいるそうだ。
で終わる。川端は、私は子供の文章や、素人(職業的文筆婦人でない)の女性の文章を読むのが好きである。芸術には子供的なるものが多分に含まれている。作家にそれが乏しくなると、油の切れた機械のようで製作(制作)が乾いてくるらしい。批評家もそうである。専門の批評家には、よくそういう人があって、感受性が動かず、生物の作品と無生物な比評家とが睨みあったようなことになる。この「尾山田三五郎」は一見、子供らしさ、娘らしさは目立たぬようである。飾りとしてのそれはない。つまり感傷の曇りがない。単純な写真機に焦点がぴたり合ったような、鏡が無心に写したような、驚くべき写生である。素朴な写生文の極北である。とべたほめである。
映画に続いて豊田は『婦人公論』に創作を寄稿し、戦時中には中国を視察、戦後は作家、随筆家として活躍した。手元にある岩波文庫の『新編綴方教室』にはこの「尾山田三五郎」が「小山田三郎」の題名で収録されている。しかも文中の名前や豊田が引用した新聞記事まで全て「小山田三郎」に変えている。解説には川端が昭和13年(1938)11月3日から7日にかけ朝日新聞「文芸時評」の第一番に豊田を取り上げたことを、岡本かの子、円地文子、宇野千代ら女流作家らの小説と並べ「充分立派と言えよう」と書いたと紹介しているが、題名は(本書の「小山田三郎」)としているだけである。
初対面の豊田が子供心に「何となく嫌らしい人」と思ったという直感を書いた「尾山田三五郎」という名前は小山田が使っていた<偽名>だったのではあるまいか。さすがの岩波書店にしても新聞の続報でも見つかればだが、そこまでの確証は得られなかったのだろう。