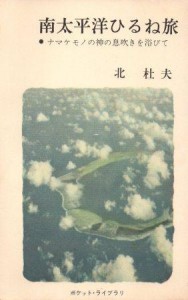書斎の漂着本(75)蚤野久蔵 南太平洋ひるね旅
北杜夫の『南太平洋ひるね旅』(昭和37年=1962)は往年の新潮社ポケット・ライブラリの一冊である。「どくとるマンボウ」シーリーズの随筆や『楡家の人々』、『白きたおやかな峰』などの小説を仲間内では一番多く読んだが、読み終わるたびに「読んだ、読んだ!」とはしゃぐので、北がカミングアウト(=告白)した躁うつ病の「躁」のほうじゃないのかと心配されたこともある。自分としては読んだ本の面白さを誰かに話したかっただけなのに。一時は本棚いっぱいに並んでいた北の著作も引越しのたびに他の本と一緒に処分したのでこの本と『マンボウ雑学記』(岩波新書)だけになった。
北杜夫はペンネームで、本名は斎藤宗一。父が伊藤左千夫門下で「アララギ」の中心人物として活躍した歌人・斎藤茂吉なので<親の七光り>と陰口をたたかれるのを嫌って使い始めた。松本高校から東北大医学部に進んだので、東京からは北にある杜の都・仙台にちなみ「北」と「杜」、心酔していたドイツの作家トーマス・マンの『トニオ・クレーゲル』から杜二夫、それをあらため杜夫とした。その後、順次、「東」「西」「南」と変更するつもりだったらしいが、「北」が売れ始めたので実現しなかった。
脱線しそうになったので『南太平洋ひるね旅』に戻る。冒頭、
たった一回船に乗っただけなのに、人は私が旅をするというと、ほかの乗り物のことを考えてくれない。
「こんどはどんな船で?」と聞く。
私は申し訳なさそうに言う。
「それがどうも、飛行機なんで」
するとみんなは、あきれたように肩をすくめる。
たった一回というのは水産庁の漁業調査船「照洋丸」の船医を半年間勤めたことによる。わずか半年なのに「どくとるマンボウ」があまりに有名になったのでこういうやりとりになったわけだ。この「ひるね旅」は、飛行機でハワイ、タヒチ、フィジー、ニューカレドニア、サモアを巡って再びハワイに戻る、まさに<南太平洋のアイランド・ホッピング>である。下図の右上がハワイ諸島、右下がタヒチ、左のオーストラリアに一番近いのがニューカレドニアだからおおよその位置関係がお分かりいただけるのではあるまいか。それぞれに直行便がある現在でも、考えられないほどの移動距離だから飛行機利用はやむを得なかったのだ。
だしぬけに、まったくだしぬけに、大きからぬ窓に区切られた視界の中に、やや逆光をあびて、一つの島が忽然とあらわれてきた。それは実に魔法にも似た、胸をしめつけられるような出現で、子供時代からの夢を実現した形態と色彩であった。島はほとんど奇怪と言ってよい。突兀とした峰がいくつも突出し、その麓は海岸にまでひろがっている。島のまわりを、くっきりとリーフの白い線がとりまいている。油絵具そのままの鮮やかさである。島全体は、緑でもない、藍でもない、灰色でもない、そうかといって黒でもない、それらを混合した一種異様な色彩なのである。私は瞬間胸をつかれた。よくぞここにやってきたと思った。
ホノルルからの飛行機が遅れ、夜明けにタヒチの隣のモーレア島上空に差しかかった光景である。予定通りなら夜だったので見ることはできなかった奇跡の光景だった。タヒチでは日本の運転免許証を見せただけで簡単に(現地)免許証を発行してもらったのでフィアットの小型車を借りて乗りまわした。
警察での印象ではおそらく日本の少年探偵団の手帳とか米屋の通帳を持っていったにしろ、やはり免許をくれたのではないかと思われる。
と書いているが「米屋の通帳」も死語になったし、さすがに今は昔だろう。果たせなかったのは、画家ゴーガン(ゴーギャン)の息子に会うことだった。昔は漁師をしていたという「ずいぶんでっぷりと肥満している」というその男=ポール・ゴーガンは、波止場の近くの大きな樹の下で魚をとる籠を売っているという。観光船が着くと観光客に写真を撮らせ平然とチップを要求するらしいがとうとう姿を見せなかった。
旅の終わり、サモアではここで人生を終えた作家の墓を訪ねる。『ジギル博士とハイド氏』『宝島』などを書いたイギリス出身のロバート・ルイス・スティブンソンである。以前、一度だけ行ったことがあるという若い案内人は「一般に、その墓はちょっとした丘の上にあると言われていますが、実情はとても丘とは申せない。山、それも山岳といってよいほど意外に困難な道程で・・・」という。
松本時代に北アルプスをかなり歩いた自信があったのに、数歩登ると息が切れた。雨はもうあがっている筈なのに、全身びっしょりと水におおわれている。それが身体からふきでた汗なのだか、梢からふりかかる露なのだか、判断がつかないくらい息をきらした。(中略)あえぎながら登った頂上の草原は十メートル四方くらいの空地にくすんだ墓石があった。墓には三方に銅版がはめられている。その一つには彼自身の手による詩句が刻まれている。彼の愛する妻、サモアの名では飛ぶ雲を意味するアオレレと呼ばれた米人の妻をうたった詩が刻まれている。南方特有のものうい静寂の支配した山頂を一尺もあろうかと思われるほどの大コウモリが、今はまばゆいほど輝かしい光線のみなぎっている青空を背景に、真っ黒い羽を水平にひろげて二度三度と旋回した。
日本脱出の2カ月、アオレレのように放浪した「どくとるマンボウ」の紀行が終わる。