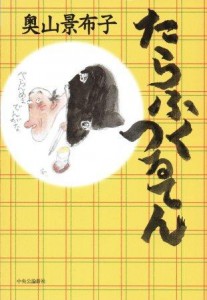新・気まぐれ読書日記(35) 石山文也 たらふくつるてん
奥山景布子(きょうこ)の『たらふくつるてん』(中央公論新社)は「江戸落語の始祖」といわれることになる鹿野武左衛門のおもしろおかしく波乱に満ちた半生を描く。
奥山景布子著『たらふくつるてん』(中央公論新社)
京都のしがない漆塗り職人・塗師(ぬし)の志賀武平は何よりも興行好き。人と話すのが苦手、猫背気味でまだ三十過ぎなのに白髪交じりの小男のうえ胡坐をかいた鼻の穴が上を向いている醜男で、女房から「お前さんの陰気な顔があかんわ。なんとかならへんのかいな」と言われている。きょうも立ち寄った北野天満宮の境内で、お目当ての露の五郎兵衛の辻咄(つじばなし)の人垣を見つけると最後まで聞いてしまい、女房の不興を買う。大阪・生玉社で一昼夜かけていかに多くの句を詠むかを競う井原西鶴の矢数俳諧が行われると聞くと仕事も身に入らず、親方に頼み込んで休みをもらうと女房には内緒で伏見から大阪行きの三十石船に乗ってしまう。ところが上りの船に乗り遅れ、さらに一晩過ごしてようやく自宅に戻ると女房は実家に帰っており、二度ほど詫びを入れに行ったが、結局本人には会えずじまいで泣く泣く離縁状を書くことになった。悪いことは重なるもので仕上がった刀の鞘を納品に行った武家の屋敷で、応対に出た奥方に誘われて酒を飲み、目を覚ますと奥方らが血まみれで死んでいるというとんでもない事件に巻き込まれ、追手を逃れて江戸へ向うことになる。
途中、増水で川止めになった大井川では旅芸人の一座の子どもたちに聞かせていた辻咄のまねごとを親方が気に入り、幕間にやらせてもらうことで宿代がかさみ路銀が乏しくなった窮地を救われる。辿りついた江戸では仕事仲間と吉原に出かけた際に宴席を隣り合わせた浮世絵師・菱川師宣の弟子、石川流宣(とものぶ)らに話芸の才能を見いだされ座敷などで小咄を聞かせる新商売を始める。付けてもらった芸名は本名をもじった鹿野、名前は武左衛門と決まった。やがて三味線弾きのお咲とめぐり合いコンビを組むこととなる。「百人一首」や「伊勢物語」にある本歌を狂歌でからかった話のあとはお咲の三味線の入る芝居仕立ての長い咄がうけた。例えば本歌はよくご存じのこんな咄である。
毎度ばかばかしいお噂を・・・ええ、なんでも昨年の大地震で東照宮さまが壊れたそうで、日光街道沿いのあたりは諸式万事高値で、お困りの方が大勢おいでやそうですな。そんな所を二人の歌詠みが通りかかりまして。『秋の田の刈るまで待たぬ我が命 賤(しず)が体は雨に濡れつつ』。おお、ようできた。では、こんなのはどうや。『田子の底うちのぞき見れば白搗(しろづ)きの 米の高値に我こそ折れける』。おお、ようできた。互いにこう自賛しておりますと、どこからか声がいたします。『起きもせず寝もせで橋に明かしては 薦被(こもかぶ)りとて眺め暮しつつ』宿なしの坊主が近くで寝ておったんですな・・・。
妻の仇討ちを誓って江戸にやってきた武士兄弟とのスリリングなやりとりも収まり、やがてお咲と一緒になった武左衛門は娘、お花に恵まれる。時代は元禄年間に入り、五代将軍綱吉の「生類憐みの令」をはじめとする締め付けはさらに厳しさを増す。それをからかった絵入り狂歌を販売した知り合いの絵師が死罪になると、犬などの動物を使った「落ち」さえ憚れるようになど咄家にも暗い影を落とす。それでも客の「笑い」を取りたい武左衛門はとうとう役人に捕まり、伊豆大島への遠島を言い渡される。ところが出帆した船は大船に辿りつく途中で浸水し、全員が海に投げ出されてしまう。手が縛られ、おまけに猿ぐつわをされた彼ら囚人たちの運命は・・・。
もちろんとっておきの「落ち」が楽しめます、とだけ書いておくが一風変った題名は、冒頭に紹介した露の五郎兵衛の辻咄に出てくる。
「海の底で音曲をいたしまするは、どの魚かな」
「お客人、ようく、三味線の音というものを思い出しなされ。答えはこうじゃ。“たらふくつるてん”、鱈(たら)河豚(ふく)つるてん。ぼってり太った鱈と河豚がヒレで三味線を抱えて、つるてーん!つるてーん!と。おわかりかな」。
おあとがよろしいようで。
ではまた