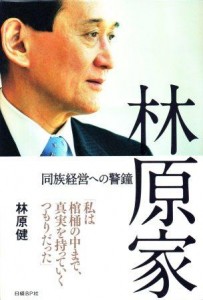あと読みじゃんけん(8)渡海 壮 林原家
変った題名である。「〇〇家」と「棺桶」とくればついつい葬儀を連想してしまう。林原家とは2011年2月に会社更生法適用を申請して倒産した岡山市のバイオ企業・林原の創業者一族である。『林原家』(日経BP社、2014年)の著者で表紙写真の林原健は倒産時の社長だったがその責任を取って辞任した。慶応大学在学中に父の死去に伴い林原の4代目社長に就任、林原を研究開発型の世界的な食品素材、医薬品素材メーカーに育て上げた。突然の倒産は社長就任から50年の節目の年に起きた。
隣県・広島出身の私が「岡山の企業といえば」として思いつくのは<御三家>といわれた天満屋、ベネッセとこの林原だ。デパートの天満屋は広島店に、ベネッセは旧社名の福武書店に知人がいたこともある。林原のほうは抗がん剤として使われるインターフェロンや甘味料トレハロースなどの<本業>よりもモンゴルでの恐竜化石発掘で多くの成果を挙げた林原自然科学博物館や林原美術館など文化・芸術活動を支援する旺盛な「メセナ事業」で知っていた。突然の倒産と書いたのはこうしたメセナ事業も社業の順調な発展があればこそ、と思っていたから林原倒産を新聞記事で知って意外だった。
会社勤めをしていた頃「サラリーマンたるものビジネス書を愛読すべし」と、ことある毎に声高に話す同僚がいた。彼は「それも成功者や、いい成績をあげたトップセールスマンの!」と付け加えるのを忘れなかった。それからするとこの本は「敗軍の将が敗因を語る」わけで間違いなく<論外>ということになるが、古書店の均一棚で見つけた時には副題の「同族経営への警鐘」や倒産に至る経緯などではなく、変わった題名と「棺桶の中まで持って行くつもりだったという真実」とは何かにがぜん興味が湧いた。
「経営破綻の真相」ではメイン銀行だった中国銀行からの電話から始まる経営破綻の発覚、粉飾決算、会社更生法の適用申請、経理部の聖域化などが外部調査委員会の報告書を引いて細かく紹介される。初めて<呼びつけられた>中国銀行の副頭取からは林原が何期にもわたってもう一つのメイン銀行、住友信託にそれぞれ異なる決算書を提出していたこと。実質的には債務超過状態が続いており、それをひた隠すために数字を粉飾していたことが伝えられる。社長の林原はその時まで会社の実態を一切聞かされていなかったという。「社長なのにうそでしょ」と言いたいところだが、企業統治以前に「どうせ林原家の会社だ。どんな経営をしていても自由だ」ということで非上場会社であるのをいいことに役員会は一度も開かれず、名目上の監査役はいるものの会計監査人も置いていなかった等々、常識では考えられないことだらけ。その挙句の倒産という結果がすでに出ているのだからいまさら触れないでおく。
江戸時代、美濃池田家に仕えていた林原家は関が原の戦いの戦功で姫路藩主となった池田公とともに姫路に、さらに鳥取藩への転封に従った。しかし42万石から32万石への石高減少で家臣を養えなくなった。林原家の先祖は藩公の窮状を見て士族を捨てることを申し出て米を取り扱う御用商人になった。1632年(寛永9年)池田公が岡山藩主に転封されると岡山に移り商売を続けた。いまふうにいえばリストラを言われないうちに真っ先に手を挙げたようなものか。当時の階級社会では懲罰としての士分剥奪はあっても自ら進んで武士から商人になることなどまずなかったが、士分を捨てても忠義を果たすことこそ武士の本懐と考えたのだろう。それだけに林原家は武士であったという<誇りと精神性>を現代にまで持ち続け「長幼の序」を重んじた武家社会そのままに長男には絶対的な強さが与えられ弟たちには長男への絶対的な忠誠が求められてきたこと。会社経理は弟の専務や経理部に任せきりの<放任>だったことなどが「林原家の宿痾(しゅくあ)」で明かされる。
明治維新を経て1883年(明治16年)祖父の克太郎が林原商店を創業し、米や芋を原料にした水飴の製造を始める。会社を急成長させたのは健の父で3代目を継いだ一郎だった。大阪商科大学(現大阪市立大学)を卒業すると京都帝国大学(現京都大学)の工業化学教室で飴の製造方法を研究した一郎は事業者と研究者の両面の能力に秀でていた。岡山に戻った一郎は積極的に設備投資をするが原料の高騰や排出される亜硫酸ガスに対する周辺住民の反対運動も起き、あえなく資金繰りが行き詰った。仕方なく林原商店を整理して旧満州に渡るが、再び岡山に戻ると画期的な量産技術を確立し「太陽印水飴」という商標で中国にも販路を拡大した。しかし売上の拡大をもくろんだ材料澱粉の先物取引で再び債務超過となり、倒産状態に陥った。さらに岡山はB29の空襲で一夜にして焼け野原になる。林原も工場を焼失したが、陸軍に納入予定の原料が空襲の翌日に入荷し倉庫に眠っていた。終戦後、一郎は財産すべてを工場再建につぎ込み、終戦5ヶ月目の46年1月に試運転を始める。これが吉と出た。当時は砂糖不足で、国民は甘さに飢えており、水飴は米に次ぐ貴重品だったから多くの「飴成金」が誕生した。群を抜いたのが林原で、年一度の澱粉買い付けは相場を左右すると言われた。
一郎は世の成金が豪邸の新築や遊興などに費消したのに対して、余裕のある財産は不動産、証券、古美術に投資することで完全な利殖の道を講じていった。岡山駅前にあった住友通信工業の工場跡地約5万平方メートルをはじめ「岡山で売り地が出るとことごとく買った」といわれるほど不動産投資に傾注した。対象は神戸、大阪、京都、東京などの一等地にも広がり、計20万坪(約66万㎡)にも及んだことでグループは「林原財閥」、「林原コンツェルン」、一郎は関東での巨大西武グループをつくり上げた企業家と並んで「西の堤康次郎」と呼ばれた。なかでも骨董や美術品には情熱を注ぎ、古物商から多くを買い取った。利殖目的とは別に購入したものもある。収蔵庫が空襲被害から奇跡的に免れた池田家所蔵の美術品や膨大な日記類などは希望を上回る金額を出した。トラック数台分にも上る藩公伝来の遺産はいずれも歴史資料としての価値が高く、将来的には岡山県に寄贈する予定だったがしかし資産目的の土地買収と同一視されたことで、こうした地域貢献さえも地元の評価は毀誉褒貶が相半ばしたことは否めない。1959年、一郎はついに新しいぶどう糖生産技術を確立し、岡山、大阪、東京で同時記者会見を開く。新聞紙上に「林原、酵素糖化法を確立」という大活字が躍り、事業家人生がさらなる高みに登りかけたその時、一郎は急死する。病名はスキルス胃がん、発見から死までわずか2カ月、享年52だった。
後を<いやいや継いだ>健社長の「それからの50年」については触れないでおくと書いたが独自研究に力点を置く経営手法は80年代に量産技術を確立したインターフェロン、90年代のトレハロースなどの成功によって林原をバイオ企業に変身させた。「成功体験とその秘訣」としてあげるのは
1. 大企業がやらない研究テーマを選ぶ
2. 社長が研究テーマを独断で決める
3. 予算に上限を設けず、成功するまで研究する
そして「神は現場に宿る」といって社内の工場を毎日のように歩く社長がいる。それも立派な経営スタイルだろうが私は違う。想像力をかき立てようと思うなら、現場を歩くだけでは無理だ。異分野の識者と話す機会、その咀嚼に時間を費やさなければならない。イノベーティブな会社をつくろうと思ったら、経営者が会社にいる時間は少しでいい。私が会社にいる時間は午前11時半から午後2時半までの3時間と決めていた。青天井の研究費についても持論を展開する。不動産に裏付けられた資金力があり、およそ10年ごとに大きなヒット商品が生まれたことで、管理体制を改めなくても会社は回った。上から締め付けるよりも個々の研究員の自主性を重んじる方が想像性を発揮しやすいのだと。経営破綻したことで、それまでメセナ事業のことを評価していたメディアが「メセナは社長の道楽で、それが破綻を招いた大きな要因」と手のひらを返して批判したことに対しても、投じた金額は年数億程度で会社に悪影響を及ぼす額ではないし、林原が発展していく上ではマイナスよりもプラスになった面がはるかに多いはずだと譲らない。たしかに結果的には林原家が私財を提供することで債務弁済率は93%に達し、社員の雇用も守られた。長瀬産業がスポンサーになってからも林原の社名はそのまま残った。
では、私の関心があった林原自然科学博物館のその後はどうなったのかと検索してみたら、奇しくも2016年3月吉日の「お知らせ」が掲載されていた。発掘標本のモンゴルへの完全返却、その他の化石や研究事業は岡山理科大や国内の博物館などに移管が完了して組織を解散したという内容だった。「あとがき」には、曾祖父が林原商店を創業して祖父に継ぎ、父の林原一郎が発展させ、そして私が会社を倒産させたという林原4代の企業物語にも、大きな時間軸で眺めれば、何らかの意味があったのだと信じたい。もっとも一財産を築いてくれた父には、いつか会うであろうあの世でこっぴどく叱られそうだが、その時はその時だ、と綴る。表紙の写真だけでなく、会社更生法の申請と辞任を発表した謝罪会見の写真を共同通信から入手してまで掲載したのは著者にしてもこの本は自身に贈る<葬送譜>だったのだろうか。