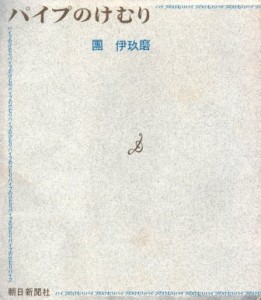書斎の漂着本(89) 蚤野久蔵 パイプのけむり
わが国を代表する作曲家でエッセイストとしても知られた團伊久磨の『パイプのけむり』の最初の一冊である。朝日新聞社の週刊写真誌『アサヒグラフ』への連載をまとめて単行本としたもので昭和40年11月30日刊。連載は平成12年10月15日発刊の「シドニー・オリンピック総集編」を最後に『アサヒグラフ』が77年間の歴史を閉じて休刊となるまで書き続けられた。本のほうも一冊分がまとまるたびに刊行され「続」「続々」「又」「又々」「まだ」「まだまだ」「も一つ」「なお」「なおなお」「重ねて」「重ね重ね」「またして」「さて」「ひねもす」「暮れても」とここまで書いてもまだ半分に届かない。團は連載の最終回で「自分が死ぬのが先か雑誌が休刊するのが先かどっちなのだろうと予想したことがある」と書き残したがその翌年5月、中国への親善使節団として訪問中だった江蘇省蘇州市で心不全により客死した。単行本は葬儀の参列者に配られた「さよなら」までなんと27冊もあるそうだから名実共に国民に愛された名エッセイといえるのではあるまいか。
- 團伊久磨『パイプのけむり』(朝日新聞社刊)
これは愛読者だった父が私に遺贈してくれた一冊である。他に何冊かあったが最初のいわば「正」にあたるこれだけを持ち帰った。本を大事にした父らしく購入時そのまま表紙には透明のビニールカバーがかけられていたが汚れていたので捨ててきた記憶がある。判型はいわゆる菊変形判の幅16センチ、高さ18センチとほぼ正方形で昭和39年6月5日号掲載の「ハンドバッグ」から同40年8月6日号の「あぶってかも」までの61回分が収録されている。
團は「あとがき」で、この連載を始めてからの一年半は僕にとって音楽的に豊饒な時であった。「オリンピック開会式序曲」が出来上がり、長くかかっていた「交響曲第四番」「交響曲第五番」が完結し、管弦楽のための「祝典序曲」弦楽のための「合奏交響曲」が完成し、僕自身の原作が脚色された東宝映画「戦場に流れる歌」の音楽が出来上がり、沢山の歌が出来上がり、それぞれが初演され、世の中に送られていった。(中略)音を書く時の僕は音を書く時の僕なのであり、文字を書く時の僕は文字を書く時の僕なのであり、僕にとって言い得る事は、音の世界と文字の世界は全く別の世界であり、その別の世界を生半可に混同したとすれば、その瞬間に、すべての音と文字は白い煙とともに消え失せてしまうものである。管弦楽の響きと合唱の高鳴りが渦を巻き、ピアノの走句(パッセージ)やソプラノの顫音(トリル)が飛び交う中で生活しながら、作曲と自作の演奏に従っている僕にとって、毎週木曜日と金曜日には、机の前で静かに過ごす時間を持つことがきまりで『パイプのけむり』を書くためである。毎週後半に訪れてくる静寂の時間は、何にも代えがたい大切な時間であった。そして、僕はこの時間を好きであった。
いくつか紹介しようと思って読み始めたらやめられなくなり結局、数時間がかりで全部を読んだ。根っからの活字好きというよりは、ま、ヒマなのでしょうね。第一作の「ハンドバッグ」は女性が持ち歩くハンドバッグの中身を見たいと思いながら果たせないという話である。それは男の目の届かぬ女性だけの秘密の空間であるから、気も狂わんばかりに見たく、また、身の毛がよだつほど見ることが恐ろしい。古事記から「夕鶴」の与ひょう、オルフェウスも見ることによって悲劇を招来した。何もそれほど大袈裟に考えるわけではないにしても、死ぬまで、きっとハンドバッグの中は見ないだろうと思う、という何とも屈折した心理を告白している。
「馬」は昭和20年4月13日の夜、東京大空襲で、当時、陸軍戸山学校軍楽隊の鼓手であった僕は、炎上する兵舎の火の手を消そうと奮闘したが及ばず、塀を越えて避難するなかで隣の東部第四部隊の燃える厩舎から逃げ出した数百頭の軍馬の中に取り残されたという恐怖の体験である。「王徳忠」は中国や台湾の服飾関係者かデザイナーだと思い込んでいたらフランスから伝わった服飾用語のオートクチュールだったという話で、外来語をありがたがってそのままカタカナで使いたがる国民性を皮肉る。あまりに無意味な外来語の氾濫に対するアイロニーは「天声人語」でも取り上げられたそうだ。「色盲」は小学一年生の図画の時間に、そうとは知らない教師から描いたクレヨンの色が違うと叱責されて廊下に立たされた辛い思い出。「義歯」は歯が悪かった僕はロンドン滞在中に駆け込んだ歯科病院で全身麻酔をかけられて一度に18本の歯を抜かれてしまう。退院後、一か月かけて通院した義歯専門医に製作してもらった義歯はなかなか具合がよく、久しぶりに行った英会話の先生に「ミスター・ダンは急に英語の発音が良くなりましたね」と訝られた。「それは当然でしょう。英国製の義歯ですから」と答えたが、こんどヨーロッパに行ったらドイツ、フランス、イタリアでそれぞれ義歯を作り、それらを「嵌め替える」ことで各国語を流暢に喋りまくろうと思う、というユーモアが笑わせる。
「暗殺」は昭和7年3月5日の白昼、日本橋の三井銀行本店前で車を降りた祖父の三井合名理事長、團琢磨が右翼・血盟団のテロリストによる暗殺に倒れた。75歳。「血盟団事件」である。白布に覆われた遺骸は、その日の午後原宿の家に帰って来た。報道陣の人達や、突然の凶変を聞いて駆け付けた弔問客のごった返す中で、僕は父に連れられて祖父に対面した。遺骸を覆っていた白布が静かに取除かれた時、僕は祖父の白い死顔を見た。顔色は異様に白く、頭髪も白く、綺麗に刈込まれていた髭も白かった。あたりの喧騒をよそに、白布の上の一点だけには異様な程の静寂が漂っていた。祖父の突然の死は8歳だった僕には何のために何者によって殺されたのかは知らされなかったが生まれて初めて見る<死>が其処にあり、<死>は滅法に白く、静寂であって、僕をいつも膝の上に乗せて可愛がってくれた祖父が、何か人為的な事件の結果もう動かないのだけ理解するのがやっとだった。
最後の「あぶってかも」も祖父の思い出につながる。四つか五つの頃、僕は、祖父が朝食をとる時、いつも膝に抱かれていた。福岡出身の祖父の朝食には、必ずと言って良い程、故郷の味のおきゅうと(ところてんに似た海藻の加工食品で博多人のソウルフード)とかあぶってかも(スズメダイ科の小魚を一塩にしたものであぶって食べる)が並んでいた。祖父は、大好物のあぶってかもの身を小さく毟(むし)りながら、小さかった僕に時々その僅かを食べさせてくれた。あぶってかもは良い香りがした。そしてあぶってかもは美味しかった。小さかった僕は、いつも祖父にせがんだ。あぶってかも。もっと。あぶってかも。
博多での一夜、女友達のアパートで「あぶってかも」をごちそうしてもらうことになる。
「さあ、焼けたわ」
小皿に盛った四尾の小魚の中の一つを手に取った。熱かった。それを毟った。その身を噛んだ。そして嚥んだ。毟れば毟るほど、噛めば噛むほど、嚥み下せば嚥み下すほど、涙が出て堪らなかった。僕はいつまでもその動作を繰り返し、いつまでも涙が止まらなかった。
女友達は、じっと部屋の隅に立ち竦んで僕を見ていた。
「疲れていらっしゃるようだわ。おやすみになった方が良いと思うわ」
然し、いつ迄も、僕は、この貧相な小魚を毟るために俯(うつむ)いていた。