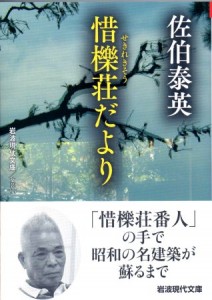あと読みじゃんけん (13) 渡海 壮 惜檪荘だより(その2)
実はこの『惜檪荘だより』(岩波書店)を読むまで、知らなかったというか、気付かなかったことがある。著者は人気時代小説の『酔いどれ小藤次留書』や『居眠り磐音 江戸双紙』シリーズなどで活躍しているのはご存じの通りだが、1970年代には写真家としてスペインに滞在し「黄金の時代」といわれた闘牛社会を取材していた。私は以前、鹿児島県の徳之島で「伝説の横綱」として活躍した実熊(さねくま)牛を描いた小林照幸のノンフィクション『闘牛の島』(新潮社、1997)に惚れ込み、沖縄に売られていった実熊牛の哀れな末路を追いかけたことがある。そういえば、と書庫の奥から探し出したのがこの『闘牛はなぜ殺されるか』(新潮選書)である。同一人物だったとはと不思議な偶然に驚いた。
「闘牛への招待」から始まって、地中海一帯にあった牡牛信仰、男社会から女の時代に変わる「闘牛社会の変革」、「闘牛はピカソに何を与えたか」、「闘牛はなぜ午後5時に始まるか」など微に入り細にわたり闘牛を紹介した労作である。題名の理由は、牡牛は信仰の対象で猛きものの代名詞として闘牛場の砂場に登場するが「祝祭の当然の帰結」として殺される。表舞台からラバに引かれて去ったわずか5分後には食肉として処理される。年間3万頭以上もの牛が闘い死んでいく闘牛は「スペイン文化の神髄」とされ、失業率の高い国を支える観光産業ではあるが、動物愛護の思想が強く主張されるにしたがって捕鯨反対の国際世論に押されて商業捕鯨が禁止されたように確実に衰退の道を進むだろうと示唆している。
写真家時代に佐伯が取材に同行したのは作家の堀田善衛、詩人の田村隆一、英文学者の氷川玲二らがいる。一時期、佐伯は堀田がマネージャー役の夫人と住んでいたスペイン・グラナダのマンションに運転手兼小間使いとして居候していた。いつもは寡黙でレース編みなどで静かに時を過ごしていた夫人は一度その勘気に触れると老練の編集者も出版社の重役も震え上がる。日本では永く逗子に住んでいたから「逗子のライオン」と怖れられていた。あるとき「佐伯、作家というものはね、文庫化されてようやく一人前、生涯食いっぱぐれがないものなのよ」としみじみ、そして誇らしげに呟いたという。芥川賞作家の堀田は老舗文庫に名を連ねていた。売れっ子作家は雑誌連載をハードカバーに纏め、さらに数年後か十数年後に、読者と識者の厳しい目に曝され、価値を認められた本が「古典」として文庫化されるのだと言いたかったわけである。田村からは詩人らしくあれこれあった人間関係を学んだ。スペインで知り合った氷川とはその生前20年ほどの付き合いがあり、文章の手ほどきを受けた。いまでも覚えているのは「原稿用紙でもいい、初校ゲラでもいい。一見して黒っぽく感じたら、こなれた文章ではないということだ」と教わった。こうしたエピソードが惜檪荘修復のさまざまな場面に挿まれているから、単に熱海での専門家を巻き込んだ純粋な工事進行の紹介にとどまらず飽きさせない。
佐伯はなぜ仕事場の条件として「海の見える地」を選んだかについてあらためて書く。スペイン時代にお金の工面を願った佐伯に母親は「先祖は豊後の大友宗麟配下の地下者(じげもん)で、天正年間、薩摩に追われて肥後に逃げた一族であるから恥ずかしい真似だけはするな」と手紙で説諭した。豊後はリアス式海岸の海の国、南蛮に憧れを抱いたキリシタン大名の大友宗麟が活躍した地である。佐伯は福岡県の旧八幡市折尾(現・北九州市)生まれで「幼い頃は海への思い入れが格別にあったとは思えないが後年、時代小説を書くようになった時、豊後を迷うことなく物語の舞台に選んだ。スペインに憧れたのも宗麟が夢半ばにして潰えた野望を思うてか。また海を想う気持ちも海の民の豊後者だからか、ともかく私の体内にも同じ血が流れていて海に憧憬を抱いたのだと勝手に考えている」と。だからか、『酔いどれ小藤次』の主人公赤目小藤次にしても豊後森藩ゆかりで『居眠り磐音』の坂崎磐音は架空だが豊後関前藩中老の嫡男という設定だ。
修復工事に戻ろう。建築当時の設計原図は吉田が描いた22枚のスケッチが東京芸大建築学科に残されていたが、現況の「実測図」を起こすことからはじめられた。窓の金具から戸車にいたるまで原寸大で、さらに床下と天井にはカメラを入れて現況を出来るだけ正確に把握することが進められた。吉田は京都からわざわざ職人を呼んでさまざまな工夫を凝らした。なかでも洋間の開口部は、雨戸、網戸、ガラス戸、障子、それぞれ3枚、計12枚の戸をすべて戸袋に仕舞うことで創られた開口部=額が醸し出す壮大な「絵」でまさに<十二単>を思わせた。のちに岩波ホールの支配人岩波律子に聞いたエピソードが紹介されている。ここに一夜泊ったポーランドの映画監督アンジェイ・ワイダ夫妻が窓からの眺めに感動した。日本画、なかでも浮世絵にも関心があった監督の絵には歌川広重風の斜めに突き刺さる雨が描かれていた。<吉田の黄金比率>ともいわれる横広のガラス窓をそのまま額縁に見たてたか。静的な雨だれよりもあえて広重の動的な雨を描くことで滞在記念の絵にダイナミズムの息吹を与えている。
工事はまず、洋間の床板のチーク材が一枚一枚丁寧に剥がされてナンバーが打たれた。吉田デザインの応接セット、文机、天井の照明器具も取り外され修理技術のある高島屋(=デパート家具部)に預けられた。すべての建具、部材、建物の解体から始まり、例えば石畳は庭の一角に砂を敷き詰めた「仮置場」が作られてそのままの配置で移動、保存された。上棟式には岩波家からワイダ監督が描いた絵と岩波茂雄と親交があり惜楽荘にも縁があった安倍能成の書が届けられた。
長く続いた再建工事については詳細にわたり過ぎることもあるからあえて紹介しない。この間、佐伯に前立腺がんが見つかって手術したり、その気分転換のためにベトナムに旅行したりとさまざまあったが、特筆しておきたいのは佐伯を大いに力づけた俳優・児玉清の存在だろう。古今東西の書物を読破し続けた児玉には『寝ても覚めても本の虫』(新潮文庫)などの著書がある。『居眠り磐音』シリーズが15巻に達した新聞対談が初回だった。児玉は幼い頃、講談本を愛読していて時代小説に親近感を持っており、佐伯の著書を読破していた。いつの日か時代小説を書こうと思っている。それを文庫書き下ろしでねと、どこか引け目を感じていた佐伯の胸中を見抜くように「面白いからこそ読者の支持を受け、売れるんです。悔しかったらキャッシャーのベル(会計レジの音)を鳴らす作家になれということですよ。作家は読者に支持されてなんぼの存在です」と喝破した。児玉はその後も年2回のペースで佐伯と対談し、以来、会うたびに同じ言葉を吐いて鼓舞してくれたばかりでなく、いろいろなところで『居眠り磐音』は面白いよと宣伝これ努めてくれたお陰で、二百万部だったシリーズ累計が五百万部を超え、一千万部に化けた。いわば大恩人である。惜檪荘の洋間で行われたNHKのテレビドキュメンタリーでは「佐伯さん、これはやりがいのあるすばらしいプロジェクトです」とその決断を認めてくれたのに楽しみにしていた完成披露を待たずに亡くなった。
惜檪荘の修復落成式は平成23年(2011)10月13日に行われた。付き合いのある編集者、岩波家と岩波書店関係、不遇な時代を支えてくれた友人知人たちだけで60名になった。そうなると惜楽荘での飲食はできないので、建物見学のあとは近くのレストランでの宴となった。出版関係では角川春樹事務所の御大自ら出席し、乾杯の音頭をとってくれるということが知れると、他社も「うちも幹部を」となったが、それをすべて断ったのも佐伯流だった。当日は曇り空で宴が始まる頃には雨が降り出した。主賓の角川は「新たに惜楽荘主人に就いた佐伯は、時代小説に転じた当初から売れたわけではありません。うちでハードカバーとして出した『瑠璃の寺』は全く出ませんでした、はい。ところが文庫化すると動き出した」とスピーチした。児玉の令息で当時はタレントだった北川大裕も児玉の元マネージャーと出席してくれて降り続く雨を「これは父が流すうれし涙の雨です。おれもこの場に居たかったという雨です」と佐伯を感動させた。なかでも場を盛り上げたのが司会に指名された某社の文庫担当だった。佐伯が考えもしなかったほどの「あがり屋」で、冒頭から惜檪荘を「落石荘」と言い間違え、佐伯を「そ、それでは落石荘番人の・・・」と失笑ならぬ爆笑を誘って会場を大いに和ませた。それもあってではなかろうが、文庫版には背と表紙に、単行本では帯だけにしかなかったルビがふってある。