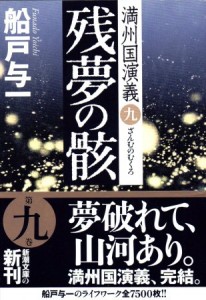新・気まぐれ読書日記 (40) 石山文也 残夢の骸
『残夢の骸』(新潮社)は船戸与一が足掛け10年以上、最後は肺がんの余命告知を受けて残された体力を削りながら書いた『満州国演義』全9巻の完結作である。昨年春、たまたま古書店で入手した前作の『南冥の雫』を読もうとした矢先、船戸の訃報に接した。平成27年4月22日、肺がんの一種である胸腺がんで死去、71歳。記事には同2月に『残夢の骸』の単行本が出版されたばかりで、それが絶筆となったとあった。『満州国演義』は400字詰め原稿用紙で実に7千5百枚、まさに著者畢生のオデッセイ=叙事詩である。船戸作品を多く読んできたし、何かの対談で自身ががんを闘病中ながら『満州国演義』に賭ける思いを語っていただけに「そうか、見事にやりきったか」という感慨が湧いた。
初めて船戸作品を読んだのはもう30年以上前になる。昭和59年(1984)の第3回日本冒険小説協会大賞を受賞した『山猫の夏』(講談社)だった。ブラジルの辺境にある田舎町で起こる血で血を洗う抗争がこれでもかと描かれる。町の名はここに黒人奴隷として連れてこられた人たちの言葉で「悪霊」を意味する。現地を旅した船戸はこの町で数十年も抗争を続ける地元の二大勢力に警察も手が出せない無法ぶりをつぶさに体験する。その原体験を素材として船戸は見事な作品に仕上げた。
ブラジルの東北部を旅すると、時として感じる強烈な眩暈(めまい)を感ずることがある。それは何も暑さばかりのせいではない。そこでは近代が張りめぐらした網から抜け落ちた世界が突如として眼のまえに現れることもあるからだ。熱暑のなかで汗にまみれながら旅を続け、ふと立ち寄った幻の町で見たただの白日夢にすぎない―と語られるすべては<純然たる妄想の産物>である。だが読み始めるとたちまちにして「衝撃の船戸ワールド」に引き込まれた。名前は忘れてしまった船戸が実際に足を運び小説の舞台になった実在の町をようやく「ブラジル全図」で見つけた。ブラジルを大西洋に向いた「顔」にたとえると「鼻」の部分、今回オリンピックが開催されたリオデジャネイロは「下あご」に当たる。首都ブラジリアからなら東北方向に千数百キロ、同じブラジル国内とはいえ、どうやって行くのだろうという地の果てのそのまた果てのような場所だった。何でそんな場所に、と思ったが「早稲田大学探検部OB」という経歴を知ってなるほどねとようやく納得した。以来、『神話の果て』、『カルナヴァル戦記』、『猛き箱舟』、『伝説なき地』・・・と新刊が出るたびに読んだ。しばらく遠ざかっていたが、興味ジャンルの北海道を舞台にした『蝦夷地別件』を完読、この『満州国演義』はそれ以来の作品だった。
さまざまに面白く脚色した話(=白話)を織り込んだ『三国志演義』を略して『三国志』というように『満州国演義』は東京・霊南坂の名家に育った敷島家の4兄弟がそれぞれの生きざまを通してわずか13年間で終わった満州国と<切り結ぶ>壮大な物語である。舞台は満州だけにとどまらない。中国の各都市、蘭領東インドのジャワ、昭南島=シンガポール、英領ビルマからインパール・・・いやまだまだある。ところでこの霊南坂は国会議事堂の南の方角、赤坂1丁目のアメリカ大使館と虎ノ門2丁目のホテルオークラに挟まれたゆるやかな坂である。住所表示は変ったが霊南坂一帯は「東京の一等地」であることに変わりない。敷島家は長州=山口県にルーツをもつ一族で、祖父は奇兵隊で活躍、父は著名な建築家だからこの地に屋敷を構えることができた。
4人はまったく別々の道を歩く。長兄の太郎は東京帝大を卒業。満州国建国のきっかけになった満州事変の勃発時は奉天総領事館の参事官で、国家を創るという最高の浪漫を地でいくように国務院外交部政務処長へと出世していく。次男の次郎は18歳で日本を飛び出し、やがて満州で馬賊の頭目になる。何にも頼らず何も信じない生きかたは風まかせでその日その日をただ生きて上海から東アジアへと流れていく。風に吹かれる柳絮(りゅうじょ=柳の綿毛)の如く。三男の三郎は陸軍士官学校を出ると関東軍の将校として満州全域の抗日武装ゲリラ掃討作戦を指揮する。時には軍規を犯した日本軍将校を射殺するなど剛直な帝国軍人でもある。末弟の四郎は早大生だったが大杉栄の思想に共鳴して左翼劇団に入る。その後、上海同文書院で学び、阿片窟や売春宿での生活を経てロシアと対峙する北辺の武装開拓村、天津の親日新聞の記者、甘粕正彦の満映、関東軍司令部の特殊情報課の嘱託として中国、満州の地を這い回る。
船戸作品は<正史と叛(はん)史をつむぐ力技>と評される。船戸は「歴史とは暗黙の諒解のうえにできあがった嘘の集積である」というかのナポレオン・ボナパルトの箴言(しんげん)を引きながら「小説は歴史の奴隷ではないが、歴史もまた小説の玩具ではない」と喝破する。つまり歴史=正史は客観的と認定された事実の繋がりによって構成されているが、その事実関係の連鎖によって小説家の想像力が封殺され、単に事実関係をなぞるだけになってはならない。かといって、小説家が脳裏に浮かんだみずからのストーリーのために事実関係を強引にねじ曲げるような真似はすべきでない。認定された客観的事実と小説家の想像力。このふたつはたがいに捕捉しあいながら緊張感を持って対峙すべきであると。ではこの『満州国演義』はその対極にある「叛史の集積」なのか。否である。叛史が民衆のアナーキーな情念をも吸収しながら野史とか稗史などと、時にはさげすんだ評に甘んじることがあったとしても「船戸叛史」は少しも揺るぎはしない。ましてや巷間言うところの<自虐史観>とは全く無縁である。
ところで第1巻の『風の払暁』は戊辰戦争で長州奇兵隊の間諜が会津の武家の若妻を凌蓐するシーンから始まる。不肖私、あえて書かれたということは<望まない妊娠>で誕生する子かその子孫が主要な登場人物になるのだろうなあと想像した。この俗過ぎる発想は的中したが、なぜはじまりが戊辰戦争だったのかを見落としてしまったことに『残夢の骸』を読んでいてようやく気付いた。船戸は終戦の玉音放送を太郎と一緒に聞いた同盟通信の記者に日本における民族主義の地下水脈を語らせる。
「日本の民族主義は黒船の来航で一挙に顕在化し、このままでは欧米によって植民地化されるという危機感に包まれた。その打開策を論じたのが吉田松陰だ。それが尊王攘夷となって現れた。明治維新という内戦を終えたあとも吉田松陰の打開策は生き続けた。欧米列強による植民地化を回避するためには国の近代化と民営国家づくりを推進しながらアジアを植民地化するしかない。松陰が『幽囚録』で示した通り朝鮮を併合し、満州領有に向かうことになった。これに日本民族主義の発展形たる大アジア主義が合流し、東亜新秩序の形成をめざして走り出していった・・・それがアメリカの投下した2発の原子爆弾によって木っ端微塵にされた。日本の民族主義の興隆と破摧(さい)。たった90年の間にそれは起った。これほど劇的な生涯は世界史上類例がないかも知れない。この濁流のあとかたづけに日本は相当の歳月を要することになるだろう」
だから、はじまりは戊辰戦争に置いたわけだ。「王道楽土」といわれた満州国はわずか13年で理想の欠片まで失い、重い鉄鎖と化した。終章は昭和21年5月の広島である。三郎が助け、回り巡って預かることになった10才の孤児を連れた四郎が広島駅前のバス停から木炭バスに乗ってその祖父が住む佐伯郡石内村へ向う。満州に新天地をめざす開拓民として村を出ていった三人の息子たちやその家族は一人も帰らず消息すらつかめない。孤児は三男の長男なのである。関東軍に入った父親も、一緒に避難する途中で母親も、妹も死んだ。祖父の「何で死んだんじゃ?」と繰り返す問いかけに「言わんよ、言えん!」・・・嗚咽が慟哭に変わっていく。
四郎はこの子が他人には言えないような地獄に直面したと聞いていたが、それがどんな地獄だったのかは見当もつかないし、別に知りたくもなかった。この時代を生きている人間はだれもが地獄を経験しているのだ、いかに幼くても耐えるしかないだろう。(中略)
歩いて市街地に戻る四郎は脚を速めていった。熱情も憤怒も、高揚も失意も、恐怖も後悔も、満州に絡むすべてはがらがらと音を立てながらどこかへ流れ去っていった。いまや過去に拘ったところで何かが産み出せるわけじゃないだろう。問題はこれからどう生きるかしかない。しかし、どう生きていくのだ?そのまえに、どういうふうに生きたいのだ?この答えは見つかりそうもなかった。
ただひとつ紹介したこの満州の大地で生きながら地獄を見た孤児と祖父との再会場面にしても何かの救いがあるわけではない。四郎にも少年にもただふるさと日本に戻ってこられたというだけで、夢破れて山河あり。それにしてもさまざまな舞台でさまざまに描かれた地獄絵図に比べれば命がつながっただけでも。「不感症になれ。そうでなくては、気が狂う」というフレーズが頭の片隅にまだ消えずに残っている。
船戸はあとがきに「資料渉猟はわたしのもっとも苦手とするところである。文献に当たっては執筆し、執筆しては資料を再確認するという作業の繰り返しは苦行僧の営為のごとく感じられた」と書く。たしかにこの作品を仕上げるには膨大な量の文献との格闘が不可避だったろう。巻末にまとめられた参考文献は、単行本では13ページ、文庫本では23ページに及ぶ。船戸はさらに「文献を読むかぎり」と前置きして、「昭和初期の時代の濃さは後期とは比較にならない。戦争。革命。叛逆。狂気。弾圧。謀略。抗命。破壊。哄笑。落胆。敗戦。抑留。幕末維新時に巣立ちした日本の民族主義が明治期に飛翔しつづけ、第一次世界大戦後の国内外の乱気流に揉まれて方向感覚を失い、ついにはいったん墜死を遂げるのだ。あらゆるものがぎっしり詰まっている。そしてこの濃密な歴史は満州を巡る諸問題を軸に展開していく。わたしは昭和19年山口県生まれで、戦争にたいする記憶がまったくないにも拘わらず、満州を舞台に四つの視点からの叙事詩を書きあげようと思ったのは凝縮された時間に引きつけられたからに他ならない」と付け加える。
さて、この大作をどう読めばいいのか。単行本をじっくり読むのもいいかもしれない。私なら各巻に解説が付いた文庫本のほうをお勧めする。あえてその顔ぶれを紹介すると第1巻『風の払暁』が馳星周、第2巻『事変の夜』が志水辰夫、第3巻『群狼の舞』が北方謙二、第4巻『炎の回廊』が高山文彦、第5巻『灰塵の暦』が西木正明、第6巻『大地の牙』が北上次郎、第7巻『雷の波濤』が高野秀行、第8巻『南冥の雫』が佐々木譲、この第9巻『残夢の骸』が井家上隆幸である。いずれも船戸と親交があり、日本における冒険小説というジャンルの地平をともに切り開いてきた、あるいは文芸評論家として見続けてきた面々である。船戸という稀有な作家を、いや歴史を舞台にした小説というものをさまざまな面から案内してくれるはずだ。選りすぐりのガイド役9人を従えていざ行かん。この一大歴史小説を読み解き、あるいは歴史そのものに内在する欺瞞を学ぶもいい。シリーズの題を船戸が「演義」としたのもそこにありそうに思う。
ではまた