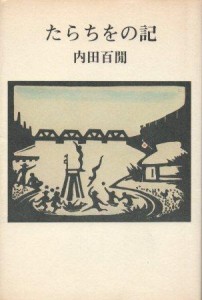書斎の漂着本 (91) 蚤野久蔵 たらちをの記
内田百閒の『たらちをの記』(六興出版)である。どこの古書店だったか忘れたが変わった題名が目について購入した。自宅に帰って辞書を引くと母親の枕詞「たらちね」の反対語で父親の枕詞を「たらちを」というとあった。装画は百閒お気に入りの版画家・谷中安規。作風は天真爛漫、自由奔放で、生きることも食べることにも頓着せずに放浪したことで「稀代の偏屈作家」といわれた百閒から「風船画伯」と呼ばれた。共通していたのは家庭環境が複雑だったこと。百閒は収録された表題作品や『枝も栄えて』、『葉が落ちる』などで父との思い出を書いているが、谷中も奈良・長谷寺門前の名家に生まれながら6歳で母親を亡くし、女出入りの激しかった父のもとで多感な少年時代を過ごした。この本は「偏屈作家」と「風船画伯」のコラボレーションと考えるとおもしろいかもしれない。
『たらちをの記』は、岡山の古京町にあった志保屋という造り酒屋の婿養子だった父親の久吉が、ひどい「藪にらみ」で、それを眼科病院で手術したのを店の人に連れられて見舞いにいった記憶から書き始める。
手術は目玉を一たん引っぱり出して、裏側で引っ釣っていた筋を切ったとかいう話なので、聞いただけでも気持ちが悪かった。しかしそのお蔭で父の目は普通になったから、晩年の俤(おもかげ)を思い浮かべても別に変ったところはないが、まだ若かった頃、母と一緒に神戸に遊びに行った時写したという硝子写真を見ると、ひがら目で洋服を着込んで、猿が怒ったような顔をしているので、これが私の父かと思うと感慨を催すこともある。
花街で遊び夜明けに戻って祖母に頭を下げる父。褌一つの裸になって縁側にあぐらをかき、後ろから使用人に四国丸亀産の大きな団扇であおがせ、酒を汲み、機嫌がよくなれば歌も歌った父。
まるい玉子も切り様で四角
こがるる、なんとしよ
物も云い様で角が立つ
東雲(しののめ)の、ストライキ
さりとはつらいね
テナ事、仰いましたかネ
やがて家産が傾き没落していくが、それでも世間の人が「志保屋の久さんは、遊ぶことは遊んでも、商売の目が利くから、身上は却って先代よりも太っている」とほめた噂や、買ってもらって一番うれしかったオルガンのことをくわしく紹介する。当時、35円もしたという「山葉(=ヤマハ)オルガン」はわざわざ大阪心斎橋の店まで連れて行ってもらって購入、荷物を上下にしてはいけないという注意書きの「天地無用」の荷造りをして岡山に送らせた。壊れるたびに何度も修理して大事に使い、東京に出る際には、ふたたび「天地無用」の荷物として持ってきた。生活に困窮して何度も差し押さえの札を貼られながらもその都度、最優先で取り戻した。<父の思い出が詰まっていた>からでもあったろう。
明治38年(1905年)百閒17歳の夏、父親は岡山市郊外の佛心寺という山寺に脚気の転地療養に行ったが、病気が重なってそのお寺の一室で亡くなった。
最後の日は、父が起こしてくれというので、父の姉がそっと後ろから抱き起こした。それで北向きに坐って、暫く庭の方を見ていたが「これでいい、もう死ぬ」といってそのまま静かに目を閉じた。父の手を執って、その膝の前に額いた私は、十七の頭で、今の父の一言と、それに直ぐ続いた死との境い目を考え分けることができなかった。
『葉が落ちる』に書いた
山蝉の鳴き入りて鳴き止まず佛心寺
は、百閒が父に贈る追悼の句か。
山寺の病床で、父はそれまでの苦しみがうそのように、ほっと楽になった。その時、父の魂は抜けて飛んだのであろう。
これは裏表紙のカットである。満月の夜、お寺の庭で踊る人たちを本堂の仏様が見守っているようにも見える。酔えば踊り出すという奇癖があったという風船画伯・谷中は昭和のはじめ版画家として注目され、もうひとりの版画界の巨人・棟方志功と同じ時代を生きた。しかし棟方が「世界の棟方」と呼ばれたのに対し、東京大空襲で住まいを焼かれ終戦翌年の秋に栄養失調で餓死した。
ところで垂乳根と漢字があてられる「たらちね」には忘れられない思い出がある。二十数年前、津軽海峡をシーカヤックで横断した帰りに青森県の日本海沿い、深浦町北金ヶ沢にある樹齢千年以上の大イチョウをオッサンふたりで見に行った。幹のあちこちから乳房状というか鍾乳石のような無数の気根が垂れ下がっているところから別名「垂乳根銀杏」という日本一大きなイチョウで、古来、多くの女性たちが「母乳がよく出ますように」と祈った信仰の対象であったという。夏場だったから青々と繁った葉群を見上げながら一周したが<乳房>はいずれも失礼ながら老婆のそれであるなあと思った。ご一緒したのが若い女性だったらこちらの考えが見透かされるかもしれないと思ったから赤面していたかも。脱線ついでにこの本を入手するまで正直知らなかった「たらちを」は垂乳男と書くそうな。相撲界に転じると理想の力士像といわれた「あんこ型力士」より筋肉質の痩せ形が注目される時代である。昔なら幕内に何人かいた<垂乳力士>は影をひそめ、このことばもいまや「死語」になって久しい。