季語道楽(30)季語はどのように生まれたのか 坂崎重盛

“地貌“論を提唱する宮坂静生の『季語の誕生』に戻りたい。
くりかえしになるが、宮坂は“地貌”とは、「風土の上に展開される季節の推移に基づく生活や文化までを包含することば」とし、“地貌”と、季語の重ね合わせを説く。
まさに、すでに紹介した正岡子規の、
「盛岡の人は盛岡の実景を詠むが第一なり」ということになる。しかし、その上で宮坂は必ずしも実現をそのまま詠んだところで、当然のこと、それがそのまま俳句にはならない、とクギを刺すことを忘れない。本文から引用する。
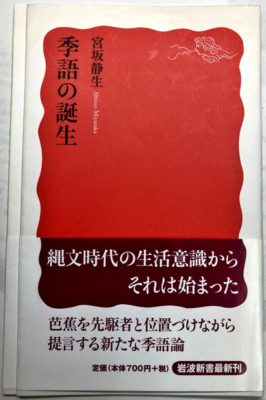
季語の誕生 著:宮坂静生
私はその一方で、俳句を作るとは現実の世界から一尺(三〇センチ)上が
ったところに舞台を設けて、そこでドラマを演じることだとつねづね説い
ている。
俳句を︱︱現実世界から三〇センチ上に舞台を設けて、そこでドラマを演じること︱︱という俳句世界を説明する宮坂の比喩は解りやすく、また的を射ている。カッコイイ。
さらに言葉をつづけて、
俳句という詩型は十七音ときわめて短い。ことばを選びぬき短く集約し
て表現することは、すべての対象から少し距離をおいて反リアリズム、フ
ィクションの世界のことばで構成することだ。
と、実景(や実体験)というリアリズムと、俳句という短詩であり、フィクションの関係を確認する。
“地貌”という概念は、おおよそ理解できたとして、季題の誕生に戻ろう。研究者でもなく、句作に精進する俳人でもなく、ただ楽しみで句を作ってみたり、興味ある俳句関連書を手にしてきたぼくなどは、「季語」というものは、なんとなく、俳句や俳諧連歌とともに生まれた言葉だとずっと思っていた。
ところが、じつは、そうではなかったのですね。
このことは、歳時記の「まえがき」や「あとがき」に寄せられた山本健吉の季語論の文章などで、すでにうっすらとは知っていたもの、本書によって、しっかりと頭にたたき込まれることとなる。自分の“おぼえ”のためにも、本書の「季語(そして歳時記)誕生」の歴史を簡略にメモしておこう。
⚪平安後期(ほぼ一〇〇〇年ころ)勅撰和歌集が出されるまでに“雪・月・
花“に代表される主な「季の題」(のちに「季題」という)、つまり、その
言葉によって喚起される“共通の情感”が成立していた
とされる。
これらは当時の、貴族らの美意識から生まれたもので、季節の移り変わ
の実景に対しながらもより美しい言葉で表現し、またそれを理解しようと
した優美な約束ごととして作り上げられてきた。
そして、この一〇〇〇年ころに形成された、季節の主な題目と、それ以
後増殖、追加されていった季題を集め、季題ごとに分け、編集したものを
「季寄せ」といった。この季寄せの季題に、さらに解説を付し、ときに例
句を示し構成したものが、すでにわれわれが知る「歳時記」である。
⚪平安後期、季の題が成立する世界は、主に京都、また畿内であった。だか
ら“雪・月・花”といっても、それらは京都や畿内の貴族の感覚の中から
生まれ、洗練されてきた“雪・月・花”なのであった。
⚪それが時代を経て、和歌、歌謡から俳諧が成立する江戸時代となって江戸
や東海道の季語や、その土地や文化の理解が加わり、今日の歳時記の姿を
とりはじめることとなる。
⚪その、もっとも本格的、充実した編集内容の歳時記として曲亭(滝沢)馬
金により『俳諧歳時記』(亨和三年╲一八〇三)が刊行され、さらに藍亭青
藍により馬琴『俳諧歳時記』の増補版『俳諧歳時記栞草』が出版される。
この、通称『栞草(しおりぐさ)』こそ、今日のほとんどの歳時記のネタ
本であり、以後、明治、大正、昭和と、さまざまな形で復刊されている。
(今日、もっとも手に入りやすいのは岩波文庫の堀切実校注『増補 俳諧
歳時記栞草』上・下)
この『季語の誕生』では、さらに「季語はどのように生まれたか」で和歌から連歌、そして俳諧に至るまでに季語の“成長”“変化”の過程に、詳しく触れていく。
そして「雪・月・花という季語はどのように生まれたか」の項では、「雪」は「吉事の象徴として」、「花は」は霊力の象徴として」、「月」は「命のあり方を規定」つまり︱︱「人間の出産と月の結びつき」、「人間の原初から生存する本質に関わり」「月以上に人間の生存を規定するものは存在しない」︱︱ (以上本文より)と、月のイメージの重要性を説く。
続く節では「雪」「花」「月」の季語のそれぞれの初源的イメージからの歴史的変遷がさらに解説されて、門外漢であっても知的な好奇心が存分に刺激される。たとえば漢詩からの影響からか和歌の世界では、「雪を花と見立てる」一方「花を雪と見たてる」ことにより、冬籠りのとき草木にとどまった雪が「春に知られぬ花」とするならば、晩春、はらはらと花の散りゆくさまを「空に知られる雪」と見立てたこと。和歌に詠われた「月」の季題が主に中国の古典や民間伝承の知識に由来すると説きつつ「月」という季語のイメージの誕生を、なんと縄文土器の文様を手がかりに考察する。
となると、われわれ二十一世紀の文明肥大社会。コンピュータが新しい神となった時代でも、夜、月を仰ぎ、その光を浴びて、ものを思い、何か無窮の時間や生命のあり方を感じつつ句を作るときは、ひょっとして縄文時代の人間と共通の感覚や意識を抱いているということになる。
たとえば、二人の人間が並んで夜空の月をボーッと眺めているとき、その一人がぼくであり、すぐ隣りに立つ人が縄文人であっても不思議ではないのではないか。これは愉快である。
そんなことまで人に思いおこさせる宮坂静生による労作『季語の誕生』、余談ながら、実は自分で買い求めたものではない。ちょっとしたことで知遇を得た岩波書店のH氏から新刊のときに、贈られたものなのです。この書の「あとがき」(二〇〇九年八月)にはH氏の名が挙げられている。
ずいぶん後になって気づいたのだが、やはり岩波新書の坪内稔典著『俳人漱石』(二〇〇三年刊)の「あとがき」にも 氏への謝辞が記されていた。平田氏はすでに岩波を退職されているが、どのように日々を送っておられるでしょうか。お目にかかって、いろいろお話をうかがい、ご教授をお願いしたいものと思いました。
『季語の誕生』は、ぼくに“季語意識”の誕生をたすける一冊となりました。
なお、『季語の誕生』を読み進めるあいだ、しばらく前に入手していた井本農一著『季語の研究』(昭和五十六年 古川書房刊)をそばに置いておいたものの、ほとんど未読。ページを開くのがさらに楽しみとなった。
次回は、『歳時記』と名を冠した、手元にある種々の書物に触れてみたい。まずは、いわゆる本格的な歳時記ではなく、ジャンルをしぼったいわゆる企画ものから。あれも歳時記、これも歳時記、これがなかなか興味深いのです。妙な歳時記もありますよ。


