季語道楽(34)季語が学べる懇切な実作講座 坂崎重盛

角川書店発行の月刊句誌『俳句』で三年間にわたる連載をまとめた今瀬剛一による『季語実作セミナー』(角川書店刊)
まず、この本の袖に載っている著者略歴を見て、ちょっと驚いた。昭和十一年茨城県生まれ。そのあと、昭和四十六年「沖」創刊とともに参加、能村登四郎に師事︱︱とある。
俳句結社の動向にうとく、興味ある特集のとき以外は俳句専門誌などもめったに入手しないので、この『季語実作セミナー』の著者と『秀句十二カ月』の著者が、句誌「沖」をともに立ち上げた同人で、しかも師弟関係であったとは気にもとめずにいた。ただ、目にとまった歳時記関連本として買いおいた二冊であった。ぼくは、少しでも興味あるテーマの本は、“積ん読派”以前に、とりあえず“買っとく派”なのだ。
ま、そんなご縁があった今瀬剛一の︱︱「季語という俳句のもっとも重要な要素がわかりやすく学べる。総合誌『俳句』の大好評連載、待望の選書化!」と帯に唱われた、この『季語実作セミナー』を開いてみよう。
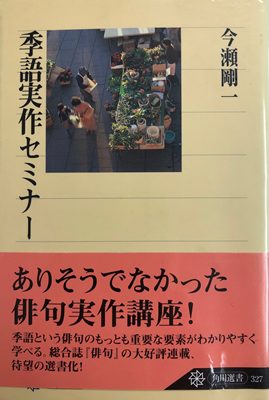
季語実作セミナー 著:今瀬剛一
「はじめに」を読む。「五月、いま私の周囲は全くの青葉である」と、始まり、季節の変化の早さにふれてゆく。そして、
こうした自然の変化、季節の移り変わりのなかにいると、俳句は有季定
型の詩であるという主張には全く疑いをはさむ余地はない。たかだか十七
文字の俳句、何もものを言えない俳句という側面に立つとき、この「有季」
「定型」という二つのことが私にどれほどの力を与えてくれるか、このこ
とを考えないわけにはいかないと思うのである。
と訴え、さらに「とりわけ季語には歴史を経てきた力がある。膨らみがある」としたうえで、高浜虚子の、
遠山に日の当たりたる枯野かな
という、たしか教科書にも載っていた虚子の代表句の一つを提示する。そして著者は、
「枯野」の力強さ、広がり、そしてその強さ広がりは単に表面的なものに
とどまってはいない。それは清浄たるかつての人間全てが見聞した枯野、
生きて泣いた枯野、歩き疲れた枯野……、そのような意味から人生そのも
のの象徴の響きも持っている。
と解説する。とても説得力のある読みだ。さらに著者は、
ただ気をつけなくてはならないのは季語に纏(まつ)わる既成概念であり、
そうした意味からは、季語を一つ一つ洗い直してみることも大切であると
思う。
と、この本の目的の一つが“季語の洗い直し”見直しであることを明らかにしている。
さて、本文、第一章は「季節の移ろいを詠む」早春の季語【二月】からスタート。〈︱︱ さあ春だ、句帳を持って外へ出よう〉と始まる。例句として、
春なれや名もなき山の朝がすみ 芭蕉
枯れ枝に初春の雨の玉円か 高浜虚子
を挙げ、解説を付しているが、︱︱「春だなあ」という感嘆の声は芭蕉の作品に比べて静かである。それは作品の背後から聞こえてくる︱︱と語り、つづけて、
山深み春とも知らぬ松の戸にたえだえかかる雪の玉水
という新古今集、式子内親王の和歌を引き、
古来こうした情景は短歌にも詠まれているが、「円か」とまではとらえて
いない。ここに物を確かに見るという俳句の特性、あるいはもっと大きく
言えば実際に対象を外に出してみているかいないかの違いがあると思うの
である。
と同じ季節感の中で、それを詠むにしても観念でとらえる和歌と、実際の観察を通して表現する俳句の差を指摘する。
次が〈二 春を見よう、聞こう〉ここで著者は「要は自分の目で春を見付けること、自分の耳で春を聞くこと」とアドバイスし、
鎌倉の古き土より牡丹の芽 高浜虚子
みつけたる夕日の端の蕗の薹 柴田白葉女
山川のとどろく梅を手折るかな 飯田蛇笏
の三句を示し、虚子の句に対しては︱︱この作品の全ては「牡丹の芽」を見付けたところから始まっている︱︱とし、白葉女の句には、作者はまず「みつけたる」と直叙した︱︱そして、「蕗の薹」を提示しているだけで、読者のその感動を自由に味わわせている、と解説し、この一文の締めとして、
俳句とは述べるものではない、これは俳句を作るときの鉄則である。
と、われわれ初学の人たちにとって、句作のもっとも重要な“肝(きも)”を伝えてくれている。
二作目の蛇笏の句に対しては、
山々に響き渡る川の轟音(ごうおん)の中、一枝の梅を手折ったのである。
ぽきりという音は小さい音ではあるが確かに轟音のなかに一瞬響いたこと
と思う。その確かな音。
と解説する。なるほどなぁ、春近く雪解けとなる季節、山川の大自然の轟音に対して、手折った梅の枝の、小さな、しかし確かな、生命の証のような音、俳句はたった五・七・五の十七文字で、こんな、真実の、臨場感のあるスケールの世界まで描き出してしまうのだなぁ、といまさらながらの感慨。
そして〈三 春を行動してみよう〉〈四 私の推薦する早春の季語〉〈五 そのたの早春の季語、作句してみよう〉と、実作セミナーは進んでゆく。
また、初心者のための〈こんな作り方はいけません〉〈晩春の作品の失敗例〉〈どんなときに失敗するか〉〈晩春の作品、失敗三つの例〉などと、それぞれ例句を挙げながら、その問題点と改良句(添削句)を示す。
親切な季語活用、まさに実作セミナーとして構成され、同時に歳時記であり、季寄せの俳句入門書となっている。
(この項つづく)



