季語道楽(38)”隠れ歳時記”の自在さを楽しむ(1)坂崎重盛

「歳時記」とは銘打つものの、単なる随想、エッセイ集だったりする本も、まま、あるが、一方、エッセイ集かなと思いつつも手に取ってみると、これが、きちんと四季折々の句が添えられていて、歳時記のバリエーションとして、無視できないこともある。いわば“隠れ歳時記”。
こういう事情は、目録やインターネット上での紹介ではなかなか、そこまではわかりにくいだろう。手に取って、本を開いてチェックするしかない。また、このように街を歩き、書店や古本屋さんの棚の前に立たずみ、本と接するアナログ感というんですか、身体感が、漁書の楽しみ、醍醐味でもあるでしょう。
手元にある、二、三例を挙げてみた。
- 『やじうま歳時記』(ひろさちや著・平成六年 文藝春秋・平成九年 文春文庫・刊)
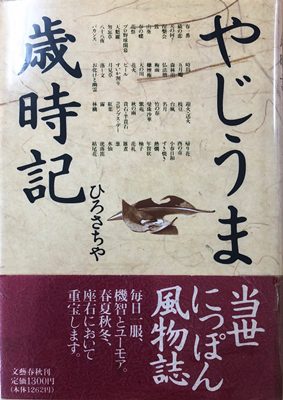
やじうま歳時記 著:ひろさちや
まず、失礼ながらこのタイトルで本が出版されたというのが、今日の出版事
情を知るぼくなどにとっては驚きである。刊行は1994年、二十六年前。もちろん著者に固定ファンがいたということでもあるだろうが、まだまだ出版界にパワーがあったということだろう。
閑話休題、今のその『やじうま歳時記』を読む。例によって、今の季節の章を開く。——夏——。扉には「夏はただ昼寝むしろに夜の月 成美」 とある。
「成美」とは、もちろん夏目成美(せいび)のこと。江戸後期の俳人で、五代目井筒屋八郎衛門という浅草の札差、今日でいう金融業の人でありながら粋人として、また生涯、小林一茶(一茶より十四歳ほど年長)を援助しつづけたことでも知られる。
この『やじうま歳時記』の章扉の「夏はただ昼寝むしろに夜の月」も商人らしからぬ(いや、だからこそか)小ざっぱりした好ましい句だが、さらに「のちの月葡萄の核のくもりかな」「魚くふて口なまぐさし昼の雪」といった、ほのかに優艶ともいえる印象的な句も残している。
いきなり夏見成美に寄り道したが、『やじうま歳時記』の本文を訪ねる。
面白い。たとえば「紅一点」と題する項。「紅一点」という言葉はもちろん誰もが知る日常語だが、その「紅」について語られる。
女性に対してのたとえとされる、その「紅」とは? 紅梅ではなく、バラ? でもなく牡丹、芍薬でもない、
となると︱︱その紅とは、中国宋代の詩人、王安石を引きつつ、柘榴(ざくろ)の花という。
一説にインド、(この場合は印度と書いた方が感じが出るか)、原産とされるザクロ、punica granatumの花は、ご存知のように初めて口紅をぬった乙女の、くちびるのように紅い。
王安石の「詠石榴詩」の、これも知る人多き「万緑叢中紅一点︱︱」が出どころ。この紅き柘榴の花の季語は仲夏。
五月雨にぬれてやあかき花柘榴 野坡
さあ来いと大口明けしざくろかな 一茶
花は夏、実は秋の季語としても、この紹介の二句、ぼくだったら、感じはわかるけど、いや、わかりすぎるから、取りませんね。
「鮎(あゆ)」の項。この字が中国ではナマズを指すことを導入として、話はすぐにアイナメとなる。表記には「鮎魚女」あるいは「鮎並」とされるらしい。
さらに話は横スベリして、アイナメが「魚偏に“69”と表記するのだそうだ」と、不審なことを記している。で、“六九”より「 “69”にしたほうがいいですね」と、おっしゃる。ああ、例のシックス・ナインか、とガクッ! とくる。
この『やじうま歳時記』、“目うろこ”のウンチクが語られると思えば、所々に、かくのごとき色っぽいサービスもある。
気をとりなおして、「名月」の項を見てみよう。ここで掲げられるのは、まず芭蕉の、
名月や池をめぐりて夜もすがら
これに対して、「江國滋氏は、芭蕉でさえこの程度の句しか読めないのか、と慨嘆しておられたが」とあり、「たしかにそうだ。むしろ其角の、
名月や畳の上に松の影
のほうがいい」とおっしゃっている。
う〜む。芭蕉の「名月や〜」の句、当然、“名月を句にするために「夜もすがら」苦吟したと思うのがあたりまえだろう”が、別の考えだってなくはない。
この五七五だけで、他の情報がまったくないとすれば、名月の下、池をめぐって、男と女(もちろん男と男、女と女でもいい)、月の光を浴びながら、何ごとかを語り合い、一晩中、池をめぐり歩いてもいいわけでしょう。つまり、恋の句でもいいわけだ。
ついでに、著者にほめられた其角の句だが「名月や畳の上に松の影」って、ちょっとした浮世絵にありそうな絵柄。それこそ“月並み”じゃありません?
って、ツッコミを入れますが、そんなことまで書きたくなるくらい、この『やじうま歳時記』は読んでいて楽しい。「夏」の部で他の本に移ろうと思っていたのが止められず「秋」の部「名月」から「熱燗」「年惜しむ」といった「冬」の部まで読みつづけ、コロナ下の自室で一日を過ごしてしまった次第。
そうこうしてはいられない、次の『美酒佳肴の歳時記』(森下賢一・一九九一年徳間書店刊)をざっと見よう。

美酒佳肴の歳時記 著:森下賢一
ところが、これが困ったことにまた力作で面白く、じつにためになる。
ぼくの記憶ではこの『美酒佳肴の歳時記』の著者、森下賢一氏とは、二、三度しかお会いしたことがないと思う。ただ少なくとも一回は、よく記憶している。それは、浅草の類さん(吉田)の句会に呼ばれてのことだったから。
もう二回は、それよりも前、たしか誰かのイベントかトークショウか何かの時だったのでは。
もちろん氏の名は存じあげていた。外国文学に通じ、銀座をはじめとして洋酒やBarに精通しているお方。こちらは、居酒屋での安酒と、ちょいとしたアテがあれば満足で、スコッチやカクテルなど、あまり普段は呑まないほうで、いわゆる守備範囲が異なるで、きちんとは話したことがない。
ただ、この森下氏が、いわゆる“洋物文化”ばかりではなく、俳句に対しても関心をもっていて、類さんの誘いではあったにしても、こういう素人中心の句会に顔を出すご仁であることに、意外な感を抱いたことである。類さんの交友範囲の広さ、深さを再認識するとともに、森下氏のフットワークの軽るさを知ることとなった。
その森下氏の「浅く酌み低く唱! 四季折々の酒と肴をうたって今日も酔う」と帯にコピーのある、つまりは“浅酌低唱“『美酒佳肴の歳時記』。
「春の章」から始まるが、本文に入るまえに「あとがき」をのぞいてみたい。まず、冒頭の書き出し、
「歳時記に聞きて冬至のはかりごとーー松本たかし」という句があるが、
歳時記には、たんに俳句の季節の説明や例句が並んでいる、俳人のための
参考書ではなく、日本的なライフ・スタイルのガイドブックのような一面
をあわせもつ。(中略)人生の大きなたのしみである飲食についても、人は
歳時記を読んで、自分がこの人生でまだ見逃している、ひじょうに多くの
飲み物、食べ物や、その飲み方、食べ方、味わい方があることを知ること
ができる。
と、この、酒と肴に特化した歳時記を自己紹介、そして俳聖・芭蕉にも酒の句は多いとしながら、
俳句とは、花鳥風月とか、神社仏閣などを、きれいごとで詠むだけのもの
でなく、酒を飲みながらでも、また、悪酔いしながら、二日酔いに苦しみ
ながらでも、作り、鑑賞出来るものであることを知ってもらえれば、ぼく
として、これ以上に嬉しいことはない。
と、酒飲み俳人ならではの、心強い(?)決意表明をしていらっしゃる。
本文を拾い読みしつつ、夏の「ビール」の項に至る。ここで著者は、ビールについてのうんちく(傍点)を傾ける。日本におけるビールの歴史と、その製法と味の限られた特長。さらに、ベルギー、ドイツ、イギリス、アメリカ、オランダ、さらにメキシコやフィリピン、タイといった世界のビールをガイドする。ちょっとしたビール事典の一項目。(これは歳時記かぁ?)といった力の入れようなのだ。
そして、その後に挙げられる例句の量もまた、特大ジョッキなみにたっぷり。数えてみたら六十二句あった。すべて書きうつす、気持ちも、気力もない。失礼ながら選句するつもりで、これはと思う句に・印をつけてみたら十一句になった。さらにふるい落として六句をえらんでみた。行きます!
やうやくに目処のつきたる麦酒かな 西山 誠
なんの技巧も見せぬようでいて、ビール好きには共感がわく。仕事に区切りがついて、仲間とでも、ひとりだとしても、「お疲れさま!」と杯をほす。こういう一見、素直な句を作るのは力量がいる。
ビールほろ苦し女傑になりきれず 桂信子
ビールと「女傑になりきれず」の妙。
大ジョッキ奢りし方が早く酔ふ 田川飛旅子
川柳風味のユーモアというか、なるほど! という“うがち”がある。俳号の「飛旅子」は本名の「博」から。
ビール酌む共に女の幸知らず 風間ゆき
ほろ苦い味の句だが、「共に」と一人ぎめしてよかったのだろうか? ことによると相手の女性は密かに「幸」あったりして。
生ビール運ぶ蝶ネクタイ曲げて 池田秀水
いかにも繁盛しているビアホールの一景。黒い蝶ネクタイを見るだけで、ビールが1・5倍は美味くなる。ビアホールの句では「天井が高くて古きビヤホール」も捨てがたかった。二句とも銀座七丁目の「ライオン」を思い出させてくれます。
うそばかりいふ男らとビール飲む 岡本眸
この句は、どこで見たのか、前から知っていて、ぼくのメモでは「嘘ばかりつく男らとビール飲む」とある。まあ、どちらにせよ、慣れた技巧で作ろうとして作れる句ではない。「男ら」と複数型が効いていますね。しかも、作者の世間智というか、したたかな社会的経験をうかがわせる。「男ら」は彼女に見すかされています。
と、ビール六句中、三句が女性の句だったのに、自分でもちょっとびっくり。森下氏の挙げた六十四句の中には、石田波郷、大野林火、久保田万太郎、山口誓子、石原八束、石塚友二、山口青邨、石川桂郎、楠本憲吉、富安風生、日野草城、平畑静塔等々、錚々たる俳人の名がならぶが、ぼくの選んだのは以上の六句でした。日本酒ならともかく、ビールはあまり好みじゃないのでは? という句や、ビールの、その世界を避けての苦しい句も見られ、なかなか興味深かった。
ビールという、あまりに身近かでイメージがかなり定着してしまっている題は、取り組みやすいようで、意外と難しいのかもしれない。一度、自分も参加している仲間うち句会の兼題で出してみようかな。
もう一つ二つ夏の季語から見てみよう。
「蛍」。
先日、仕事部屋近くの小さな酒場で、「蛍狩りをしてきた」というママの話を聞いて「えっ、もう蛍が出るの?」聞いてしまった。ぼくの、旅先での記憶やイメージでは、梅雨時のいまごろではなく、夏休みの真夏の頃のはずだった。
ところが、ママの話によると、この時期に見られるのは、大型のゲンジボタル。その一カ月ほどあとあたりから初秋頃まで飛んでいるのが小型のヘイケボタルという。ホタルに二種の名があることは知っていたが、出る時期や大きさが違うとは、このとき初めて知った。
森下氏の解説にも、もちろん、このことはもっとくわしくふれられている。九月の末の頃まで生きているヘイケボタルは「秋の虫」ともいうらしい。
このあと、夜の銀座通りの森下氏ならではの一行。
今も銀座に出る虫売りは、秋の虫に先立ち、六月にホタルを売る。
と記す。はたして、最近も銀座ではホタルは売っているのだろうか。ちなみにこの本は一九九一年に刊行されている。いまから二〇年ほど前だ。
それはともかく森下氏、「蛍」で六句を例句としている。句だけ転記する。
ほたる見や船頭酔ておぼつかな 芭蕉
蛍火やある夜女は深酔いし 鈴木真砂女
蛍籠酔ひたる父の息かかる 新谷瑠璃
蛍の川酔いのこる脚ひたしけり 後藤隆介
蛍狩一火もみずに酔ひにけり 藤中 和
蛍飛ぶ酔ひたる闇の旅路かな 遠藤帆碗
なるほどなぁ。こう書きうつしていると、蛍と酔うは、よく似合う。
夏の季語で「万太郎忌」も「桜桃忌」も挙げられている。例句についてひと言ふたこと言い添えたいが、きりもないので、毛色の変わったところで七月十四日、「パリ祭」。
ここでも、パリ祭についての解説の後半、銀座の話が出てくる。
戦前のパリを知る芸術家や、パリに憧れるインテリなどが、パリ祭と称し
て、銀座などの酒場で騒いだり、クラブやキャバレーが客寄せのイベント
として「パリ祭」を行ったりした。
「汝が胸の谷間の汗や巴里祭 楠本憲吉」は、酒場の冷房の性能もイマイ
チだったその頃の、その日本版パリ祭を詠んだ憲吉畢生の名作。
と楠本氏の句を絶賛。
例句は次の二句。
巴里祭の灯を背に酔語らちもなし 志摩芳次郎
酔えば唄う一曲ありぬ巴里祭 河野閑子
いやぁ、いまでもいるんですよ。パリ祭という言葉を聞いたら、すぐにシャンソンの、二、三曲を大声で唄う、横浜出身、船旅好きの元編集者の友人が。「浅酌低唱」にあらず「深酌暴唱」。彼の前で「パリ祭」「ナポリ」「ファド」という言葉は禁句です。
パリ大学で学び、銀座と酒と俳句に親しんだ森下氏は、2013年、八十一歳で亡くなりました。もっとお話をうかがっておけばよかった。


