季語道楽(40)隠れ歳時記の自在さ−3 坂崎重盛

タイトルに歳時記とは銘打ってないものの、なんとなく入手していた俳句本を、手にしてページを開いたら、実際の構成は、歳時記だったりする。今回はまず、森澄雄編『名句鑑賞事典』(一九八五年・三省堂)を見てみよう。

名句鑑賞辞典 歳時記の心を知る 編:森 澄雄
新書版より、わずか大ぶりでソフトカバー、本文、294ページのハンディな本ながら、ぼくは机の一隅に置いて、なにかと、事あるごとに手にしてきた。
タイトルは『名句鑑賞事典』ではあるが、カバーに「歳時記の心を知る」とある。目次を開けば一目瞭然、「春・夏・秋・冬.新年」と、歳時記そのものの構成。
巻頭は、編者・森澄雄のことばとして「名句を読む」。芭蕉の
春なれや名もなき山の薄霞
旅寝して見しやうき世の煤払ひ
の二句を挙げ、その解釈、諸説はあったとしても“自分が、その句から何を、どう受け取るか”ということの大切さを訴えている。
「名句は、意味だけでなく、いい果(おお)せない豊かな表情を持つ」とし、「故に名句、おのおのの心でよみとることも、名句を読む必須の心がまえであろう」と説いている。
つまり、名句への接し方は、単にその句の意味するところ、解釈・鑑賞だけではなく、その句から、自分の心に生じる思いを大切にすることが「名句を読む」心がまえではないだろうか、と記している。
つづけて、本書の構成と季語・季題の重要性について、さらっとふれられている。引用する。
本書は主要季題四〇〇を選んで、その代表の一句に鑑賞を付し、さらに
例句をあげた。季題は単なる季物であるばかりではなく季節感であり、さ
らに一句が一句の世界をもつ重要な要素である。
︱︱と。そして巻末には付録として「俳諧の歴史」「俳句の歴史」俳人百余人の紹介、年表、とさすがに三省堂、実に親切でゆきとどいた本づくりがされている。ヘタな専門書、学術書を編集するより、こういう入門書を作ることのほうが、編集者の力量が要求される。
本文を見る。それも、もっとも初学の人が「えっ?」と思う、定番の季語かの句から拾ってみよう。まず「麦の秋」、いわゆる「麦秋(ばくしゅう)」ですね。俳句に無縁な人は「麦秋」という文字を見たら秋の文字が入っているので、当然、秋をイメージするでしょう。ところが「麦秋」とは、麦の刈り入れ時。つまり初夏なのである。
鑑賞の句は、
麦秋(ばくしゅう)の中なるが悲し聖廃墟(せいはいきょ) 水 原秋桜子(みずはらしゅうおうし)
作者が原爆投下を受けた七年後、長崎の浦上天主堂を訪れた時の句。そのころはまだ、天主堂跡には、崩れた煉瓦や天使の像などがころがっていたという。周囲は折から黄色に穂が染まる麦の熟す時期で、物悲しい廃墟と、盛りの麦の色と香のコントラストが俳人の心をとらえた。静謐で、心にしみる鎮魂の一句。
もうひとつ、これも初歩の初歩「夜の秋」。夏の終わり、夜になると秋の気配を思わせる時節もちろん夏も晩夏の季語。素人句会の座であっても、「秋の夜」と混同すると恥ずかしい。ここで挙げられる句は、とても印象的で、一度接したら忘れられない。女人の作る句には、ときどき、こういう傑作がある。
西鶴(さいかく)の女みな死ぬ夜の秋 長谷川かな女(じょ)
解釈は略そう。例句が四句付されているが、そのうちの二句だけ紹介して、次の“隠れ歳時記”移りたい。
家かげをゆく人ほそき夜の秋 臼田亜浪
吊り皮を両手でつかみ夜の秋 原田種茅(たねじ)
俳句関連書を精力的に執筆している朝日俳壇選者・長谷川櫂の『日めくり 四季のうた』(二〇一〇年・中公新書)がある。これは「読売新聞」に毎朝、一つずつ句や歌や詩など取り上げ紹介したものを版元の編集部が選択、構成。いわば読売版「折々のうた」か。
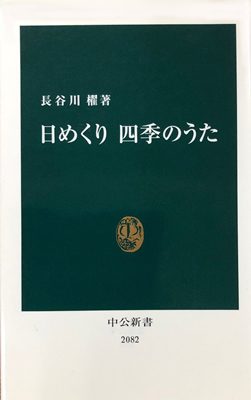
日めくり 四季のうた 著:長谷川 櫂
これもまた歳時記本の一冊だが、四季どころか、タイトルにあるように“日めくり”、つまり一月一日の元日から十二月三十一日の大晦日までの日付ごとに詩歌句が挙げられている。
二日前、コロナ騒動下、うっとうしい長い梅雨が終わり、梅雨明け宣言されたのが、ほんの二日前。例年よりも十一日遅い梅雨明けとかで、この書の「八月五日」は一茶の句、
月かげや夜も水売る日本橋
ここでの水はただの水ではないことが解説される「白玉を入れ、砂糖で味がつけてあった。江戸ではこれを冷や水と呼んで売り歩いた」とある。そして、この一茶の句について「夜風の立ちこめるころ、月光を浴びた水売りの影法師が見える」と説く。
次の「六日」は、旧暦の七夕とあって、
天(あま)の河(かわ)浅瀬しらなみたどりつつ
渡りはてねば明けぞしにける
と紀友則の歌を紹介。
「七日」は、
稲光(いなびかり)男ばっかり涼む也(なり)
という『柳多留』の川柳を取り上げる。「ばっかり」というあたりが、いかにも俗を旨とした川柳。稲光がして雷の音が近づけば、それまで夕涼みしていた女性や子供たちは、あわてて家の中に避難してしまう、しかし、そこは男性、雷ごときにバタバタできるかと見栄を張って、なにごともないかのように夕涼みをつづけている。故に「男ばっかり」となる。
ちなみに、「雷」の季語は夏だが、「稲妻」は秋、稲妻が秋の季語なのは、稲妻の電光が稲を実らせると考えられていたからという。農耕と季語の深い関係をうかがわせる。
一日一話、枕辺において、寝入る前に開いているうちに、日本の豊穣なる詩歌の世界に招き入れられる心地がする。
さて、このタイトルの本も歳時記? 高橋治『くさぐさの花』(一九九〇年 朝日文庫)。これが新年から冬まで、四季折々、著者が出会った草花について、それに関わる句を紹介しつつ、作者の思いをつづる。

くさぐさの花 著:高橋 治 写真:冨成忠夫
内容は、いわゆる草花の歳時記なのだが、並の歳時記との差は、さすがに鋭い感性を持ち、それを表現することに心をくだいてきた作家ならではの、一話一話が物語として構成されている。
まず、作者による「あとがき」を見る。この小さな書への作者の思いを知ることができるからだ。
どうやら、著者と俳句(俳諧)と草花に対する愛は、半端ではないようだ。
径二十センチもありそうな山つつじをばっさり切って、ホテルのロビーに生ける花道の家元たちの所業に、
「テメエの命とこの花の命と、地球にとってはどっちが大事だとおもって
るんだ」と叫びだしたくなったとする。
と、強烈なタンカを切っている。
この朝日文庫『くさぐさの花』を著した直木賞作家・高橋治は、東大国文科で近世文学を専攻、卒論のテーマに天明俳諧史を選んだ、とこの書の「あとがき」にある。
天明の俳諧といえば、芭蕉死後、宝井其角を代表とする江戸座の粋や通を喜ぶ遊戯的俳風、また各務支考(かがみしこう)らによる美濃派や、伊勢俳壇の伊勢派といった、ともすれば通俗に流れると言ってよい傾向に対し、“芭蕉に帰れ”という蕉風復興の気運のなか、大島蓼太(りょうた)、加舎白雄(かやしらお)、加藤暁台(きょうたい)、与謝蕪村らが主な俳人として挙げられる。
高橋治、この天明の俳諧史を卒論のテーマにしたというのだから、俳句への思いは一入(ひとしお)だろう。ましてや、この作家“花狂い”(はなぐるい)と自白しているのだから、もう花の歳時記を編むには適任の人である。
また、このハンディな文庫のありがたいところは、その植物写真のリアルでしかも美しいことである。植物写真は、よい条件の草木を、きちんとピントを合わせて撮ればいいだろうと思われるかもしれないが、そんなものではない。
ぼくも多くの植物図鑑を持っているが、そこで掲載されている植物の写真によって、現実の植物を同定するのはむずかしいことが多い。植物はそれこそ、個体差があり、“枝葉末節”で、それぞれ微妙に色や形を変えることが珍しくないし、また撮る側のアングルや接写の距離によって多様に見えてしまうからだ。
『くさぐさの花』の写真家は冨成忠夫。もともとは美校(現・東京芸大)の油画科を卒業、自由美術家協会の会員として公募展に出品する洋画家であったというが、画筆をカメラに持ちかえて、植物写真家として名を成す。(なるほど、対象物をじっと見つめ、細部まで描くように写真を撮ったのか)とぼくは一人合点する。
“花狂い”の高橋治と植物写真のジャンルを確立した冨成忠夫のコラボによる『くさぐさの花』、内容を見てみよう。
「夏」の章で「カンナ」、冒頭は次の一句。
夏痩せて嫌ひなものは嫌ひなり 三橋鷹女
千葉県成田の人。この句、新羅万象我慢ならぬことには、敢然と立ち向
かう心意気と読める。(中略)
気性の烈しい女性を見ると私はカンナを思い出すが、花言葉に情熱、堅
実な生き方とある。まさに千葉産の女である。そのせいではないだろうが、
鷹女にはカンナの秀句が多い。
ちなみに著者・高橋治も千葉県の出身。“千葉産”の女、三橋鷹女の写真を見ると、平成、令和の時代では見かけない、ぞくっとするほどの、細面の美人である。
この本ではカンナは夏の章に出てくるが季語としては秋。
もうひとつ行ってみよう。「朝顔」。
朝顔に島原ものの茶の湯かな
上田無腸、別号秋成、『雨月物語』の作者である。句からは仕事はうかが
えないが、廓(くるわ)の出という艶っぽさを花と茶の澄明感に添えてい
る。さすがは短編の名手の作。
朝顔は江戸(とくに末期)おびただしいほどの園芸新種が栽培される。それにしても、茶の湯に、朝顔の取り合わせがモダンではないか。この本で、著者がたびたび引用する森川許六の『百花譜』では、と。
『百花譜』の雑言。病気がちの美女が、夏の間も月の中二十日ほど頭痛鉢
巻で寝ていたところ、たまたま快晴で気分がよかったのか、薄化粧で姿を
見せたような花だ。持って廻っているが“いえている”ではないか。
と許六の“雑言”を喜んでいる。ここでいう、洒落に飛んだ、持って廻った“見立て”は、今日でも落語家の腕の見せどころでもあります。ところで朝顔の季語は、よく知られるように「秋」。
「くさぐさの花」、高橋治の四季折々の花随筆、そして、巻末の宮尾登美子による解説「一花一花に情い情調」でも記されているように「終わりに、写真が非常に正確でかつみずみずしく、思わず手をのばして触れたくなるような美しさ」という感想も、あらためて同感で、幾度も手に取りたくなる一冊である。
草木の歳時記、また季寄せは、数多く出版されているが、僕の記憶では、一番最初に手にしたのは、いまはない、社会思想社・現代教養文庫の松田修著『花の歳時記』であったと思う。大学の園芸学部、造園学科に入り、少しは草花のことも知っておかなければ、と思ったのだろう。

花の歳時記 著:松田 修
このころ、和歌はもちろん、俳句にも、ほとんど興味はなかった。江戸ものといえば。すでに宮尾しげをの川柳や江戸小咄し本、あるいは三田村鳶魚や正岡容の本は手にしていたものの、このころ、江戸東京懐古への憧れから一転、二十五人しかいない学科の中でもモダンジャズのコンポを結成しようと無謀な行動を始めていたからだ。
とはいえ、庭や植物のことは自分で選んだコースでもあり、興味や関心は抱き続けていた。松田修『花の歳時記』は、そんな学生時代に入手したはず。
ところが、この本を今回、久しぶりに手にして、奥付をチェックすると、初版は三十九年だが五十三年十一刷とある。五十三年なら三十六歳である。そうか! と思った。本文、ほとんどマーカーの跡もないし、フセンも四カ所歯科挟んでいない。つまり、この『花の歳時記』は、ぼくにとって後で改めて買った二代目だったのか。
と、まぁ、他人にとってはどうでもいいようなエピソードが、本と人との関係には生じる。
「はしがき」の宣言がいい。
「花の歳時記」は、和歌、俳句、詩、文学書、古典などをよむ人のため
解説した日本で初めての植物文学事典です。
「日本で初めての植物文学事典です」が堂々として気持ちいい。文庫本本文418頁、索引32頁のボリュームで収録されている植物の数一二五七。著者は1903年山形県生まれ。東京大学農学部卒。植物、とくに花に関する本を多く著している。
この本を手にして、ラインを引いた部分を見る。「アシビ」の項「この葉を食べると足がしびれるという」に赤線が引かれている。馬が食べると酔っぱらったようになるとか、馬酔木(あしび)。ちなみに、この「アシビ」(アセボともいう)では「吾が背子に吾が恋ふらくは奥山の馬酔木の花の今盛りなり」(万葉集・巻一〇)が挙げられている。
「イタドリ(虎杖)」にもラインがある。築地の場外に、この名の寿司屋があって使い勝手がよく好きな店だった。築地の移転問題があってから、足が遠のいているが健在だろうか。それはともかく「虎杖」とも書いて「イタドリ」。由来はさまざまな説があるようだが、何か嬉しい漢字であり、和名である。紹介五句の中でラインが引かれているのが「虎杖の軒に出てをる芸者かな」(富安風生)の一句。今なら「虎杖や見上げて通る切り通し」(柏若)にもラインを引くだろう。
頁を繰っていくと切りもない。とくに昔手に入れて、ずっと本棚の片隅に置かれていた本を久しぶりに手にすると、寝ころびながらずっと頁をめくっていたい。しかし、先を急がねば。
ぼくの本棚に、写真をふんだんに掲載しての文庫判、全七巻の歳時記がある。朝日新聞社刊『吟行版 季寄せ草木花』。“吟行版”と銘打ったのは文庫判でハンディな本づくりをアピールする、ためだろう。七冊のうちの、夏[上]を手にする。〈選・監修〉中村草田男、〈写真〉冨成忠夫、〈解説〉本田正次。説得力のあるチーム編成。ここでも写真は冨成忠夫。この写真歳時記シリーズの特色はなにより植物学者に本田正次による解説。植物には、もともと中国由来の漢名、また、日本各地の異名、同名でありながら、まったくの異種があったりするが、これらについて丁寧にふれられている。
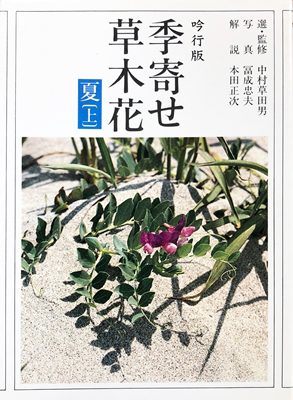
吟行版 季寄せ草木花 夏(上) 選・監修:中村草田男 写真:冨成忠夫 解説:本田正次
選の監修の中村草田男は、東大国文科の学生時代から虚子の「ホトトギス」に関わり、戦後昭和二十一年「萬緑」を創刊。この「萬緑」とはもちろん、
萬緑の中や吾子の歯生えそむる
から。この草田男の句で万緑が新たな季語として誕生する。一つの名句によって季語が生まれるという、有名な例の一つ。
もうひとつ草田男には、
降る雪や明治は遠くなりにけり
という、俳句をたしなまない人でも、よく知る代表句がある。ぼくなんかは、(まるで久保田万太郎の句みたいな)と思ってしまう。その作者が、この『季寄せ草木花』の巻末に「現代俳句と季語及び写生」という一文を寄せている。これが美しい写真を添えた一般読者のための植物歳時記には、ふさわしからぬ? 近代短歌と俳句に関わる評論であり、現代俳句への、厳しい提言となっている。
今日でも容易に入手できるものなので、関心のある人は、この文庫を入手してもらいたいが、ただ、結びに近い文章から引いておく。
現在の俳句界も、明治から百年を経て、あらたなる教養主義
に分解、分散化しているように思う。求道ゆえの偏りや硬直な
どを無くしてしまい、うぶうぶしいシロウト臭さなども無くし
てしまい、洗練された芸人(アー チザン)がお互いに肩を
叩いて、その教養を誇り合って楽しむ、いわゆる「かるみ」の
世界になってきたように思う。
││この一節、なんか、この俳人に叱られているような気になってくる。マジだ。草田男は国文科の前は、もともと独逸文学科に入学、終戦後、あの桑原武夫による「俳句第二芸術論」が出たとき、堂々と正面切って反論したのはこの草田男という。
解説は││先の文章に続く次の三行で、この「解説」は言い終わっている。
そういうことであってはならず、文学を第一義的ないのち(傍
点)の道だと考え、「自然・自己一元の上に」絶対的なものを求
めて、まかり間違ったら死んでもいいという気持ちでいきたい
と思う。
桑原の「第二芸術論」への怒りが、あれから三十年以上たっても収まらぬか、あるいはまた、現代俳句に対する安易な姿勢を叱咤激励せずにはおれなかったか。この求道精神というか純度の高い情熱には、ぼくなど首をすくめてしまうが、貴重な提言だ。
なお、この『吟行版 季寄せ 草木花』は「春」(上・下)は山口誓子、「夏」(上・下)中村草田男、「秋」(上・下)は加藤楸邨、「冬」(上・下)は山口誓子の選・監修による。
植物写真をふんだんに使っての歳時記といえば、いま俳句界で一番よく知られた人、あの夏井いつき先生が「この図鑑で、名も知らぬ植物が『出会いたい』季語に変わる!」と帯で推薦する『俳句でつかう季語の植物図鑑』(遠藤若狭男[監修]2019年・山川出版者刊)がある。

俳句でつかう季語の植物図鑑 監修:遠藤若狭男 編:『俳句でつかう季語の植物図鑑』編集委員会
ページを開くと、すぐにこの図鑑歳時記の使勝手の良さが伝わってくる。草木一種(見出し季語)が一ページか半ページに収められ、季語の下に傍題と、その読み、植物の種類、花期、名前の由来などがとても読みやすくレイアウトされている。
監修者の遠藤若狭男は鷹羽狩行に師事、『狩』同人、多くの句集や俳句評論集を持つ。例句は、主に現代俳句が多く、初心の人にも理解されやすい句を選んだ配慮がうかがえる。
また、いわゆる文人俳句も取り上げられ、たとえば、ぼくが敬愛する室生犀星の句が取り上げられたりして、つい嬉しくなる。たとえば「菫」(すみれ)の季題では、
うすぐもり都のすみれ咲きにけり
あるいは「桜桃の花」(おうとうのはな)では、
さくらごは二つつながり居りにけり
と、平明な句風。そういえば犀星の代表作は「杏っ子」であり、『庭をつくる人』というタイトルの随筆集がある。また、薄っぺらい造本の『犀星発句集』も入手にしているが、いま手元に見当たらない。ぼくのなかで犀星の句といったら、まずは、「あんずあまそうなひとはねむそうな」である。とにかく、犀星は植物、庭、そして俳句には縁、浅からぬ文人なのだ。
ところで監修者自身の例句に接して、ぼくはちょっとした“邪推”をしてしまった。季語は「薔薇」(ばら)、若狭男の例句は、
薔薇圓のすべての薔薇を捧げたし
││うーむ、この句は漱石の、
あるほどの菊投げ入れよ棺の中
を、思い起こしてしまう。よく知られるように、この句は親交の深かった美貌の女流歌人・大塚楠緒子(くすおこ)が三十五歳で亡くなったときの追悼句。
さらに連想と言えば、この句はまた、加藤登紀子が歌った「百万本のバラ」も頭に浮かんでしまう。
といったことなどに心が遊ぶのも、この季語図鑑の編集が見ていて、とても快いからではないだろうか。
ここで取り上げられる草木、約400種、季語約1400というのだから、存分にありがたい。俳句に親しむ人はもちろん、日本の植物とそれに関わる言葉に関心のある人のためのビジュアルなガイドブックでもある。

