季語道楽(43)いよいよ「季寄せ」「歳時記」本の本丸へ① 坂崎重盛

吟行などの携帯のための「季寄せ」は後でふれるとして、いわゆる「歳時記」本(歳時記的事典や辞典も含めて)には、本造りの形として、大きく分けて二種類ある。
一巻完結編集もの(仮に単巻歳時記、単巻本と呼ぶことにする)と、われわれがよく目にして入手、利用する文庫版によるような「春・夏・秋・冬」の四冊型と、それに「新年」が加えられての五冊型である。(これを、複刊歳時記、複刊本と呼ぶこととしよう)
と、いうことで、まずは単巻歳時記から見てみることにする。手元の各種歳時記関連本のなかから単巻歳時記を抜き出し並べてみた。ざっと二十一冊ある。ページ数でいえば千二百ページを超えるものから、もっとも薄い歳時記でも三百ページ近く。仮に平均五〇〇ページとしても一万ページ。もちろん全巻読破、などという無謀にして酔狂なことはしない。いやできないし、意味もない。
ただ、この際、一巻一巻わが手に取って、ページをめくり、ぼくの関心のある個所や掲げられている例句をチェックしていきたい。
まずは四六判でドカンと分厚い単巻本から。
- 石田波郷・嶋芳次郎 共編『新訂現代俳句歳時記』(一九八八年 主婦と生
活社/全1216頁)
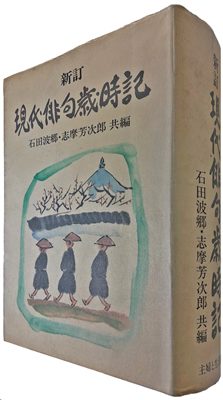
新訂 現代俳句歳時記 石田波郷・志摩芳次郎 共編

新訂 現代俳句歳時記 石田波郷・志摩芳次郎 共編
『広辞苑よりは、ちょっと判も小さく、重さも少し軽い。しかし手にしていると、つらくなる重さだ。机上に置いてチェック。この、分厚い歳時記本のカバー絵や扉絵が、なんとも洒脱で軽みのあるイラストレーション。戦後、政治家の似顔絵で人気を博した文人的漫画家・那須良輔の禅味のあふれた画である。
本文を見てみよう。じつは、ぼくは各種歳時記の「序文」や「あとがき」を読みたいがために、あれこれ入手してきたフシがある。
この際時記の序文は加藤楸邨による「二人の友人のこと——新訂版の序にかへて」と題する一文。書き出し二行目から、引用する。
実は私は序文は書かないことにしてゐるので、今度も辞退したのだが、
社と志摩(注・芳次郎)君の方から強っての話だったので、今は亡き波郷
(注・石田)との永い交流も考へた上、序文といふやうなあらたまったも
のではなく、両君との間の気楽な気持ちでの随想とでもいったらよいやう
な小文をかかせてもらふことにした。
と、歳時記の「序文」というよりは、年長の加藤楸邨と、この歳時記編者の石田波郷・志摩芳次郎の思い出というか、楸邨以下、三者の交流の逸話を紹介している。これはこれで興味深いが、しかし『歳時記』らしい序は、次の波郷による「初版のはしがき(抄)」にある。
俳句は自然と生活との調和の上に成立する詩だと言う考え方は、もっと
も広く認められている。
と、この一文は書き出されている。
先の明治三十八年生まれの楸邨の文と大正2年生まれの波郷の文章の差に気づかされる。楸邨の文は旧仮名づかいに対し、波郷は、今日の文のように新仮名である。ただ、波郷の文は昭和三十八年記。
楸邨の文は、それから二十五年もたっての昭和六十三年の記なのだ。旧い文体と今日の文体が時間的ネジレ現象を起こしている。時流は変わっても、易々と新仮名に移行しない楸邨の人柄がうかがえて興味深い。
ま、そんなことはともかく、波郷の「季語」に対する考えを見てみよう。引用する。
季語として採択されるには、次の三つの条件を備えていなければならない。
イ、季節感があること ロ、普遍性があること ハ、詩語としてすぐ
れていること
とし、
洗練され安定した季語たるには、厳しい選択の目をくぐらねばならないの
である。長い歴史を持つ季語は三条件をそなえ、万人の深い共感を呼ぶの
である。
と定言する。そして歳時記が「俳人だけのものでなく」「私たち日本人の伝統的な生活史を背負って、豊かな遺産の宝庫であるという意味こそは大きい」と語り、「その意味では、むしろ高校生位の若い世代から歳時記に親しんでほしい」と望んでいる。波郷による、平易でまっとうな、初学の人向けの序文といえる。
「あとがき」は波郷より五歳ほど年上でありながら波郷に傾倒した志摩芳次郎による。はじめに、共編者であり、師であり、この新訂刊行時には、すでに世を去っている波郷へのあいさつがあり、結語近くでは、一文の結びで俳句歳時記への思いを強い言葉で訴える。
俳句に携わる携わらないにかかわらず、俳句歳時記は国民必読の書であ
ると叫びたい。それゆえ、本歳時記が数おおくの人びとの座右の書となる
なることを望む。日本および日本人がほろびないためにも。
と。
本文を見てみよう。例によって、この原稿を書いている正月、新春の季語で気になるものを眼で追ってゆく。「食積(くひつみ)」、「礼者(れいじゃ)」、「寝積(いねつ)む」といった、ほぼ死語に近い季語に目が止まる。
まず「食積」は正月料理を詰め合わせたもの。今日風に言うと「おせち」。例句に、
食積みに添えたる箸も輪島塗 上野たかし
食積の蒔絵の塗りに映える顔 會津龍之
食積の黒豆だけがのこりけり 本土みよ治
「礼者」は三か日の「年賀客」。新年のあいさつだけを玄関先からして辞するのを「門礼者(かどれいじゃ)」、また、女性の年賀の客を「女礼者(おんなれいじゃ)」といい、花柳界の芸妓の新年のあいさつまわりも含まれる。
病床をかこむ礼者や五六人 正岡子規
一門の女礼者や屋にあふれ 石田波郷
「寝積む」。「元旦に寝ること」。昔、正月は縁起をかついで、病気で寝込むことを連想する寝(いね)という言葉をきらって、「寝(いね)」が稲と同音であることから「稲積む」としたという。今日、ほとんど死語。
寝積や布団の上の紋どころ 阿波野青畝
寝積や煙草火つくり独言 角川源義
この「寝積」=「稲積む」の季語に少し興味を持ったので、すでに紹介した夏井いつき先生の『絶滅寸前季語辞典』にあたってみる。「稲積む」でありました。
「秋の季語だと勘違いする人が九割いても不思議ではない」「収穫した尾根を積み上げていくさま」と思ってしまうからと説明したあとで、「このところ稲積み損ねてばかりいるせいか」という夏井先生の愚痴的(というか、当たりちらし的自句を例として挙げている。
稲積みたしかれこれ二十時間ほど
二十時間も稲積みますかぁ。しかし、夏井先生の句にはユーモアがあるなぁ。
次の単巻歳時記にうつろう。
- 山本健吉『基本季語五〇〇選』(一九八九年 講談社学術文庫/全千二十頁)
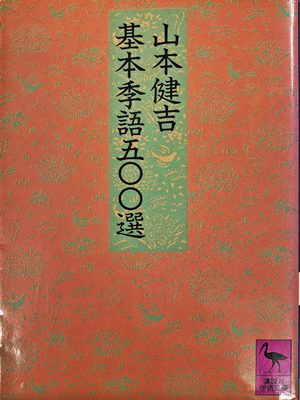
基本季語五〇〇選 著:山本健吉
文庫本という判型と基本季語五〇〇 というタイトルのためか、この季語集がいつも本棚で目にしていながら千頁を超える大著とは、とくに意識していなかった。考えてみれば季語五〇〇だって相当の数だ。紹介されている例句を見れば、少なくても平均二〇句、いや平均三〇句はあるか、仮に二〇句としても、一万句だ。
著者・山本健吉は和歌や俳句といった短詩系文学に少しでも関心を持つ人ならば、親しい著述家で、著書の一冊や二冊は書棚にあるだろう。とくに俳句歳時記、季語の成立に対する考察は説得力があり、今日も一つの定説の位置を得ている。
本書を開く。「序」や「まえがき」「凡例」の類いはなく、いきなり「春」の季語から始まる。しかし、例によってぼくは、この原稿を書いている新年・新春のページから、とりあげられている季語と例句をちぇっくすることに。
ところが、新年の章は季語が「新年」、「初春」、「去年」、「初日」、「初風」、「初富士」、「若水」、「初詣」などと、当然のことながら、あまりに伝統的な季語が並び、少々、新鮮みに乏しい。
では、ということで、少し先の「初春」の章をチェックする。最初に登場するのが「春浅し(はるあさし)」。傍題、つまり関連季語として「浅き春」、「浅春(せんしゅん)」が示されている。解説文の一例を見てみたい。引用する。
二月ころ、春になってもまだ寒く、春色なを十分にはととのわぬ季節
である。
季語としてはある新鮮な語感があり、江戸時代には見かけない季語だ
った。(中略)子規派で初めて季語として立てられたのだろう。
と碧梧桐(河東碧梧桐)や鬼骨(?)の句が紹介され、さらに『新撰朗詠集』からの白楽天の詩が引用され、俳句の季語としては比較的新しいものの、
詩語や短歌には古くから意識されたとしている。そして、解説の〆(しめ)は、
早春、初春(しょしゅん)とほぼ同じ時期を現すが、「浅し」と言った
ところに、特殊な感情が籠る。
と、季語とそれ以前の詩語の関係に心を配りつつ、親切で香気のある文で解説される。例句は十三句挙げられ、山本健吉による歳時記や伝統の詩歌解説書が多くの読者を獲得したのも得心がゆく。
つづく季語は「冴返る(さえかえる・さえかへる)。傍題は「冱返る(いてかえる)」・「しみ返る」・「しみ返る」・「寒返る(かんかえる)」・「寒もどり」。
解説は、この「冴返る」の類似した季語として「冴ゆる」を挙げる。ところが、こちらは冬の季語で、
「光、光沢、色、音響、寒気などが澄みとおることで、そこから転じて
頭脳や面貌やわざのあざやかさなどにも言う。冬の季語とされているの
は、特にあざやかな寒気や冷気について言ったので、光や色や音につい
て言う場合も、冷たさが伴っている。
とし、対し「冴返る」は、
春になって、いったんゆるんだ換気が、寒波の影響でまたぶりかえすこ
とがある。余寒、春寒を意味する。
と解き、ここでも和歌の藤原家隆や藤原為家の歌を紹介と、時代は下って、連歌の時代には一月(初春)のもの、あるいは二月あたりまで季題とされたと記されている。例句は、こちらも少なく十八句。うち、
神鳴や一むら雨のさえかえり 去来
三日月は反(そ)るぞ寒さは冴返る 一茶
衰へし命を張れば冴返る 草城
冴え返る面魂(つらだましい)は誰にありや 草田男
といった句が目にとまったが、中でもぼくが面白いと思った句は、楸邨の、
冴え返るもののひとつに夜の鼻
であった。「夜の鼻」とくるかぁ、と脱帽した次第。掲げられている例句の中から勝手に自分で選句遊びをするのも歳時記を読む楽しみのひとつ。
寒中から早春にかけての季語「猫の恋」も人気のある季題で、素人句会でもよく題として出される。解説では、
生活の上ではきわめて親しい季題でよく、和歌、連歌では、このような
卑俗な世界は忌避(きひ)されていた。(中略)「妻恋う鹿」が和歌の題、
「猿の声」が詩の題、「猫の恋」が俳諧の題と、それぞれのジャンルの特
質を見せている。
と、これまた季題の歴史をふまえた、ありがたい解説。掲げられている例句は二十四句。
寝て起て大欠(あくび)して猫の恋 一茶
色町(いろまち)や真昼ひそかに猫の恋 荷風
恋猫の身も世もあらず啼きにけり 敦(安住)
という句が目にとまったが、耕衣(永田)の有名な、
恋猫の恋する猫で押し通す
が、やはり脱帽。また「木場」として春樹(角川)の、
恋猫や蕎麦屋に酒と木遣節(きやりぶし)
も、下町の気配が横溢していて、うれしい句である。
「白魚」も、この季節の題で、解説も例句も心ひかれるが、キリもないのでこのくらいにして、「あとがき」をさっとチェックして、次の歳時記本に移りたい。しかし、じつは、この山本健吉による「あとがき」季語の成立にとっての重要な姿が浮かび上がってくる。
「あとがき」より。
私は前に、季語の集積が形作る秩序の世界をピラミッドに喩えたこと
がある。頂点に座を占めるのは、いわゆる五個の景物(花・月・雪・時
鳥・紅葉)であり、それから順次に、和歌の題・連歌の季題、俳句の季
語と、下降しながら拡がってゆく。これだけで数千項目が数えられるが、
それらは日本の風土の客観的認識を目ざしたものであることはもちろん
ながら、それに止まらず、それは日本人の美意識の選択であり、しばし
ば美意識が客観的認識に優先することがあるということだ。
と説き、また
季語を季題と化すものは、ある作者によって名句が詠まれたかどうか(傍
点、坂崎)ということで、芭蕉が新しい季の詞の一つも見出すのは後世
へのよき冥加と言ったのは、新しい季題で人の口に上るほどの名句を一
句でも作り出すのだ。
と芭蕉の言葉をひきつつ、新しい季語誕生の消息について語り、つづけて、
そのときそれは、新しい季題として正式に登録される(傍点、坂崎)の
であって、近代
の例では、「夜の秋」「万緑」「春一番」「釣瓶落とし」「乗込鮒(のっこみ
ぶな)」その他、幾つかの例が挙げられるはずだ。
としている。この中の「夜の秋」は、秋の季節とする説もないわけでもなかったが、いまや(というか原石鼎の「粥すする杣が塀の腑(ふ)や夜の秋」を虚子が夏の句と定めたことによって)、好もしい夏の季語として定着したようだ。例句三十二句のうち石鼎の句は当然として、
手花火の香の沁(しむ)ばかり夜の秋 汀女
簪屋(かざしや)と向きあふ小寄席(よせ)や夜の秋 寒々(?)
海わたる魂ひとつ夜の秋 信子(桂)
などが目にとまったが、以前からこの季題で好きなのは、
西鶴の女みな死ぬ夜の秋 かな女(長谷川)
である。「西鶴の女みな死ぬ」がすごい。とここまで書いて、かな女の、西鶴の句については、すでに一回紹介したかに気づく。
それはともかく「夜の秋」と並んで挙げられている「万縁」、これが新しい夏の季語として認知されたのは中村草田男の、
万緑の中や吾子(あこ)の歯生え初(そ)むる
によって「たちまち全俳壇的に共感されて」意向、多くの俳人から数々の句を生むこととなる。ちなみに草田男は、戦後創刊した自らの句誌名を『万緑』としたーーというのも俳句に親しむ人たちの間ではよく知られたこと。
芭蕉の先に紹介した「新しい季の詞の一つも見出すのは後世へのよき冥加」という言葉ではないが、草田男は「吾子の歯生え初むる」で「万緑」を新しい季語として今日に残したのである。
恐るべし、一句の名句の誕生。
この山本健吉による単巻、一冊本の歳時記の傍らにハンディーな「季寄せ」(昭和四十八年・文藝春秋)があるが、こちらは上・下巻本なので、今回はとりあげず。また、複刊本となると、歳時記の決定本のひとつ『最新俳句歳時記』(全五巻)や、『地名俳句歳時記』(全八巻)があるが、これらについては、この後の山と積まれた複刊歳時記について総覧するときにふれてゆきたい。
さて、次は金子兜太へんによる『現代俳句歳時記』と兜太・黒田杏子・夏石番矢といった現代人気俳人の編となる『現代歳時記』を見てみたい。
前衛俳句運動を牽引してきた、また「銀行員等朝より蛍光す烏賊のごとく」「おおかみに鶯が一つ付いていた」といった句を作る俳人の季語感を知りたいじゃありませんか。
興味津々。

