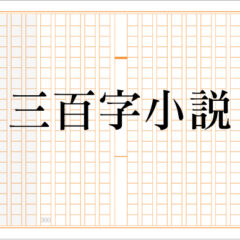B29を見た男 浜井 武

一九三八年(昭和十三年)生まれの私は、敗戦の日を、小学一年生のとき、二度目の疎開地だった愛知県の山奥で迎えました。 祖父が日本の植民地政策に乗っかって、満州と朝鮮に、「大阪屋号書店」という出版社兼取次業(戦後の取次店・大阪屋とは無関係)を手広く展開していたので、わりと裕福な家庭でした。
しかし、敗戦と同時に外地の資産は全て失い、私が生まれた日本橋呉服橋(今の中央区八重洲)にあった本店も空襲で焼失し、いっぺんに生活の手段を失いました。
戦時中、幼稚園児だった頃の記憶は断片的なもので、それより前の呉服橋の赤ん坊時代もちろん、父母が一時白金に住んでいた頃の幼児期のことも全く記憶にありません。
品川の御殿山に移ったあと、八ツ山橋際にあった森村学園幼稚科に通ったのですが、子供の足では十分以上かかるので、ふだんは担当の子守さん(四人の子供にそれぞれ子守が付いていた)に送ってもらったのでしょうが、遅刻しそうになると、パッカードという祖父の自家用車で送ってもらった記憶があります。
幼稚園では、ちょっと可愛い女の子(今でも名前を覚えています)がいて、その子と一緒に駆けっこするときは、わざと負けるように遅く走ったものです。後年、といっても、初等科時代の話ですが、同級生に「オンナに甘いさん」と仇名を付けられましたが、そいつは「ハマイ」をフランス語読みにすると、「アマイ」になると知っていたのでしょうか?
これは三十年の前の話ですが、銀座のバーで(酒は飲めなくても、時間外が稼げるので作家とはよく銀座に行きました)吉行淳之介さんに、「ぼくはB29を見てるんですよ」と言ったことがあります。すると吉行さんに「『B29を見た男』というのは、小説の題になるなあ」と言われましたが、そんな小説は書いていないようです。
空襲警報が鳴って、庭に堀った防空壕に逃げ込んだり、夜空に探照灯に照らされたB29の編隊が、高射砲の届かないはるか一万メートルの上空を、キラキラと銀色に機体を輝かせて飛ぶさまは、子供心には怖いというより、ワクワクするような気分でした。
私は長い間、自分が見上げたB29は、一九四五年三月のいわゆる東京下町大空襲で飛んで来たものとばかり思い込んでおりましたが、二歳上の兄の記憶によると、二月にはもう疎開していた、というのです。となると、あのB29は、いったいどこで見たのでしょう?
父は敗戦前年の一九四四年に赤紙が来て、千葉県柏の歩兵連隊でにわか訓練を受け、中国大陸に連れていかれました。留守家族の私たちはも、いよいよ東京もあぶない、ということで、神奈川県の葉山にあった別荘に疎開することになり、幼稚園を「中退」した私は、葉山小学校に入学しました。
葉山という所は、海水浴にはいいでしょうが、疎開先としては適していませんでした。三浦半島の背中合わせに横須賀軍港や浦賀ドックがあり、山の上には高射砲の陣地があって、格好の攻撃目標となります。高射砲から放たれた弾丸は空中で炸裂し、触っただけで手が切れてしまうような、ギザギザの鉄の塊が落ちてきて、屋根をぶち抜いたりするのです。私たちの家の庭にも、落ちてきました。
また、横須賀攻撃に加わったアメリカのグラマンF6Fは、機体を軽くするためなのか面白半分か、帰りついでに市街地を機銃掃射して行きます。道路には点々と穴が開き、犬が撃たれたりしたそうです。
ここも危ないということで、直参旗本の末裔を自認する母方の祖母は、長女を嫁がせた浜井の家名断絶を避けようと、長男の兄と、兄が死んだときの補欠要員として次男の私とを、自分の故郷である愛知県の山の中に、再度疎開させます。さすがに今度は空襲の心配はありませんでしたが、ひよわな都会っ子は、いじめの対象になりました。
そして、敗戦。私には、同い歳で広島の原爆投下に遭いながら奇蹟的に助かった「はだしのゲン」の作者・中沢啓治さんや、東京大空襲で逃げ惑ったという二歳上の毒蝮三太夫さんのような、強烈な戦争体験はありませんが、それでも、ああ戦争が終わってよかった、という解放感は、今も忘れられません。
アジア太平洋戦争と呼ばれるあの戦いで、大日本帝国が敗れたのは、むしろ良いことだった、と思うようになるのは、もっとあとのことですが、それでも幼いながら、もう灯火管制もしないでいいのだ、という平和の有難さは、身に沁みて感じたものです。
一旦、父方の祖母と母と弟が待つ葉山に戻って最初に覚えた英語は、「ギブミー・チューインガム」と「ギブミー・チョコレート」。父も無事復員して来て、宇都宮に学童疎開していた小学五年生の姉も戻り、一家は焼けずに残った品川の家に戻ることができました。
しかし、外地での資産と仕事先を全て失ってしまった父には、もう出版取次業を再開する気はなく、数ある道楽の中から、社交ダンスを教えてわずかな小遣いを稼ぐほかは、好きな講談で生きていこうと思いきります。
出版関係の若社長と結婚したつもりだった母は、それには我慢がならず、小学校の調書で「保護者の職業」という欄には、とっくに失ったはずの「出版取次業専務取締役」という肩書をずっと書き続け、「キミのお父さんは講談師だろう」と言われ、私は返答に困りました。(注 浜井氏の父浜井弘は誰あろう、かの講談界隆盛の礎を築いた二代目神田山陽その人である。弟子には人間国宝神田松鯉はじめ多くの女流講釈師、さらには、孫弟子には今人気沸騰の神田伯山らを輩出)
戦後、講釈師は忠君愛国の手助けをしたといわれて、落語家よりも生きにくく、ましてや素人の旦那芸が商売になるわけがありません。金目の物を売り払って凌いでいく、文字通りの竹の子生活が始まります。
ある日、座敷に子供たちが集められ、床の間に掛けてある横山大観の「富士山」の掛け軸を見せられると、次の日には無くなっています。また別の日には、竹内栖鳳による「竹林の雀」を見せられ、これも翌日には、姿を消します。
私が覚えていたのはこの二つですが、父が書いた『桂馬の高跳び』(注 副題は「坊ちゃん講釈師一代記」1986年光文社刊 2020年中文庫 解説神田伯山)が中公文庫になったので読み直してみたところ、びっくり。なんと川合玉堂、下村観山、川端竜子、橋本関雪、伊藤深水、上村松園といった人たちの、祖父が楽しみで集めた絵画が、日本橋T百貨店などの画商に、それこそ二束三文で叩き売られていたのです。オイオイ、子供四人にせめて一枚づつでも残しておけよな、と言いたいところですが、まあ、そのお金で生き延びたのだと思えば、仕方がないことなのでしょう。
しかし、そんなことでは、焼け石に水で、とうとう私が小学四年生の時、二百坪以上あった御殿山の家を、これも騙されたような値段で売り払い、私の生まれた呉服橋へと移り住みます。
空襲で焼けてしまった(大阪屋号書店)本店の跡地には、母方の祖母が始めた喫茶店と、祖母の末娘で宝塚出身の叔母と結婚した、映画俳優の水島道太郎の家が建っていて、私たち家族は水島の家へ移り住みます。
水島の叔父さんは、私たちをとても可愛がってくれて、釣り好きが高じて狩野川に面した大仁へ引っ越した時も、自分の運転する車で大仁を案内してくれたり、京王多摩川にある日活か大映だかのスタジオで長期の撮影に入った時には、仮住まいの多摩川で、水遊びに連れて行ってくれたりしました。
彼は、「泳げるようになるには、水の中で眼を開けなきゃだめだ」といって、私の頭をつかんで川に漬け、「目を開けているか」と訊くのです。「うん、開けてる」とウソをつくと、「じゃあ、おじさんがグーかチョキかパーを出すから当ててごらん」と言うので、これには参りました。
呉服橋の家は、東京駅八重洲口の目の前なので、近所にビルが建つ前は、物干し場に上がると、東海道線の発着がよく見えました。
学校は転校しなかったので、東京品川間を電車通学することになり、子供にとっては嬉しいことでした。時間に余裕がある帰り道は、省線には乗らず、品川駅のホームで東海道線の列車を待ちます。
ご存じのように、いやご存じないかもしれませんが、EF56かEF57など、一輌の電気機関車が長い客車を牽引するので、発車直後は人が歩くよりも遅く、だんだんと速度を上げていきます。そこで悪ガキは列車に合わせてホームを走り、もう無理だというところで、デッキに飛び乗るのです。当時の客車は手動扉でしたから、こんな芸当ができました。
そして停車するのは、新橋、東京という、日本有数の著名駅だけ。ああ楽しかったなあ。
品川駅も思い出の多い駅です。品川駅ときいて、中野重治の詩「雨の降る品川駅」を連想する人がいたらすごいと思いますが、こっちはもっと楽しい思い出です。
昔の品川駅には、貨物専用の品鶴線との関係なのか、駅構内に運河が入り込んでいました。
子供たちは駅で入場券を買い、芝浦川の東口(現南口)へ通じる長い長い渡り廊下を通って、運河に降り立ちます。そこで、セイゴやボラが釣れるはずです。「はず」といったのは、友達のリールを借りて勢いよく投げたら、リールごと飛んでいってしまい、釣れなかったものですから。
水島道太郎と結婚した宝塚の叔母は、山鳩くるみという芸名で、越路吹雪の一年上級生でした。戦争中の宝塚ですから一年でも先輩の上級生が連れてきた汚いガキにでも、愛想よくしないわけにはいかず、越路さんに「高い高い」をしてもらったのが、私だったのか、兄貴だったのか、いまだに二人の間で決着がついていません。叔母の山鳩くるみにも少しはファンがいたようで、生前の小泉喜美子さんに、叔母の芸名をつげたところ、あの小泉さんが「えっ、コバ!?(本名小林の略)」絶叫したのでした。愛知の疎開先にも叔母を慕ってついてきたガラス屋のお兄さんは、戦後になると、私をよく宝塚を観に連れて行ってくれました。
本来の東京宝塚劇場は、アニーパイルといって占領軍に接収されていたので、有楽町の日劇を借りていました。その十五日間の公演を欠かさず毎日観にいくのです。そんな小遣いがどこにあったのかふしぎですが、子供の私の分はタダだったのでしょうか。
毎日聴くのですから、さすがに歌は全部覚えてしまいました。演し物の「真夏の夜の夢」の中で歌う「筏乗りの歌」とかは、今でもソラで歌えます。
日劇と有楽町の間には、闇市が広がっていて、そこで生まれて初めて飲ませてもらったミルクセーキのうまかったこと!世の中にこんなにおいしいものがあったのか、とびっくりしたものです。
うん、まだらボケっていうのか、どんどん思い出してきたぞ!
でも、これ以上書いたら安倍さん、じゃなかった(これはひどい間違い、すいません)阿部さんに迷惑かけるので、この辺で止めときます。
おとなはみんな子どもだった