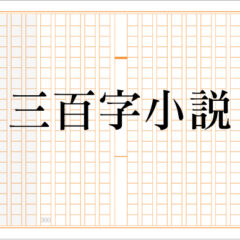山あいの町

伊藤謙介
私は山あいの町で生を受けました。
中国山地の奥深く抱かれ、清流に沿って縫うように走る街道の両側に、張りつくように民家が立ち並んでいました。
そんな田舎町に、日華事変の年に生まれ、太平洋戦争の開戦を四歳で迎えたのです。
しかし、激動する時代の足音も、山あいの町からは遠いものでしかありませんでした。
とりわけ、わずかな田んぼしか持たない、貧しい農家に生を受けた少年にとって、時代は雑音まじりに聞こえてくる、ラジオの向こうに、おぼろげにかすんでいるだけでした。
海を初めて見たのも、小学校の修学旅行で瀬戸内海を訪ねたときでした。今も大海原は私にとって憧憬の対象です。
親から「勉強しろ」と言われたこともないし、したおぼえもありません。ただただ、真っ黒になって、一年中、川で魚たちと遊んでいました。
そんな子ども時代は、今も私の中で、鮮やかな光を放ち、輝き続けています。
「かがしら」釣りという釣りをしました。
竹竿から伸びた糸の先に、五本の毛針と浮きをつけます。そんな仕掛けをもって、夕方、陽が西の山に輝く頃、いつもの浅瀬に出かけていく。
竿を上手に振り抜き、ねらいの場所にぴたりと落とします。
夕暮れ時に水面を飛ぶ虫をねらっていた「はえ」が、川面を跳ね、毛針に食いつきます。
白い魚がさざ波をたてます。私の心は、釣竿の動き、せせらぎの音と共振し、静かに奏でる音楽のようにさざめいていたのでしょう。
薄暮の空には、虫を求めて、蝙蝠が乱舞し、闇がさらに色濃くなるころ、少年は、揚揚と釣りの成果をもって、家路をたどります。
「釣れたかな」
母の明るい声が玄関に響き、私が差し出した、びく一杯の「はえ」を、母は串に刺して、炭火で焼いてくれて、醤油を少しつけて食べると、貧しい食卓は華やぎました。
月もない夜には「夜ぼり」に行ったりしました。アセチレンのガス灯とヤス、網をもって、川に出かけて、流れにそっと足を踏み入れ、浅瀬に忍び寄り、岩間に寄り添うような魚影を、網ですくい、ヤスで突きました。
そんな夜は、闇の底で生き物の不思議な鳴き声を聞きました。岸辺の草むらで小さな獣の気配がし、ガス灯の光が川面を不気味に照らします。私は魚を求めて、秘かで小さな冒険の旅に出るのでした。
「うなぎかご」もよく仕掛けたものです。
流れの速い所に、獣道のように、魚が通る道筋があります。そんな場所に前夜にかごを置いて、翌朝、陽もまだ昇り切らない頃に、川へと急いだのです。
流れからかごを引き上げ振ってみると、うごめく魚の気配がします。小さな少年は歓声をあげました。
山峡の町には、まだ陽がのぼりきる気配はありません。山鳥の声が、東雲の空に響きます。
「穴づり」という方法でも魚をとりました。
細い棒の先にミミズをつけ、いしがきの隙間にそっと差し入れると、激しい衝撃が五体を走り抜けました。太いウナギが食いついたのです。大きなナマズや、大人の掌くらいのカニがとれることもあります。そんな日は一日中上気して、夜もなかなか眠れませんでした。
「明日も、また行こう」
ようやく白みはじめた裏庭で、ニワトリがひときわ高く鳴きました。
今も、はるかな郷愁とともに思い出す、川と魚とたわむれた少年時代、それが、私の原点です。
今でも、故郷に帰れば、川面に竿を振ります。一瞬のもとに、すべてを忘れ、少年時代に立ち返ります。忘我の境地とは、こういうものでしょうか。
こんな時代があった
岡山県の片田舎に生まれた私は、八歳の時に終戦を迎えました。家は農家で、兄弟が五人もいて生活は楽ではなく、ひもじい子供時代を過ごしました。
今から五十年以上も前、ずいぶん昔のことです。
朝五時、私はいつものように目が覚めて、朝の支度にかかりました。
中国山地の山あいにある町の夜明けは遅く、外はまだ暗いなか、朝食の準備と弁当をこしらえる母の台所で働く音が聞こえてきます。弁当といっても米がなく、蒸したジャガイモが三個入っているだけでした。けれど、ふだんからイモのつるや、イナゴやハチの仔などをとって食べていることを思えば、贅沢は言えませんでした。
学校かばんを持ち自転車に乗り駅へ向かいます。舗装されていないひどいデコボコ道が三十分近く続きます。貧しい農家の子どもにバスの乗るお金はなかったのです。道幅一杯に走り抜けるバスがまきあげる猛烈な土ぼこりのなかで、むせながら懸命にペダルを漕いでいました。
駅に自転車をおいて汽車に乗りかえます。一時間ほど揺れながら学校の最寄り駅について、ここからは徒歩で向かいました。バスはあるのですが、乗車賃がもったいなくて歩きです。
私は学びたい、勉強するんだという一心で、このような長時間の通学にも、貧しさにも「負けるもんか」と、いつも歯を食いしばっていたように思います。
春一番が吹き荒れる春先の日も、ギラギラと太陽が照りつける夏の日も、強風が襲いかかリ雨がたたきつける秋の日も、山道に小雪が舞い凍てつく冬の日も、毎日二時間ほどかけて、学校に通い、一日たりとも休むことはありませんでした。
放課後とて、ぐずぐずしてはいられません。特に日の短い冬はすぐに太陽が西にかたむき、デコボコ道を自転車を漕いで、家に着く頃にはいつも日が暮れて真っ暗でした。
帰り道、山あいに立つ家の灯りがほのかに見え始めるときには、学校に通えること、またなんとか食べていけること、そして健康で元気で生きていることに、なんともいえない感謝の思いがわいてくるのです。
なぜなら、いつも私の頭の中に、懸命に働く母の姿があったからです。まえの晩は一番おそく寝たはずなのに、翌朝は四時というとすでに起きだして、井戸から水をくみ、かまどに火をおこし、五人の子ども全員の弁当を用意してくれました。そんな母のことを思えば、弱音どころかいつも「明日もがんばろう!」と、心に誓ったものです。
私だけに限らず、昭和の二十年代はほとんどの人が、多少の程度の差こそあれ、このような環境の中で育ったのではないでしょうか。しかし、そんな日々が人生を生きていく上で、本当に大切なものを与えてくれ、教えてくれたと思うのです。
私の例ですが、まず頑健な身体をつくってくれました。病気らしい病気もせず、仕事に打ち込む人生を送ることができたのも、毎日の通学で、健康の基礎となる体力をつくることができたからに違いありません。
「忍耐力」も養われたようです。健康だけでなく、人生ではどうすることもできない困難に直面することがあります。そのようなときに、泣き叫んでみてもどうしようもない、ただただ、じっと歯をくいしばり、耐えながら乗り越えていくしかない、ということを学びました。
襲いかかってくる風がいつまでも続くことはありません。吹き荒れる風雨に負けることなく、じっと耐え抜き、さらに
努力を重ねていけば、嵐の後には大空に七色に輝く虹がかかるように、人生では必ずすばらしい幸運にめぐりあうことができるのです。
つらく苦しい生活の中で、少しは「意志」を強く持つことができました、自分が学校に行くときめたいじょうは、何があろうと、絶対に負けたくなかったので、体調が思わしくないときなど、ついへこたれそうになったけれども、その度に、「負けるな!」と自分を励ましてきました。
白い秋
父の生家は山峡の小さな集落にあった。源平の争乱に敗れた平家の落武者の隠れ家もあったと父から聞いたことがある。実際に、生家を背負うようにそびえる裏山の頂に立つ小さな石碑は、平家の落武者の墓であろうという。
隣家はずいぶん離れたところにあり、まさに一軒家といった風情であった。家の周りには畑が広がり、よく猪や兎が作物を荒らした。庭には数本の大きな柿の木があり、たくさんの草花が植えられている。
牛が二頭飼われ、鳥が数十羽、広い庭に放し飼いにされていた。
少年時代、その家に泊りがけで、父に連れられ、よく行った。
思い出は今も鮮明に残っているが、とりわけ子供心に印象に残ったのは、厠(かわや)であった。母屋からずいぶん離れ、深夜に用が生じると下駄にはきかえ、とぼとぼと白い月光を浴びながら歩いていかなければならなかった。
白い草花の一群が月の光に幽かに揺らめき、いかにも不気味だった。
厠の前には白い花をつける百日紅があり、季節ともなれば、白い着物をまとった女性に見えた。用を済ますと、少年は後ろを振り向かず一目散に母屋へと走り帰った。
ときに、狐の遠吠えも聞こえてきたものだ。
しかし、昼間の静寂に包まれた山峡の美しさは、少年の心をとりこにして離さなかった。そんな山間の集落に、観音寺という古寺があった。
父から赤松月船(げっせん)という名をたびたび聞いた。奇妙な名前の人がいるものだと不思議に思っていたが、しばらくして、月船が観音寺の僧侶であることがわかった。
同時に生田長江に師事し、草野心平、佐藤春夫、室生犀星と交流のあった著名な詩人であることを知った。
父は、春や夏の催事を通じて、月船と交流を深めていた。
そんなこともあってか、幼い私ではあったが、赤松月船の詩集を折に触れ、ひもといた。
それから、もう半世紀が過ぎた……。
夜も白々と明ける頃、詩集を手に再び庭に出る。小さな庭の木々の影が日ごとに夏の力を失い、秋の気配を深めていく。
久しぶりに月船詩集のページをめくる。「秋冷」という短詩に目がとまった。
深い渓流に臨んだ
断崖の家の窓から乗り出し
髪をすきながら
その白い裸身を
惜しげもなく
朝の嵐気に晒している婦は
何といふ爽やかな秋冷でせう!
(赤松月船詩集『秋冷』所収)
少年のころの父の生家の周りに漂う、白い秋の静謐な美しさを思い返す。まさに月船の「秋冷」の世界であった。
片隅に咲く百日紅の白い花が空気に融けこみ、可憐な風情をみせている。しかし、わずかな時を経て、枯れていくのであろう。
透明な青いそらの底を、一筋の白い雲がゆっくりと流れていく。
美しい秋だ。
違うことなく時を刻み、うつろうき季節。
生も死もすべてのものが秋空の彼方に消えていく。
昭和十二年 岡山県生まれ 昭和三十四年京都セラミック(現・京セラ)の創業に参加。主に開発・製造畑を歩み、平成元年・社長、会長を経て相談役。経営の第一線を退いたのちは、晴耕雨読の日々を送る。趣味は読書、美術鑑賞、散歩等。
おとなはみんな子どもだった